 ��ՒT�K
��ՒT�K ��ՒT�K
��ՒT�K
�q���̍����狻�������������j���ɍl�Êw�W�̈�ՒT�K���n�߂܂����B
�Ƃ���߂����}�ڍ����A��䒬�������ɂ͓��ɂɑ�R�̌Õ�������܂��B�ŋ߂ł͓����ɂ��钆���̏�Ղ�K�˂Ă���B
�s���ɂ͖�100�P���A�s�S�̂ł�200�����Ղ�����Ƃ����B
�썑���ɂ��镶��14�N(1817�N)�ɍ��ꂽ�x�m�ˁB�]�˔��x�m�̂ЂƂ�����6���[�g���قǂō��ڐȂ�30��c����Ă���B��������Ɍ��ݒn�Ɉړ]���ꂽ���A�s���ł��l�ԖڂɌÂ��B |
 |
| �썑�� �ܑ㏫�R�j�g��1681�N�ɐ���j���@�̔���Ō����B�]�˂̖ʉe���c�������Ȃ��^���@�L�R�h�̎��@�B�d�v�������̖{���ȂǑ����͓����̂��́B�������������͋C�̒��A�]�ˎ������������B�����ɂ͑�G�d�M�A�O�������A�R�`�L���Ȃǂ̗L���l�̂��悪����B |
 |
| �V����(�F��_��) ��c���X�ɂ���k�����Ɛb����������̏�ՂƂ�����B����n�̐�[�ɂ���A�܂��ɍD���n�B�������ɂ͋��r�㓹���ʂ�B���݂͌F��_�ЂƑP�c���ƂȂ��Ă��邪�A�n���͕s������������̗��̍ہA���哢���̐폟���s��ꂽ�Ɠ`���B�P�c���͐_�������܂ŕʓ����ŐV��`���Z�l�O�̂��悪����B |
 |
| �F����(2023.3.29) ����12�V��̂ЂƂō���B��Ï���ڒz�����ƌ����A1607�N(�c��12�N)�Ɋ����B����V��́A�F���ȊO�͕P�H�A���{�A��R�A���]�����B�[���璷���A�Ȃ������Βi�̓�������A�Â��A�����A�}�ȊK�i��o�邪���ꂪ��ς������B�z�铖���̂܂܂Ȃ̂ŁA���R�G���o��Â炢�\���Ȃ��߁A�]�����������ɂȂ�B����ʼn����H���͓���Ǝv�����A�����̊댯���������Ǝv���B���N����q���ɗD�����\���ɐ���Ƃ������Ăق����B |
 |
| ������(2023.3.29) ���Ր_�͓��{�ŏ��̒j���_�Ƃ����Ɏדߊ��_�ƈɎדߔ���_�œV�Ƒ��_�̐e�_�B���ɐ��Q�������֎Q��A���ɐ��̂�����̎q�ł�����ƌ����A�����̑�_�ł��艄���E�����сE����̐_�Ƃ��đ����̐M���W�߂Ă���B�N��170���l�̎Q�q�q������Ƃ����B���q����̖ÏP���̎��A�k�����@���O�G���U�̋F�����������ƂŗL���B���y�Y�̎��݂ؖ��L���Ŕ��������B |
 |
| ���O�����(2023.2.1) �]�ˎ���ɕs�E�r�𐅌��Ƃ���E��ɉ˂����Ă����O�̋��B�����ɂ������͓��쏫�R�����i���ɎQ�q����ۂɒʂ������͌䋴�ƌĂꂽ�B�����G��]�˖����}��ɂ��`����Ă������A��������ɈË������ꂽ�B�ŋ߁A���̈ʒu�̋߂��ɕ����ۑ�����Ă���B�Ö����̂���݂݂̂͂��̓X���̗R���Ƃ����B |
 |
| �ُˎ�(2023.2.1) ����ƌ��̓���t���ǂ̕�B���͖��q���G�̏d�b�V�����O�A��͈�t�Ǔ��̖��B��t�����̍ȂƂȂ邪�A����ƂȂ邽�߁A���������`���Ƃ����Ƃ����Ă���B�剜���x���\���I�ɐ������A�����I�ɂ��e���͂��������Ƃ�����B�܂��A�����̑O�𑖂�t���ʂ�̗R���Ƃ��Ȃ��Ă���B�⌾�Ŏ�������̒�������邽�߁A����̏㕔�ɑ傫�Ȍ����J�����Ă���B�����ɂ͌��v�̈�t�Ƃ̂��������B |
 |
| ����_��(2022.6.15) �����̍���V�{�ʼn��쎮�ЁB���݂ł͗]��m���Ă��Ȃ����A�����ɂ͌�k�����⑾�c����̑��h�Ă���B�{���ɂ�����_�Ђ�����A������̔×��ɂ�鐅�Q�ɂ��J������Ė{�ЁA���Ђ�2�ЂɂȂ����Ƃ����Ă���B�_�Ђ̑O�̂��˂��˂������H������L������n���̐ՂȂǂ��Ă̑�����̐��^�̗v�ՂƂ��ĉh�����ꏊ�Ǝv����B���Ȃ݂ɑ�{�̕X��_�Ђ͎O�m�{�B |
 |
| ��X�ؔ������(2022.6.1) ��X�ؔ����ɂ���ꕶ����̕����Z���ՁB1952�N�ɔ��@�������ꂽ�ꕶ����(��4500�N�O)�̒G���Z���ՁB���w�@��w�̔�����V�����̎w���̂��Ƃŕ�������Ă���B�W����32m����A�����J�u�˂̓�ɓ˂��o���������̒[�Ɉʒu���Ă���B���̏ꏊ������\�����y���Ί�ނ��o�y���Ă��āA�߂��ɓW������Ă���B |
 |
| �����X�_�Еx�m��(2022.6.1) ��ʃ��J�̔����X�_�Ђɂ��銰�����N(1789�N)�ɒz�����ꂽ�x�m�ˁB����܂ŒʔN�o�邱�Ƃ��o���A����߂��ɂ͕x�m�R�̗n�₪�z����Ă���B����6���A���a25���œs���Ɍ�������ŌÂƂ����]�˔��x�m�̂ЂƂB�s�w��L�`�����������B |
 |
| �����{���F��_�ЌÕ�(2022.5.15) �����7���I�ɍ��ꂽ��~�������ō��̎j�ՂɎw�肳��Ă���B���{�ɂ͐��Ⴕ���Ȃ��������`��10�N�قǑO�ɐΕ����������ꂽ�B�����̈�ӂ�32m�A��~�͒��a16m�A�c�O�Ȃ��畛���i�̖w�ǂ������Ă��邪�A��K�����K���X�ʂȂǂ��������Ă���B�܂��Ύ�����͂����̓B��@�ەЂ���������A���Ȃ�g���̍����푒�҂Ɛ��肳��Ă���B�����c���̌����҂��A���l��������Ȃ��B |
 |
| �ԉH����(2021.9.29) ���H�̈���`��Ɩk��ԉH�̎j�Ղ�K�˂��B �ԉH�����́A�����̕������n���֓�����ɓ��k�[�ɓ˂��o�����ʒu�ɂ���B����3�N(784�N)���c�����C�����Α叫�R�Ƃ��ĉڈΐ����̍ہA�w��~��3�����������폟�F�肵�����Ƃɂ��n�����ꂽ�B���̌㌹�����A�����A���c���ɂ��ċ����ꂽ�B��n�̏�Ɍ����A�Ж����̉��ɏ�z�A�k���V�����A�鋞���̃g���l��������Ă��邽�߁A�S���t�@���ɂ͐l�C�̂���X�|�b�g�ɂ��Ȃ��Ă���B |
 |
| ��t�隬(2021.9.29) ���̂Ƃ��뒆���̏�Ղ�K�˂Ă��邪�A����͑��c���z�邵����t�隬�Ɍ��Ï����Ɩ@�^����K�ꂽ�B �@�^���͓V�����N(1537�N)�ɓV�C��l�̒������l���J�R�B�������n�̒����ɂ���e�Ɋ�ΊX�����ʂ��Ă���B����ꂳ�ꂽ�͎R���̒낪�f���炵���B�V�ҕ������y�L�ɂ��ڂ��Ă���B �Ï����́A��ΊX�������ɂ���O�����u�˂Ɉ͂܂�Ă���B���c���]�ˏ�Ɗ�Ώ�𒆌p����R��Ƃ��Ēz��B���a62�N�̔��@�ɂ���x���m�F����Ă���B���c����̎���1504�N�ɓ���̈ꑰ�����Ƃ��Č����B�]�ˎ���ɑ��c���̕�Ƃ���A����N(1655�N)�ɓ���̖ؑ������u���铹�����c���ꂽ�B |
 |
| �n���隬(2021.8.21) ��c��n���ɂ������Ƃ���钆���̏�ՁB�퍑�����k�����̉Ɛb�������ܘY�̏��̂ɂ������Ƃ����B���͖k��_�ЁA���͓��a�_�ЁA��͉P�c�≺�A�k�͔n���}���ق܂łɋy�ԁB���̊ق͓��a�����ɂ������Ƃ�����B��̍\���͎��͂̋}�ȊR�ƒ�n�ɂ͓��삪����A�Ꮌ�n�т��L����V�R�̗v�Q�B�߂��̒r��{�厛���i���̏�^���ɂ������̏�Ȃǂ��������Ƃ����Ă���B�A��ɗ�������������i���䂩��̖������ɂ͉F����̐킢�Ŋ������n�̃u�����Y��������B�ŋ߁A�����̎��Ђƒn���̊W�ɋ����������Ē��ׂĂ���B |
 |
| �����O�q���@(2019.10.22) ���a13�N�ɍ����̍����̕ی��q���Ɋւ��钲�������y�ь��O�q���̕��y������ړI�ɋ@�ւ̌����B2002�N�܂Ŏg�p����A2018�N�ɍ`�拽�y���j�قƂ��ăI�[�v���B�����z�[���A���u���A����@�����Ȃǂ��ۑ�����Ă���B���ʂ̒����G���g�����X���猚���̈Зe�ɂ͈��|�����B �v�҂͓�����w�̈��c�u����v�������c�ˎO�B�悭�����̂悤�ȑ傫�Ȍ�������P�œs��(�`�攒��)�j�ꂸ�c���Ă������̂��B |
 |
| �m���V�c��(2019.9.8) ��s�̕S�㒹�Õ��Q�ɂ��鐢�E�ő�̑O����~���B�S����486���[�g���B�`�m���V�c�˂ƌ����Ă��邪�A���ۂ͕ʂ̔푒�҂��Ƃ����A���Õ��Ɗw��ł͌����Ă���B���E��Y�ɓo�^���ꂽ���A���ȏ��ɍڂ��Ă���S�̑��͎c�O�Ȃ����s�@���炵�������Ȃ��B�q���O�Ŏq���̂���O�x�ʼnj�������Ƃ�����Ƃ����{�����e�B�A�K�C�h�̏����̐������A��s�s������21�K�̓W�]��ɓo��B�挎�͓����ł������S�㒹�Õ��Q�V���|�W�E���ɎQ�������B����S�̂��݂���悤�Ȏ{�݂��]�܂��B |
 |
| �փ����Ð��(2019.9.7) 1600�N�ɂ������V�������ڂ̊փ�������B���R�̓���ƍN�Ɛ��R�̐Γc�O�������˂��A�������R�L�����������A���R�̏�����G�H�̗���œ��R�����������B����͗��j���������قƉƍN�̍ŏI�w�n�ՂƓ���˂����w����B�ŏ��ƍN���w���\�������z�R��O�����w���\���������R�������ɒ��߂�B���̒n�͌Â����琼�Ɠ��̂ŁA�Â��͕s�j�̊ւ�����A�p�\�̗��ł͑�C�l�c�q�Ƒ�F�c�q�����̒n���킢�܂����B |
 |
| �����(2019.2.10) 2019�N�Q���̉Ƒ����s�ŖK�ꂽ�B����(�t��)��1601�N�ɈɒB���@���z����n�߂�����B�t�R�ɍ��ꂽ�̂Őt��Ƃ�������B�������w�̖���ƌ�����B��m�ېՒn�͎s�X����]�ł��A�ɒB���@�̋R�n���ŗL���B�R�n���̑���ɂ͐��@�̎Ⴋ���̎p�̃����[�t������B�ȑO��Ђ̗��j������̃����o�[�ŖK��Ẳ��������v���o�����B�B�c�O�Ȃ����̈�\�͖����̑�⑾���m�푈�̋�P�ł��ׂďĎ������B |
 |
| ���P�a(2019.2.10) �ɒB�Ƃ̌�쉮�B���̓Ɗᗳ�ŗL���Ȑ��@�������Ă���B���Ƃ��Ƃ̌�����1637�N�ɑ��c���ꂽ���A����P�ŏĎ��������A1979�N�ɍČ�����A�n�������̑N�₩�ȐF�ʂ̒����╶�l���Č�����Ă���B���؈�ࣂ��͓��R��������ɓ`���Ă���B�{�����e�B�A�K�C�h�ɂ��ƈɒB�Ƃ͏G�g����Ƃɂ�����ꂽ9�̉Ɩ䂪����Ƃ����B�߂��ɂ�2�㒉�@�̕_����a�A�R��j�@�̕_�P���a������B |
 |
| �l����(2018.1.7) 2018�N�̐V�N�Ƒ����s�ŖK��܂����B�l����͓���ƍN���O�������ŕ��c�M���ɔs�ꓦ���A������ŁA���̌�A�ƍN���V�������ɂ��̏�ɓ���������喼���o���������Ƃ���A�o����Ƃ��ėL���ɂȂ�܂����B�V��t��140�N�Ԃ�ɍČ�����܂��̂ł����A�Ί_�͑n�������̖�ʐς݂̐Ί_���c����Ă��܂��B�܂��A�V���̒n���ɂ͈�˂������̂��̂��c����Ă��܂��B���̂Ƃ����N�̏x�{��ɑ����A�ƍN�̏�ɉ�������܂��B |
 |
| �o�C��ՂƏx�{��(2016.9.10) 50�N�قǑO�ɓǂo�C�̋L�^�ȗ��A���N����̓o�C�ɍs���Ă��܂����B���{�l�Êw���˂̒n�ƌ����Ă��܂��B�É��w����̃o�X���~���Ɩڂ̑O�̍L��ȏꏊ�ɐ��c�╜���Z�����_�݂��Ă��܂��B�܂��͕~�n���̔����قɍs���A���@���ꂽ�ؐ��i�Ȃǂ����w�B�c��Ȗؐ��i���悭�c�������̂��B�ŋ�775�_���d�v�������Ɉꊇ�w�肳��Ă��܂��B�{�����e�B�A�ɐ������A���������[�܂����B�x�{��͓���ƍN���]�˂Ɉڂ�O�ƔӔN�����������ꏊ�ŁA������E�Ȃǂ���������Ă���B����ɂ��铿��ƍN���₨��A���݂̂���̖�����܂��B���݂͌����ƂȂ�s���̌e���̏�ƂȂ��Ă��܂��B |
 |
   |
 |
| ���J��{�x�m(2016.7.1) ������_�Ђɂ���x�m�ˁB�V���N�Ԃ�1782�N�ɕx�m�R���n���D�ς݂��A���c����Ԃʼn^��z�R���ꂽ�B�z�R�����230�N�o���Ă��邪�A�����̎p���悭���߂Ă���B������5���[�g���قǂ����A�o�R�����W�O�U���ɐ݂����Ă��āA���傤�Ƃ����o�R�C���𖡂킦���B���J�͎R�J����6��30���A7��1���̂݁B���̏d�v�L�`�������Ɏw�肳��Ă���B���a�����܂ŕx�m�܌�͂����r��ٓ�������͂����傫�ȉ������������Ƃ����B ���J���Ԓ��A������̕ۑ���̕�����������z�z���Ă���B |
|
| ��ʃ��J�x�m��(2016.6.27) ��ʃ��J�̔��X�����{�����ɂ���A�������N(1798�N)�ɑ���ꂽ�Ƃ����A�s�̗L�`�����������Ɏw�肳��Ă���B����t�߂ɂ͕x�m�R�̗n�₪�z����Ă���B�R���ɐ�Ԑ_�ЁA����ɉ��{���A�r���ɓ��A�A�G�X�q��A�߉ނ̊���₪�Č�����Ă���B����ꂽ�����̌��^�𗯂߂Ă���s���ł͐����Ȃ��{�i�I�ȕx�m�ˁB�x�m�ˈē��}�͍ŋߐV�������ꂽ�B�A��ɖ����_�{�܂ŕ����A�v���Ԃ�Q�q�����B��������ɍ��ꂽ�l�H�̐X���݂��ƂɎ��R�̐X�ƂȂ��Ă���B�����������l���͂��ߊO�l�̊ό��q�œ�����Ă����B |
 |
| ���R�x�m(2016.6.17) �����攒�R�ɂ���x�m�ˁB���������Ղ���Ԓ��̂��J����A�o�邱�Ƃ��ł���B�r���ɂ������������A�����Ă���A�ڂ��y���܂��Ă����B����ɂ͏����ȎЂ�����A�G�߂̉ʕ������������Ă����B�O���̊ό��q���܂ߑ����̐l���o���Ă����B��N�͎c�O�Ȃ���o�邱�Ƃ��ł��Ȃ��������A���N�͖����o�邱�Ƃ��ł��ĂЂƈ��S�B����ŕi��x�m�������4�x�m�˂ɓo���������ƂɂȂ邪�A�{�Ƃ̕x�m�R�ɂ͂܂��o��Ă��Ȃ��B |
|
| ������x�m��(2016.6.14) �������Ԑ_�Ђɂ���x�m�ˁB���Ƃ��ƌÕ�������Ƃ���ɐ_�Ђ�����Ă���B�n����800�N�O�̊��q����Ŗk�𐭎q�����̒n�ɍՂ����Ƃ����Ă���B�������瑽����z���ɕx�m�R�����邱�Ƃ��ł���B�Q���̓r���ɂ͏��C�M�̕M�ɂ��x�m�u�����̑c�̐Δ肪����B |
|
| ������(2016.2.5) �I�B�˓��엊��̖��A�ƍN�̑��ɂ�����F�S�@�̕揊�B�r��{�厛�ɂ���i���@�ɂ��鋐��ȕB���ꂾ���L��Ȃ���͒������B�����̕P�̂��߂ɒ����̎̕���ɓ�d�̖x����炳��Ă���B����ɂ�2000�N�O�̖퐶����̏Z���Ղ�Õ�����̒������Õ��̈ꕔ���Č�����Ă���B�Õ�����͏��ւ�n����o�y���Ă���B�̘e�ɂ͎����B�̂���⋟�{��������A�M�̐[�����Â��B |
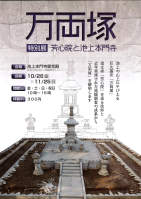 |
| �\��x�m(2015.12) �s�����x�m����̂ЂƂB�\��n��̐l�B���]�ˎ��ォ�猻�݂܂ŐM���Ă���B6��30���A7��1���ɑ�Ղ��Â���A�����̐l�łɂ��키�Ƃ����B�˂ɂ͖�30��̐Α���������A�V�۔N�Ԃ̋L�q������B���Ƃ��Ƃ����ɂ͌Õ�������A����𗘗p���Ă���炵���K�i������A�悭��������Ă���B |
 |
| �]�ˏ�V���(2015.12.6) �c������ʂ蔲���̋A��v���Ԃ�ɍ]�ˏ���U���B �V��t�͉ƍN�A�G���A�ƌ��̎����3�����A�ƌ��̎���ɖ���̑�ŏ������A�Ȍ�Č�����Ȃ������B�V���͓���41���A��k45���A����11���ŁA�V��t�̍�����51���������Ƃ����Ă���B���݂͓V���̏�܂ł͓o�邱�Ƃ��ł���B����NPO�ɂ��V��t�����v���W�F�N�g�������オ���Ă���B |
 |
| ��ё�ˌÕ�(2013.11.29) ���X�͉w����������ѕ����ɂ��炭�s���ƁA��ь���������A���̈�p�Ɍ����ɕ�����������Ă���B5���I�㔼�̔����L�`�O����~���ŕ����i�́A�S���A�S���Z�b�Ȃǂ̕���ނ̏o�y����֓��ŃX�o�����đ����Ƃ����B���u�ɂ͓o�邱�Ƃ��ł��A�e���X�ɂ͉~������(����)�����ׂ��Ă���B�܂��A���㕔�ɂ͖����̗l�q���킩��悤�ɕ����i���^�C���ɕ`����Ă���B |
|
| ��x�R�Õ�(2013.11.29) ���X�͕s�����炷���̖ڍ��ʂ�ɉ����ɂ���A���͌�Ԑ_�Ђ����������A���͖�Ɍ����������Ă��āA���ɓ��邱�Ƃ͏o���Ȃ��B���a42M�A����7M�̑O����~���ŁA5���I���̂��̂Ƃ����Ă���B�o�y�i�͓S���A�S�����Z�b�Ȃǂ�����A�푒�҂͕��l�Ƃ����Ă���B |
|
| ���X�͌k�J������Q(2013.11.29) �ڍ��ʂ肩�炷���̓��X�͌k�J�ɂ���A1���A2���A3����3���A3���悪�Ύ������J����Ă��邪�A�����͕ۑ������̂��ߌW�������Ă��č�ƒ��̂��߁A�c�O�Ȃ���߂��ɂ���͌��邱�Ƃ͏o���Ȃ��������A��Ƃ��Ă��������ȒP�Ȑ��������Ă��ꂽ�B�����5���I���炢�̂��̂炵���B�o�y�i�͐��c�J���y�����قœW������Ă���B |
 |
| �T�b�R�Õ��A�������Õ��Q (2013.11.20) �ڍ����̑�����w�ɂĉ��Ԃ������̂Ƃ���ɂ���A�A�N�Z�X�͂����Ԃ�ǂ��B�����̖ړI�́A�T�b�R�Õ��ƌÕ��W���������A��������̒��]�͍ō��ŁA�O��x�m�R�܂Ō������B�Õ���4���I����7���I�܂ł̂��̂ŁA�T�b�R�Õ��͍��w��̎j�Ղʼn`����Õ��Q�ő�̂��́B�܂��A�Õ��W�����ł́A�o�y�i�Ȃǂ��킩��₷���W������Ă���B�������Õ��Q�́A1������8����܂ł���A�������Ɍ��^���悭�ۑ�����Ă���B |
 |
| �����Ռ��w��(2013.11.22) �����̐V���ɖ{���̓���L�����p�X�ł̈�Ռ��w��̋L�����ڂ��Ă����̂ŁA���������s���Ă݂��B����\���ɓ���̂͏��߂Ă��������A�ӊO�ƈ�ʐl�������A���t�����C�`���E���o�b�N�ɊG���悢�Ă���l�����������B�܂��A�����͂��Ƃ��C�O�̊ό��q�Ǝv����l���݂�ꂽ�B�A��Ɉ��c�u����O�l�Y�r�Ȃǂ����ĉ�������A�c�O�Ȃ��瓌�呍�����������ق͋x�قł����B |
|
| ����̈�Ղ́A�֓���k�Ђŏ���������������̐}���ِՂƍ]�ˎ�����(150�N�O)�̉���ˑ喼���~�Ղł��B�˓@�Ղ���͈�˂�n�����Ȃǂ����@����A��������̂ق������⋾�Ȃlj������̎g�p�������̂Ȃǂ�������A�W������Ă����B����͐V���������l���ߌ�̕���100�l�ȏ゠�܂萷���ł����B���j�ɋ��������l�̑����ɋ����܂����B | |
Ryouji My Favorite