| 交流電化区間の拡大に伴い、直流・交流の双方で使用できる特急型電車として開発された車両。当初は60Hz向けが481系、50Hz向けが483系と別形式であったが、485系として投合された。車体は鋼製の20m級。台車は、451系で開発されたインダイレクトマウント式空気ばねのDT32AとTR69Aを採用。主電動機は国鉄の標準となったMT54系(1時間定格出力120kW)、駆動は中空軸平行カルダン、制御は電動カム軸式、制動は電磁直通(発電併用)で抑速ブレーキ付きである。先頭車は481系、483系、485系0番台が共通となっており、逆に中間車は485系0番台、200番台、300番台が共通になっている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国鉄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 481・483系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 481系は、落成とともに向日町運転所に配置され、1964年10月から「雷鳥」「しらさぎ」にて営業運転を開始した。続いて登場した483系は、仙台に配置されて、1965年10月から「やまびこ」「ひばり」にて営業運転を開始している。481系は赤スカート、483系はクリームのスカートで、その後の485系もクリームのスカートが採用されている。 481系として登場した車両は残っていない。鉄道博物館で保存されているクハ481-26は、483系として登場したもので、最後は勝田で訓練車になっていた。モハ484-61とともに、国鉄仕様に復元のうえ展示されている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015.12 クハ481-26:鉄道博物館 | 左:481系赤スカート、右:483系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 485系0番台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 485系0番台は、50Hz、60Hzの両方に対応した形式であるが、先頭車は481・483系と同じ形式。JR発足後も、東北から九州まで幅広く活躍した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987.3 「白鳥」:直江津駅 | 1984年頃 「ひたち」:上野駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 485系200番台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分割・併合運転を考えて、先頭車をボンネット型ではなく貫通型としたもの。新製時は青森と向日町に集中的に配置されたが、JR発足時には多くが九州に移っていた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990.2 「みどり」:佐賀駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 485系300番台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974年以降に製造されたものは、先頭車が非貫通型となり、300番台に区分された。東北地方、北陸地方に多かった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984年頃 「ひばり」:上野駅 | 1984年頃 「ひたち」:上野駅(左の車両) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984年頃 「鳥海」:上野駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 485系1000番台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐寒耐雪装備を強化したもので、秋田エリアを中心に配置された。非貫通型で、先頭車の外観は300番台とほぼ同じである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985.8 「たざわ」:盛岡駅 | 1984年頃 「あいづ」:上野駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987.3 「つばさ」:新庄駅 | 1988.3 「いなほ」:新潟駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 485系1500番台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北海道向けに耐寒耐雪装備を強化したもので、北海道初の電車特急「いしかり」として、1975年7月に営業運転が始まった。しかし冬季にトラブルが多発し、さらに耐寒耐雪装備が強化された781系が開発されることとなった。781系が量産された1980年には北海道から撤退し、本州で1000番台などと混用されている。下の写真は本州転属後で、屋根上のヘッドライトが2灯であることで見分けがつく。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987.3 「白鳥」:直江津駅 | 1985.8 「はつかり」:八戸駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国鉄時代の改造車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〇クハ481-600 クロ481を普通車化改造したもので、ボンネットの外観を残す。603が九州鉄道記念館で保存されている、 〇クハ480 特急「くろしお」を増発するため、東北新幹線開業等による余剰車を転用したもの。併結可能な4両編成にするため、中間付随車を貫通型先頭車に改造したクハ480形を連結しており、平面的な外観は特異だった。381系の「くろしお」と比較して速度が見劣りしたため1年半しか使用されず、多くの車両は福知山へ転属して、後に183系へ改造された。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016.8 クハ481-603:九州鉄道記念館 | クハ480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JR北海道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JR北海道発足時に、サロ481が6両、サシ481が1両所属していた。営業を行ったことはなく、部品取りのためと思われる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JR東日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青森運転所/青森車両センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青森運転所には、1972年の羽越本線全線電化時に、東北地方では仙台に続いて485系が配置され、「白鳥」「いなほ」などを受け持った。JR発足時の在籍は、6両編成11本と5両編成9本に予備車を含めた115両。1000番台が多かったが、300番台と1500番台の先頭車も混在していた。翌1988年に6両編成12本のみに再編され、受け持ちが「はつかり」「いなほ」のみになる。その後はしばらく大きな変動は無かったが、1996年から3000番台リニューアル車への改造が始まる。前面がFRP製のものに取り換えられたため、印象がまったく違うものになっている。 2002年12月の東北新幹線八戸開業後は、3000番台を除くと1000番台1本のみとなり、これは2006年に転属。3000番台は、6両編成7本が「はつかり」を中心に運用。2016年3月の北海道新幹線開業により運用が無くなった後も、しばらく28両が盛岡車両センターに移って残されていたが、2019年1月までに廃車。これにより、ジョイフルトレインを除いて485系が消滅した。 1972.10.2 「白鳥」「いなほ」等で運用開始 1988.3.13 5両編成が秋田転属、6両編成にThsc連結 1996.3.30 「いなほ」の運用終了 1996.3 3000番台への改造始まる 2002.12.1 東北新幹線八戸開業により、「はつかり」が「白鳥」と「つがる」に再編 2006.3.23 1000番台最後の1本が仙台に転属 2010.12.3 東北新幹線新青森開業により、「つがる」向けを4両化 2016.3.21 北海道新幹線開業により運用消滅、青森から盛岡へ転属 2019.1.22 全廃 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988.3 300番台「はつかり」:青森駅 | 2015.10 3000番台:青森駅(左の車両) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南秋田運転所/秋田車両センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秋田運転所には、1975年の奥羽本線秋田電化時に485系が配置され、「つばさ」などを受け持った。当初は300番台などもあったが、早い段階で耐寒耐雪装備を持った1000番台に統一される。JR発足後も転入があって最大125両が所属したが、山形新幹線・秋田新幹線の開業などにより運用範囲が減少。1999年の山形新幹線新庄延伸後は特急「かもしか」のみの運用になる。2010年に「かもしか」がE751系「つがる」となり、485系は役割を失った。 1975.11.25 奥羽本線秋田電化、「つばさ」にて運用開始 1988.3.13 青森運転所から5両編成転入 1992.7.1 「つばさ」「あいづ」の運用終了、「こまくさ」運用開始 1997.3.22 「たざわ」廃止、「いなほ」運用車が上沼垂転属 1997.11 かもしか色への変更始まる 1999.3.13 「こまくさ」廃止、「かもしか」運用のみとなる 2010.12.4 定期運用が消滅 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
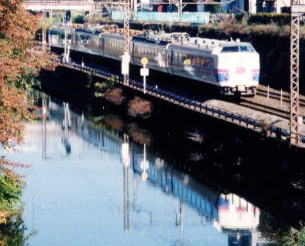 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995.7 1000番台:山形駅(左の車両) | 1998.11 1000番台かもしか色:山形駅付近 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝田電車区/勝田車両センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特急「ひたち」は、1972年から仙台運転所所属車で運用されていたが、1985年に勝田へ移管された。JR発足後もボンネットの0・100番台が主力で、M車には483系も残っていた。E653系に置き換えられて、1998年12月に定期運用終了。一度は訓練車を除いて消滅するが、2002年と03年に1000番台主体の編成が転入する。いるかのマークが付いた塗装で、波動用として活躍した。2013年1月に廃車となり、消滅している。 1985.3.14 「ひたち」運用車を仙台運転所より移管 1987.4.1 JR発足。9両編成18本が「ひたち」で運用 1990. 7両編成化 1992.3 ひたち色への変更始まる 1998.12.7 定期運用終了 2002.12.6 K60編成転入 2003.3.29 K40編成転入 2003.12.27 勝田色への変更始まる 2007.7.10 訓練車廃車 2013.1.23 全廃 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 左から勝田色、ひたち色300番台、ひたち色0番台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上沼垂運転区/新潟車両センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JR発足直前の1986年11月に、青森車などの転入により485系が配置、「白鳥」「雷鳥」北越」などで運用された。1996年と97年に秋田から6両編成が転入するなどにより、最大141両の体制。1000番台が中心であるが、先頭車は0・100・200・300・1500番台などバラエティに富んでいた。2001年に9両編成が消滅した後は、6両編成9本、4両編成2本の体制となり、その後は少しずつ減少。2014年以降、E653系への置き換えが始まり、2015年に営業運転を終えている。 1986.11.1 青森等からの転入により485系配置、9両編成が「白鳥」「雷鳥」「北越」で運用 1988.10 上沼垂色への塗装変更始まる 1996.3 秋田から6両編成2本転入、「いなほ」で運用 1997.3 秋田から追加転入し、6両編成10本となる 2001.3.3 「雷鳥」運用終了、9両編成も運用終了 2008.6 T18編成が国鉄色復帰 2015.3.14 定期運用終了 2015.5.30 最後の営業運転 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991.3 「白鳥」:青森駅 | 2003.8 300番台「くびき野」:柏崎駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002.4 1500番台「いなほ」:府屋駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青森地区に続いて、485系の大規模リニューアル工事によって3000番台が登場した。新潟地区では、9両編成2本、6両編成5本が、「はくたか」「北越」「いなほ」などに使用された。2015年にE653系に置き換えられて特急運用が無くなるが、JR西日本の交流区間に乗り入れられるという特性を活かして、新潟〜糸魚川間の快速に2年間使用される。2017年には快速運用も無くなり、消滅している。 1996.12 3000番台への改造始まる。当初は9両編成で「はくたか」「雷鳥」等で運用 2000.1 3000番台6両編成登場、「いなほ」等で運用 2005..1 9両編成の定期運用無くなる 2015.3.14 特急運用終了、新潟〜糸魚川間の快速のみとなる 2017.3.4 定期運用終了 2017.4 全廃 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016.6 東三条駅 | 2002.1 新潟駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仙台電車区/仙台車両センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仙台運転所は、東日本の50Hz対応483系が初めて配置されたところで、「ひばり」「やまびこ」「やまばと」「あいづ」などを受け持った。1985年の東北新幹線上野開業後は配置が一度無くなっていたが、1993年、1000番台主体の特急「ビバあいづ」が登場。その後、何度も車両の入換えがあり、「あかべぇ」編成、「臨時あいづ」編成など特徴的な列車が誕生する。最後は2016年に国鉄色のA1-2編成がラストランを行って消滅している。 1993.12.1 「ビバあいづ」運転開始(ビバあいづ色 2002.12.1 「ビバあいづ」に代わって、国鉄色による「あいづ」運転開始 2003.10.1 「あいづ」を快速「あいづライナー」に変更 2004.8.30 「あいづライナー」運転終了 2005. 「臨時あいづ」編成に改造 2007.3.18 「あいづライナー」運転再開(あかべぇ色) 2011.6.2 A1-2編成が国鉄色になる 2015.3.14 「あいづライナー」廃止により定期運用なくなる 2016.6.19 最後の営業運転(A1-2編成) 2016.8.4 全廃 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 左から あかべぇ編成、臨時あいづ編成、ビバあいづ編成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小山車両センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仙台運転所の臨時「あいづ」編成6両が転入し、2006年3月から東武線直通特急「日光・きぬがわ」として運用を開始した。2011年6月に253系へ置換えられて運用を終え、仙台に戻っている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日光・きぬがわ色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョイフルトレイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○シルフィード→NODOKA 1990年に登場した3両編成の欧風車両で、ディーゼル機関車に牽引されて非電化区間に入線することが想定されている。189系グリーン車の改造ということになっているが、車体は新製で、走行機器は485系のものである。2001年にカーペット車両に改造し、NODOKAという名称になった。2018年1月に営業運転を終えている。 ○リゾートエクスプレスゆう 1991年に登場した水戸地区の6両編成の欧風車両。5両は183系・189系、1両は485系の改造ということになっているが、車体はすべて新製である。2018年9月に廃車となった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017.3 NODOKA:新松戸駅 | 2017.2 リゾートエクスプレスゆう:船橋駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○宴・華 どちらも1994年・1997年に登場した6両編成の御座敷電車。485系の改造で、車体は新製されている。 当初は小山に所属し、2015年3月に高崎へ移管されている。華はリゾートやまどりとともに2022年まで活躍したが、同年10月に運用を終えている。 ○やまなみ・せせらぎ どちらも1999年・2001年登場した4両編成の車両。2011年に、このうち6両がリゾートやまどり、残る2両はジパングに再改造された。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016.10 華:勝田駅 | 2017.2 宴:東川口駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ニューなのはな 165系「なのはな」の後継として、1997年に登場した千葉地区の団体向けの6両編成。座席車とお座敷車両を切り替えられる。車体は、宴・華とほぼ同じものが新製されている。2016年9月にさよなら運転を行って廃車となった。 ○きらきらうえつ 2001年に登場した、4両編成の羽越線観光列車向け車両。車体は新製ではないが、大幅に改造されている。2019年9月に定期運用終了。12月に最後の営業運転を終えた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.7 ニューなのはな:高崎駅 | 2019.1 きらきらうえつ:西袋駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○彩(いろどり) 2006年に登場した、長野地区の団体向けの6両編成。車体の改造は小規模にとどまっているため、485系の雰囲気が残っている。2017年9月にさよなら運転を行って廃車となった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017.7 彩:平田駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○リゾートやまどり 2011年に、せせらぎ4両とやまなみの中間車2両を再改造した車両。基本は普通座席車で、団体やイベント列車に使用される。最後の485系となったが、2022年12月に運用を終えてる。 ○ジパング 2011年に、やまなみの先頭車2両と3000番台の中間車2両を改造して登場した車両。平泉への観光列車として運行された。2021年10月に運用を終えている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016.6 リゾートやまどり:大宮駅 | 2019.4 ジパング:二本松駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JR西日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 向日町運転所/京都総合運転所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 向日町運転所は、481系が最初に配置されたところである。九州方面の運用が無くなった後は、特急「雷鳥」を中心に運用されていた。2003年には旧「スーパー雷鳥」のパノラマ編成も転入している。2011年に定期運用を終了した。 1964.12.25 特急「雷鳥」にて営業運転開始 1965.10.1 特急「つばめ」「はと」運用開始 1975.10 山陽新幹線博多開業により九州方面の運用無くなる 2003.5-9 パノラマ編成が金沢から転入、国鉄色となる 2009.10.1 パノラマ編成を除いて運用終了 2011.3.12 「雷鳥」定期運用終了 2011.3.27 最後の営業運転 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987.3 300番台「雷鳥」:直江津駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金沢運転所/金沢総合車両所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特急「雷鳥」「しらさぎ」は、1964年から向日町運転所所属車で運行されていたが、1975年から金沢にも配置される。JR発足後は、「かがやき」「きらめき」、「スーパー雷鳥」、「はくたか」、「しらさぎ」と、それぞれオリジナル塗装があって賑やかだった。2003年に「しらさぎ」運用が無くなり、定期運用はすべて京都へ移管されている。 1975.3.10 「雷鳥」「しらさぎ」運用車が配置される 1988.3.13 「かがやき」「きらめき」運用開始(4両編成) 1989.3.11 「スーパー雷鳥」運転開始(7両編成) 1990.3.10 「かがやき」6両編成、「スーパー雷鳥」9両編成となる 1996.10-11 「はくたか」向け塗装変更(V01-02編成) 1997.3.22 「かがやき」「きらめき」廃止 2001.3.3 「スーパー雷鳥」「白鳥」廃止 2001.3-9 「しらさぎ」向け塗装変更(Y01-04、Y21-23、K11-13編成) 2002.3.23 「はくたか」運用終了 2003.3.15 「しらさぎ」運用終了 2003.6-9 「雷鳥」定期運用を京都へ移管 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989.8 「加越」:金沢駅 | 1989.8 かがやき色 (右はスーパー雷鳥) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 左から 2200番台かがやき色、はくたか色、2000番台スーパー雷鳥色、200番台しらさぎ色、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福知山運転所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986年11月の福知山電化の際、直流区間でありながら交直流の485系が配置され、特急「北近畿」にて営業運転を開始した。しかし、1991年に113系を交直流化して七尾線へ投入するために交流危機を撤去し、183系800番台となっている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JR九州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南福岡電車区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹿児島とともに、1975年の山陽新幹線博多開業時から配置されていた。JR発足後、車体更新に合わせて赤一色にたくさんのロゴという衝撃的な塗装となる。更新時に貫通扉が撤去されたため、その後は貫通型200番台のイメージが無くなっている。2000年に「かもめ」「みどり」運用がなくなり、2001年3月に定期運用を終えた。一部の車両は鹿児島に転属している。 1975.3.10 「にちりん」にて運用開始(11両編成) 1976.7.1 「かもめ」「みどり」運転開始(8両+4両編成) 1990.3.6 赤かもめ塗装運転開始 1991.2 赤みどり塗装への変更開始 1992.3.25 「ハウステンボス」運転開始 1994.1 ハウステンボス色への変更開始 1994.3.1 「にちりん」運用車の多くが大分電車区に転属 1994.7.1 「有明」運用終了 2000.3.11 「かもめ」「みどり」運用終了、「にちりん」運用のみとなる 2001.3.3 南福岡所属車の定期運用終了 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990.2 「みどり」:佐世保駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991.3 赤みどり色:博多駅 | 1993.8 赤塗装ハウステンボス:鳥栖駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹿児島運転所/鹿児島総合車両所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南福岡とともに、1975年の山陽新幹線博多開業時から配置されていた。JR発足後は特急「にちりん」「有明」などを受け持ち、ボンネット型の先頭車が多かったが、車両の入換えにより200番台主体に変わっていった。2011年に定期運用を終了している。 1975.3.10 「有明」「にちりん」にて運用開始(11両編成) 1991. RED EXPRESS塗装への変更開始 1995.4.20 「きりしま」運転開始(きりしまEXRESS色) 2000.3.11 「ひゅうが」運用開始(K&H色) 2011.3.12 定期運用終了 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989.3 「にちりん」:宮崎駅 | 左から きりしま色、K&H色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大分電車区/大分運輸センター/大分車両センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JR発足時は配置が無かったが、1994年に特急「にちりん」運用車が転入。一度は定期運用が無くなるが、2006年に復活した。2011年に定期運用が無くなった後も、国鉄色の波動用編成がしばらく残り、JR九州最後の485系となっていた。大分に所属していたRED EXPRESS塗装車のカットボディが、九州鉄道記念館の入り口横で展示されている。 1994.3.1 「にちりん」運用車の多くが南福岡から転入 2000.3.11 定期運用なくなる 2006.3.18 「にちりん」「ひゅうが」「きりしま」運用車が鹿児島から転入し定期運用復活 2011.312 定期運用終了 2015.10.18 最後の営業運転 2016.10.2 全廃 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010.5 復活国鉄色:延岡駅 | 2016.8 クハ481-246:九州鉄道記念館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両配置表(JTを除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||