| 北アルプスは、一般的には飛騨山脈と呼ばれ、東に姫川・木曽川、西に神通川・飛騨川が流れる。約270万年前に始まる火山活動で山脈の基盤ができ、約130万年前からは赤石山脈と同様に断層活動で急激に隆起している。 北アルプスの最北部は、黒部川を挟んで立山連峰と後立山連峰に分かれている。写真の手前が後立山連峰、奥が立山連峰。後立山連峰の中央から右にかけて白馬三山。左側で手前に伸びる白い尾根が八方尾根で、そこにあるのが唐松岳。そこから左に五竜岳、鹿島槍ヶ岳がある。立山連峰の立山、剣岳もよく見えている。 |
|
 |
|
| 2016.11 飛行機より | |
| 白馬三山 | |
| 白馬岳と、杓子岳、白馬鑓ヶ岳を合わせて白馬三山と呼ばれる。一列に山が連なる後立山連峰でも、白馬は形よく3つ並んでいるので目印になる。 |
|
| 白馬岳(2932、百名山) | |
| 白馬岳は、後立山連峰の最高峰。地名は「はくば」だが、山名は「しろうま」である。高山植物の多さは全国でも有数で、大雪渓があることでも知られている。 |
|
 |
 |
| 2005.5 神城付近より 左から白馬鑓ヶ岳、杓子岳、白馬岳 |
2002.10 栂池より |
 |
 |
| 2002.10 栂池神の田圃より 正面の三角の山が白馬岳で、その右が小蓮華 |
2004.10 妙高山より 中央が白馬三山、右に雪倉岳、左端には剣岳の頭が見える |
| 中央左の鋭角の山が白馬岳、その右の白い山が白馬鑓ヶ岳。杓子岳はその中間だがここからはほとんど見えない。白馬鑓から右に行くと、右端で不帰のキレットが大きく切れ込んでいる。白馬の左は旭岳で、いちばん左端には雪倉岳が見える。白馬は同じ年の8月に登ったばかりだったが、まわりの山は霧の中だったので、この時に始めて周囲の様子がわかった。 |
|
 |
|
| 1995.10 立山より | |
| 白馬は私にとって初めての本格的な登山で、山小屋に泊まるのも高山のお花畑を見るのも初めてだったのでわからないことだらけの旅だった。猿倉からのコースは大雪渓を登っていくはずだったが、雪不足で溶け出していたためほとんど雪の上を歩けず、迂回路がつくられていた。大雪渓上部のお花畑は話には聞いていても、やはり実際に見ると素晴らしさがよくわかる。しかし山頂が近づくと霧に包まれてしまい、翌朝も晴れなかったので白馬山頂からの景色はまったく見られなかった。下りはルートを変えて栂池の方に向かったが、小蓮華を越えたあたりでようやくわまりが見えるようになった。 <猿倉7:00-8:10白馬尻-11:30お花畑-13:30-白馬山荘> <白馬山荘6:15-6:30山頂-8:30小蓮華山-10:00白馬大池-12:30栂池> 標高差1690m |
|
 |
 |
| 1995.8 白馬岳山頂小屋より | 1995.8 大雪渓 |
 |
|
| 1995.8 白馬山荘付近より 左が杓子岳で、右の雲に隠れているのが白馬鑓 | |
| 白馬鑓ヶ岳(2903) | 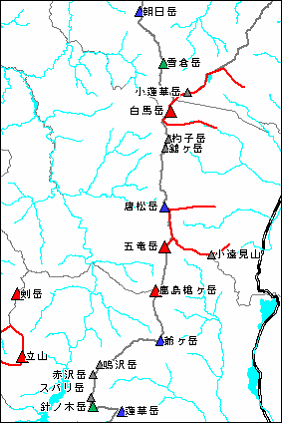 |
| 中央が白馬鑓で、右に大雪渓が見える。右に続く山が白馬岳。この日はよく晴れていたが、大雪渓の展望台に着いた前後だけ雲が出てしまった。 |
|
 |
|
| 2002.10 栂池より | |
| 雪倉岳周辺 | |
| 雪倉岳(2611、二百名山) | |
| 北アルプスのいちばん北にある二百名山。麓にある蓮華温泉は、徒歩でしか行くことができない温泉である。 |
|
 |
|
| 1995.8 白馬大池付近より | |
| 小蓮華岳(2769) | |
| 小蓮華岳は、白馬岳から白馬大池に向かう稜線上にある。馬の背にはコマクサが多く咲いていた。 | |
 |
|
| 1995.8 馬の背より | |
| 唐松岳 | |
| 唐松岳(2696、二百名山) | |
| 中央右が唐松岳で、左端は五竜岳。唐松から東に八方尾根が伸びている。唐松は五竜の帰りに通ったが、ずっと雲の中で山の様子はまったくわからなかった。唐松の北側には、不帰キレットと呼ばれる、北アルプスでも1・2を争う難所である。離れた所から見るだけでも恐ろしげな様子がわかる。唐松山頂からはほとんど見えなかったが、下り始めてようやく晴れてきた。 |
|
 |
 |
| 2003.9 遠見尾根より 唐松岳 | 2003.9 八方尾根上部より 不帰キレット |
| 五竜岳 | |
| 五竜岳(2814、百名山) | |
| 唐松岳から、さらに後立山連峰を南下したところにある。東には遠見尾根が伸びている。2005年は、花を見に白馬自然園に行ったが、北アルプスがくっきり見えていたので花そっちのけで山の写真を撮った。鹿島槍も見えないかとポイントを探したが、さすがに駄目だった。 |
|
 |
|
| 2005.5 神城付近より | |
| 2003年は、槍ヶ岳以来久々の北アルプスである。遠見尾根のテレキャビンを利用すれば比較的楽かとも思ったが、やはり尾根を5時間かけて登りつめていくのはかなり疲れた。山もはじめは見えていたが、やがて霧に包まれてしまい、山荘では何も見えなかった。翌朝、夜明け直後に一瞬だけ霧が晴れ、五竜の山頂方面が見えたが、数秒後には霧に逆戻りである。下りは稜線沿いに唐松へ向かったが、思ったよりアップダウンが多く時間もかかるハードコースだった。八方尾根を下り始めるとようやく景色も見えてきたが、白馬に続いてまた後立山の稜線からの景色が見られなかったのは残念である。 <テレキャビン終点9:45-11:25小遠見山-13:15西遠見-14:50五竜山荘> <五竜山荘5:15-6:15山頂6:30-五竜山荘8:00-10:25唐松山荘-11:05唐松岳11:25-14:30八方池-16:05リフト終点> 標高差1300m |
|
 |
 |
| 2003.9 遠見尾根より | 2003.9 西遠見より 中央に五竜山荘 |
 |
|
| 2003.9 五竜山荘上より | |
| 雲が多いので少し自信が無いが、中央手前が五竜、その左上が鹿島槍だと思う。奥は薬師と剣だろうか。 | |
 |
|
| 2007.11 飛行機より | |
| 鹿島槍ヶ岳 | |
| 鹿島槍ヶ岳(2889、百名山) | |
| 後立山連峰のほぼ中央にあり、標高は白馬山に次ぐ高さ。北峰と南峰があり、南峰の方が少し高い。登山ルートは赤岩尾根が一般的で、8時間程度の行程となる。五竜岳からの縦走は、八帰キレットなどの難所を越えるため6時間程度を要する。 五竜岳に登った際、間近に見えることを期待したが、山頂では何も見えなかった。遠見尾根を登る際に一瞬だけ雲が晴れたのが、唯一の写真である。 |
|
 |
 |
| 2003.9 遠見尾根より | 2009.10 黒部湖ロープウェイより 左:五竜岳、右:鹿島槍ヶ岳 |
| 左から唐松岳、五竜岳、鹿島槍ヶ岳。鹿島槍ヶ岳は、やはり堂々として存在感は一番である。背後の山は、唐松の上が焼山と火打、五竜の上に妙高、そしてその右に高妻、黒姫が見えている。 |
|
 |
|
| 1995.10 立山より | |
| 中央の2つの山が鹿島槍と五竜岳。その右に立山と剣岳が見えている。 |
|
 |
|
| 2004.10 妙高山より | |
| 中央手前の三角の山の背後が五竜で、その左が鹿島槍。五竜の右には八方尾根が見えている。 | |
 |
|
| 1996.5 戸隠高原より | |
| 爺ヶ岳(2670) | |
| 鹿島槍ヶ岳の南、扇沢の北にある山。扇沢から鹿島槍ヶ岳へ登る際には、爺ヶ岳を通ることになる。写真の左に爺ヶ岳、中央付近に鳴沢岳と赤沢岳、右端は蓮華岳。奥は志賀高原と四阿山、浅間山が見える。 | |
 |
|
| 1995.10 立山より | |
| 黒部湖周辺の山 | |
| 鳴沢岳(2641)、赤沢岳(2678) |
|
| 爺ヶ岳から南西へ続く尾根に並ぶ山。この2つの山の間を、扇沢と黒部湖を結ぶトンネルバスが通っている。黒部湖ロープウェイから真正面に見える山である。 |
|
 |
|
| 2018.7 黒部平より 正面が赤沢岳、左が鳴沢岳 | |
| 針ノ木岳(2821、二百名山)、スバリ岳(2752) |
|
| 左は赤沢岳、右針ノ木岳。後立山連峰の中では特別有名な山ではないが、ロープウェイの上から見ると、黒部湖の背後に堂々とそびえている。 | |
 |
 |
| 1991.8 黒部湖ロープウェイより 左から赤沢岳、スバリ岳、針ノ木岳 |
2009.10 黒部湖ロープウェイより 左:スバリ岳、右:針ノ木岳 |
 |
|
| 2006.10 横手山より 右側の山が左から蓮華、針ノ木、スバリ岳。左の山は薬師 |
|