| 大雪山という名のピークは無く、大雪山系と呼ぶ場合は、狭義には旭岳周辺からトムラウシまでの表大雪、広義にはニセウカウシュッペ山などの北大雪、石狩岳・ニペソツ山などの東大雪を含んだ北海道中央部の山々全体を指す。十勝連峰を含めることもある。このうち大雪山という山名は、表大雪のうち緑岳以北を指すことが多いようである。表大雪は火山活動によるもので、千島列島と同じ千島火山帯に分類される。東大雪の石狩岳、北大雪の武利岳などは火山ではなく褶曲山脈だが、そこにニペソツ山、ニセイカウシュッペ山などの古い時代の火山が混在している。 |
|
| 表大雪 | |
| 旭岳(2290、百名山) | |
| 旭岳は北海道の最高峰で、表大雪のいちばん西にある成層火山。記録に残る活動は無いが、活火山である。ロープウェイで姿見に登ると、手の届くほど近くに見える。実際に登ってみると、あっけなく山頂に着いた。ほとんどがガレ場の急登で、植物を見るという楽しさは無いが景色はよかった。 <姿見の池10:00-11:15山頂12:00-12:50姿見> 標高差690m |
|
 |
 |
| 1997.8 姿見より | 1997.8 金庫岩と山頂 |
| 旭岳山頂からは、大雪山中心部の山々が一望できた。車道はもちろん人工のものが何もないのがいい。黒岳の向こうが層雲峡で、頑張れば一日で縦走できるのでいつか行ってみたいところである。 | |
 |
 |
| 1997.8 旭岳山頂より 左に安足間岳・比布岳、右奥に鋸岳・北鎮岳、右手前は中岳 |
1997.8 旭岳山頂より 手前がお鉢のある間宮岳、左奥に北鎮岳・凌雲岳、中央奥に黒岳、右奥に北海岳・烏帽子岳 |
 |
|
| 1997.8 旭岳山頂より 中央左に白雲岳、その左になだらかに続くのが小泉岳と赤岳。中央奥は緑岳、手前は後旭岳 |
|
| 2006年は、憧れだった大雪の紅葉を見ようと、時期を見計らって出かけた。その甲斐あって、赤や黄色の絵の具を散りばめたような風景にめぐり合えたが、曇っていて色があまり鮮やかでないのが残念である。また強風でロープウェイが時々止まっていたので、下りられなくなるのではという不安でゆっくりする気分ではなかった。 | |
 |
 |
| 2006.9 姿見 | 2006.9 姿見 |
| 北鎮岳(2244) | |
| 2003年は、お花畑を求めて裾合平へ。裾合平は姿見から旭岳をまわ込むように1時間半ほど北側に行ったところ。山は雲ではっきり見えないものが多かったが、チングルマの大群落がすばらしかった。 | |
 |
 |
| 2003.7 裾合平より 北鎮岳 | 2003.7 裾合平より 間宮岳 |
| 愛別岳(2185) | |
| 左端の山が愛別岳で、大雪山系のいちばん北になる。その右は比布岳、北鎮岳などの山。その右の雲の中に旭岳があるはずである。 |
|
 |
|
| 1999.10 旭川付近より | |
| 北海岳(2149) | |
| 北海岳は旭岳からは角度が悪く見にくかったが、赤岳ではこの山がいちばん形良く見えていた。 |
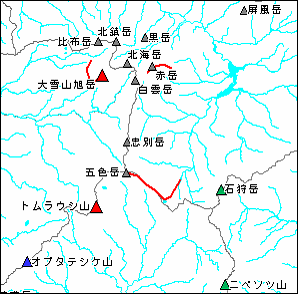 |
 |
|
| 2003.7 赤岳より | |
| 黒岳(1984) | |
| 左が黒岳で、右は桂月岳。層雲峡は何度も訪れているが、ロープウェイに乗って黒岳を見たのはこの時だけで、まだ山頂には立っていない。黒岳から旭岳は、5時間ほどで縦走することができる。 |
|
 |
 |
| 1989.7 黒岳ロープウェイ上より 黒岳 | 1989.7 黒岳ロープウェイ上より 右は屏風岳、その背後に武利岳 |
| 白雲岳(2229)、赤岳(2078) | |
| 黒岳の南にあり、大雪山の中で最も高山植物が多いエリア。赤岳は銀泉台から3時間の登りで、急な所もあるが、駒草平やいくつものお花畑があって、花を楽しんでいるうちに登ってしまう。ただ、すぐ横にもっと高い山がいくつもあるので山頂という気はしなかった。さらに小泉岳まで足を伸ばしたが、このあたりはレブンサイコをはじめ他で見たことが無いような珍しい花が多く、花を楽しめるルートであった。 <銀泉台6:55-駒草平-10:00赤岳-11:30小泉岳12:10-15:50銀泉台> 標高差670m |
|
 |
|
| 2003.7 駒草平 左は烏帽子岳 | |
 |
 |
| 2003.7 赤岳山頂より 左は白雲岳 | 2003.7 小泉岳付近より 奥は旭岳、左は白雲岳 |
| 忠別岳(1963) | |
| 大雪山の中心からは南に離れており、小泉岳から縦走すると3時間半ほど。尾根をさらに1時間半ほど南下すると五色岳がある。 |
|
 |
|
| 2003.7 五色岳より 右手前が忠別岳、奥は白雲岳 | |
| 五色岳(1868) | |
| 五色岳は、表大雪の中でも1・2を争うお花畑の山。登山口から山頂まで5時間程度と長いが、急な登りは沼の原までで、あとはゆるやかな登りである。エゾツガザクラ、アオノツガザクラ、エゾコザクラ、キバナシャクナゲ、チシマノキンバイソウなど五色に変わるお花畑で、眺めていると時間を忘れてしまう。1度目は天気が悪かったので途中で引き返したが、2度目で山頂に立つと、トムラウシだけでなく北にある忠別岳や大雪山主峰が姿を現した。 <98年:登山口8:00-9:10沼ノ原-11:30五色ヶ原11:45-15:40登山口> <03年:登山口7:10-8:15沼ノ原-五色ヶ原-12;45五色岳13:05-沼ノ原17:20-19:00登山口> 標高差790m |
|
 |
 |
| 2003.7 沼ノ原より 五色岳(中央やや左) | 2003.7 五色ヶ原より トムラウシ山 |
 |
|
| 2003.7 五色ヶ原より 中央は北見富士(1291)で、左は武利岳(1876)と武華岳(1759)。 | |
| トムラウシ山(2140、百名山) | |
| トムラウシ山は、表大雪の最奥にある山。登るには最短ルートでも5時間以上を要する。五色岳や美瑛岳からの縦走ルートもある。まだ登ってはいないが、沼ノ原から五色岳までのルート上は、ほとんどどこからでもトムラウシが眺められた。 |
|
 |
|
| 2003.7 沼ノ原より トムラウシ山 | |
 |
|
| 2015.9 十勝岳より | |
| 北大雪 | |
| ニセイカウシュッペ山(1878) | |
| 奥がニセイカウシュッペで、手前は朝陽山。ニセイカウシュッペ山は、層雲峡の浸食によって表大雪と切り離されたが、元々は表大雪の一部だったと考えられている。 。 |
|
 |
|
| 1989.7 黒岳ロープウェイ上より 手前は層雲峡 | |
| 東大雪 | |
| 石狩岳(1967、二百名山) | |
| 東大雪の主峰。このあたりは石狩中央山地と呼ばれ、日本海側、太平洋側、オホーツク海側の3つの分水嶺である。沼ノ原、五色ヶ原ではどちらを見ても山に囲まれていたが、中でもトムラウシ・ニペソツと並んで石狩岳は絵になる山だった。 。 |
|
 |
 |
| 2003.7 沼ノ原より 右が石狩岳、左は音更岳(1932) |
2015.9 十勝岳より |
| ニペソツ山(2013、二百名山) | |
| 糠平湖の近くにある山で、東大雪では数少ない火山。日本で最も西にある2000m級の山でもある。あまり聞いたことの無い名前だったが、縁があるのか五色ヶ原、糠平湖と東西から素晴らしい姿を見ることができた。なお、深田さんが日本百名山を選んだ時点では、ニペソツ山を見たことがなかったので選ばれたなかったと言われている。 |
|
 |
|
| 2008.2 糠平湖より 手前はタウシュベツ橋 | |
 |
|
| 2003.7 五色ヶ原より 中央がニペソツ山、右奥は糠平湖周辺の山々 |
|
| ウペペサンケ山(1835) | |
| 糠平湖のすぐ西にある山で、こちらも古い時代の火山。手前の山が少し邪魔になっている。 |
|
 |
 |
| 2008.2 糠平湖より | 2015.9 十勝岳より 左ニペソツ山、右ウペペサンケ山 |
| 西クマネシリ岳(1636) | |
| 右が西クマネシリで、ニペソツのさらに東、石狩山地の東端にあたる。廃止間近の置戸の駅からくっきり見えていた。 |
|
 |
|
| 2006.2 置戸駅より | |