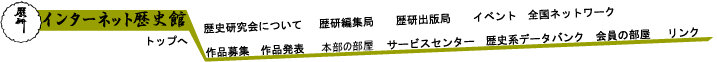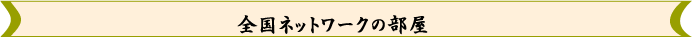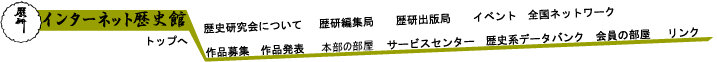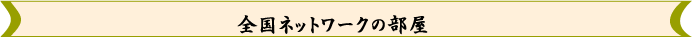全国ネットワーク歴研だより
(地域歴研・テーマ歴研、連携団体レポート)
全国ネットワーク歴研だより
(地域歴研・テーマ歴研、連携団体レポート)
◎関東・甲信越
★日立歴史研究会
*8月29日(日)全国歴史研究会主催の「歴史を楽しむ会in水戸」が水戸市の祇園寺で開かれ、当会から9名が参加した。地元の会員や東京方面からバスで来た方々と合流、同寺客室で行われた講演2件を聴講した。終わった後当会員は、同寺の墓地にある水戸藩諸生党の恩光無辺碑と市川三左衛門墓に線香をあげて帰った。
*9月12日(日)油縄子交流センターにて月例会を開催した。出席者35名。長年、県の教育や遺跡保存に従事された高根信和先生の「南郷街道を行く」の講話。近世水戸藩北領を巡る街道の話の他、古代遺跡について発掘、調査、保護に関する事を聞くことができた。
〈レポート 小浜一男〉
【連絡先】〒319・1415茨城県日立市相田町3の4の11
小浜一男(会長)方
★常総歴史研究会
*9月19日(日)柏市教育福祉会館で定例会開催。歴史研究会第26回全国大会紀州田辺大会の案内を兼ねて「紀州木の国の歴史を歩く」のテーマで土田和美顧問(東京都)が発表しました。出席者は26名。紀伊和歌山の歴史的概観から話を始められ、世界遺産である高野山と熊野の歴史的背景、また熊野三山の関係に触れられた後に、紀伊国を「紀北」・「紀中」・「紀南」の三つのエリアについて、配布された和歌山県観光ガイド&マップで旧跡を説明され、熊野への参詣道「紀伊路」「小辺路」「中辺路」「大辺路」「伊勢路」の地図上での道筋や点在する「王子」の役割などを話された。次に紀伊国といえば万葉集とは切っても切れない繋がりについて説明され、配布された紀伊万葉ガイドブックから紀ノ川から始まり那智勝浦・新宮までの名所旧跡での情感やその地で代表する和歌を詠まれ、旅心を掻き立てられる話で結ばれました。配布された資料は和歌山に関するガイドカタログなど、全国大会の基礎資料になります。
*10月10日(日)柏市教育福祉会館で15時30分から特別講演を開催。講師=専修大学名誉教授青木美智男先生。演題=「藤沢周平の文学と江戸の浮世絵師」
〈レポート 三好賢司〉
【連絡先】〒277・0066
千葉県柏市中新宿1の23の10
立川誠一(世話人代表)方
★東京龍馬会
*東京龍馬会は優しく進取の気鋭を持った幕末の志士坂本龍馬が好きな人、幕末に興味のある人、が集まって『龍馬を縁に出会いを楽しむ』をモットーに1986年(昭和六十一年)十一月十五日に発足し、以来全国各地に約四百名の会員、賛助会員を有する会です。
*主な活動として、歴史研究家や作家といった方々により寄稿された原稿の連載、会員の投稿、幕末維新に関する最新情報、会のイベントレポート、幕末関連の新刊情報などを掲載した会報誌「龍馬タイムズ」を年四回発行、有名作家や、幕末ゆかりの人物の御子孫、といった方々による講演会を年二回実施。主に東京都内を中心とした幕末、明治の史跡を巡る史跡探訪を年二回実施、その他、新年会、お花見会等のイベントも行っております。
*毎回イベント後には懇親会を行っており、龍馬を中心に幕末の話で盛り上がっております。会員さんは二十代から八十代まで年齢層も幅広く、女性会員も多数在籍している為、明るく楽しい会です。今年は大河ドラマ「龍馬伝」の影響もあり、会員の数も増え益々活発に活動しております。
*東京龍馬会では只今会員を募集致しております。興味のある方はお気軽にお問い合わせください。
*入会はホームページで受付けております。
入会金=(個人会員)二千円
年会費=(個人会員)四千円
(団体、賛助会員)一万円
【連絡先】〒167・0051
東京都杉並区荻窪4の8の9
アドレス http//:tk‐ryoma.net
★中国の歴史と文化を学ぶ会
*9月5日(日)猛暑がつづく午後、中文会は大田区民センターにおいて第85回例会を開催した。当日は栗原専務理事が司会をつとめ、三堀会長が挨拶をしたあと会員3名が発表をおこなった。例会には60名が出席し盛会であった。▽最初の発表は羽生潤吉氏で演題は「─漢民族と周辺異民族との攻防史─〈東夷・西戎・南蛮・北狄〉」であった。羽生氏は「古来、漢民族には中華思想があり、自分たちは世界の中央で華と開いた最も文化の進んだ国だという自負があり、東西南北の周辺に住む異民族たちを程度の低い未開な蛮族と見下していた」と指摘し、古代の漢民族と周辺異民族との間に展開された攻防の歴史を年表や地図を使ってわかり易く論じ、出席者の中国古代史への興味をかきたてた。▽次の発表は安藤芳夫氏で演題は「京劇─その歴史と特徴」であった。安藤氏は「わが国の歌舞伎とならぶ中国の伝統芸能の京劇は、中国人社会の文化を知るステップの一つである」として、時折プロジェクターを使いながら、京劇の歴史、四世代にわたる名優の紹介、演技の基本、行当(役柄)、唱=うた、做=しぐさ、念=うた、打=立ち回り、瞼譜(隈取)などを具体的に解説し、京劇に親しむ上で興味深い発表となった。▽最後の発表は土屋和彦氏で、演題は「マリア・ルス号とその背景」であった。横浜在住の土屋氏はこれは日中友好の歴史上有数の話です、と紹介した。「明治五年中国(清国)のマカオから南米に向かうペルー国籍のマリア・ルス号が太平洋上で嵐に遭い、マストが折れて修理のため横浜港に立ち寄った。船内には235人の奴隷状態にあった中国人が乗っていた。神奈川県令大江卓の奮闘によって裁判に勝利し中国人全員を釈放したという」正に日中友好の歴史物語であった。▽例会後は会場を移して懇親会を開催した。当夜は36人の会員が出席し、暑さを吹き飛ばす賑やかな酒宴となった。
○中文会は、有益で楽しい会です。年会費4000円、例会参加費1000円、例会では会員発表や専門家の講演があります。年一回の会報や年三回のニュースの発行もあります。みなさまのご参加をお待ちしています。
〈レポート 比留間長一〉
【連絡先】〒359・1111
埼玉県所沢市緑町3の2の2
佐山正典(事務局長)方
★横浜歴史研究会
*9月4日(土)当日の発表者は左記の三名。猛暑とあって出席者は58名▽発表者会員西山達夫氏。題は「『Japan as No・1』から『失われた20年』へ」。米国の社会学者・エズラ・ヴォーゲルの標題のフレーズで代表される、70~80年代当初の日本経済の繁栄は、80年代後半の円高不況を経た後、いわゆる「バブル景気」に突入する。90年に入りバブルは崩壊、その後上下動はあったが、結局今日まで「失われた20年」を取り返せずデフレ不況に喘ぐ日本。その原因の解明に、『失敗の本質―日本軍の組織論的研究―』(1984年出版)を引用して解説。さらにこの状況からの脱却策としての、今年六月、経済産業省発表の『産業構造ビジョン2010』に期待したい、としてその主要部分を各種計表などの資料を示されて詳細に説明された。▽発表者会員森岡璋氏。題は「慶長日件録に観る殿上人の一年」。前回に続く「慶長日件録」で、この日記は禁中内外の出来事を公私にわたって詳細に記した実録。今回はその内の「慶長八年」の一年間に焦点を当てた。著者の船橋秀賢は、慶長年間、明経博士・侍読として後陽成、後水尾両天皇の側近だった。この慶長八年は家康、征夷大将軍就任の年。日記には各所に「内府」「大樹」等、家康を示す記事が見られ、秀賢、家康間の親密な交流が窺われ興味深い。この事実は何を意味するのか。森岡氏はこう推論される。「家康は、徳川幕府の安定成長に必要な文化面の指導者の一人として秀賢を重用。特に秀賢が書物とその出版に通じていた点を重視したのでは」と。漢文の原文資料を読み解いて判り易く解説された。▽発表者渡会裕一氏。題は「北関東に覇をとなえた小山氏」。平将門の乱を平定した藤原秀郷を祖とする北関東の名門小山氏。源頼朝挙兵に参陣、戦功をあげ有力御家人となる。北条執権時代は終始、北条に組し生き残る。南北朝時代は紆余曲折の末、足利尊氏に密着し、相伝の下野守護職を維持、後に宇都宮氏と鎌倉府足利氏との戦いに敗れ小山氏は一旦断絶する。しかし幕府は小山の名跡を惜しみ復活させ、十五世紀中期には再び下野守となる。戦国期、関東は後北条、上杉両氏の激突の地となり、小山氏など関東の諸将は集合離散を繰り返す。1575年、北条氏の猛攻に拠点祇園城が落城、ここに400年来の関東の名門小山氏は滅亡する。渡会氏の関東武士研究には定評があり、今回も系図、地図ほかの資料により、詳しく検証された。
〈レポート 丹下重明〉
【連絡先】〒223・0056神奈川県横浜市港北区新吉田町3255 八城東郷(会長)方
★神奈川歴史研究会
*9月19日(日)藤沢市労働会館において、記念すべき第250回例会を開催した。思えば当地湘南の地において昭和58年に、歴史好きの仲間が集まり呱々の声をあげてから、今年で28年目になる。結成当時はささやかな集まりであったが、その後、徐々に発展をみて現在では在籍会員数五十数名の大きな会に発展した。メンバーも多士済々に富み、毎回変化のあるいろいろなテーマでの発表があり、新鮮な驚きを感じている。今年の夏は、異常気象でとにかく暑かった。この日も残暑の余韻が残り、会場に来るまで大きなエネルギーを必要とした。だが、来てみると、参加人員は29名で、いつものように友と会いほっとした安堵感をおぼえた。今回の発表は瀬戸敦氏及び池田勝宣氏の2名でその演題と内容は以下のとおりである。▽最初の発表者は瀬戸氏で、テーマは「佐賀藩とアームストロング砲」と題してお話をされた。戊辰戦争の際、佐賀藩は慶応四年の上野戦争でアームストロング砲の砲撃で寛永寺に立て籠もった彰義隊を壊滅させ、会津城攻防戦でも、この大砲を使用して会津藩を降伏に追い込んだ。そしてこの大砲の製造は佐賀藩が自製したものだと流布されている。佐賀藩のアームストロング砲は戊辰戦争の終息を早めたと言ってよい。この大砲を開発したのはイギリスのアームストロング社によるもので、鍛造製である。とにかく、強度があり、距離もよく飛び、効果が大きい。しかしながら、氏は言う。確かに佐賀藩にはこの大砲は製造できる技術はあるいは能力は存在したが、その技術も低く、藩軍事技術の元締めである本島藤大夫の「松の落葉」に製造の記述がない。ということはあるいはイギリスからの輸入品によるものであったかもしれないと。いつもの様に、氏の佐賀にたいする郷土愛を強く感じた。▽次の発表者は池田氏で、テーマは「婆羅門僧正菩提仙那」と題する講演をされた。毎年、思うのだが、池田氏の内容は、スケールが壮大である。これまでも、自分で歩かれたシルクロードの話題とか、義経伝説を追って北海道に出かけたり 、意表をつくことが多い。今回も、六世紀半ばに仏教が伝来してからの以降の、大和・奈良・平安時代における我が国の仏教事情について16ページにわたるカラー版のレジメを駆使して説明された。すなわち、センナは日本に渡来したインドの仏教僧で、身分の高いバラモン階級の出であり、婆羅門僧正のことである。彼は、衆生救済活動を行ない、多くの徳化を慕い追従するもの千人を数えたという行基とも会見をした。そして国家的大プロジェクトである東大寺の大仏開眼の法会では導師を務めた。その際、用いた筆には紐が結ばれていて、それにすがった聖武太上天皇、光明皇太后、孝謙天皇が感涙をしたという。我々は、古代の仏教に詳しくなった。
*この日に、新しく当会に横尾氏が、また、横浜歴史研究会より斉藤宗久氏がご出席された。さらに、小島房治顧問も、文筆活動の忙しい合間をみて参加された。
〈レポート 浅見 実〉
【連絡先】〒248・0002神奈川県鎌倉市二階堂267の170 井上誠一(会長)方
◎東海・北陸
★静岡県歴史研究会
*9月5日(日)静岡市文化財資料館会議室において、第89回定例研究会が開催された。▽最初の発表は松本検氏の「明治天皇と鉄舟」。山岡鉄舟研究の第一人者である氏から、改めて鉄舟の豪胆な人物像を窺い得た。江戸城無血開城の真の立役者、また剣豪で、達筆な書家としても知られるが、それ以外での凄い話。慶応四年(1868)四月十一日、徳川慶喜が寛永寺を出て水戸へ向かい、江戸城は東征軍に撤収された。同月十五日、鉄舟は四階級特進して、「大目付に任ず」の辞令を受けた・同年八月には、駿府藩若年寄格幹事役に任じられる。翌年の明治二年(1867)九月、静岡藩権大参事に任ぜられ、無禄移住の旧家臣らの善処に奔走、殖産興業に意を注ぎ、荒地であった牧之原や三方が原の開拓と茶の栽培を奨励した。静岡での行政手腕を買われて、明治四年十一月、大久保利通の依頼で茨城県参事(知事)として赴任。僅か二十日間で同県内の内紛を解決した。同年十二月には、井上馨からの依頼で伊万里県(後の佐賀県)県令に赴任。前回同様統治の手腕を発揮して内紛を解決、翌年二月には東京に戻った。明治五年六月十五日、西郷隆盛らの強い要請により、鉄舟は明治天皇の侍従となった。青年天皇の教育係である。鉄舟は十年限りの約束で、これを受けた。この十年間の間には、明治天皇と鉄舟との間に多くの逸話が残っている。ある時、酒に強い天皇が酒の席で、鉄舟に相撲を挑んできた。鉄舟は拒否したが、いきなりぶつかって来たので、これをかわし、天皇を押さえ込み、「御行跡の御改め遊ばされねば、鉄太郎は今日限りで出仕仕りませぬ」と、胸中に内蔵していた思いを述べ、自宅に帰った。天皇に不敬を働いたことで、自ら謹慎した。翌日、天皇は「朕も今までの事は悪かった。相撲も酒もやめるによって、そちもこれまで通り出仕せよ」との伝を、岩倉具視が伝えた。鉄舟は感泣し、井上馨と参内した。天皇は大いに歓び、二等官に進め、生涯宮内省御用掛を仰せ付けられた。また、明治六年の皇居の火災や、明治十一年の竹橋騒動の際に、鉄舟は寝間着に袴姿で真っ先に駆けつけ、天皇をお守りしている。山岡鉄舟を評して、西郷隆盛は「命も名も要らぬ、無我無私の御仁」、勝海舟は「維新の大業をならしむるに、これ以上の人物はいなかった」という。▽二番目の発表は鈴木康弘氏の「連歌師宗祇・宗長の東国の旅」宗祇は文亀二年(1502)七月三十日、箱根湯本で八十二歳の生涯を終えた。宗祇の弟子・宗長の記した『宗祇終焉記』は宗祇最後の旅に同行し、臨終の場に立ち会い、接した宗祇のありのままが記されている。宗祇は応仁の乱勃発直前の文正元年(1466)に離京し東国へ旅立った。京都は既に将軍の権威が落ち騒々しくなっていたが、関東も足利成氏(古河公方)と管領上杉氏との対立で「享徳の乱」が続いていた。氏は関東の状況をよく理解できるように、「享徳の乱」の構図を詳しく解説された。戦に明け暮れる武士たちではあったが、連歌師は丁重に迎えられたようだ。文正元年九月、五十子の陣所(埼玉県本庄市)を訪れ、管領上杉の家宰である長尾景信らと連歌を詠んでいる。この時に、宗祇最初の連歌論書である『長六文』が纏められた。また宗祇は翌年の三月には、長尾景信の子息・景春(「長尾景春の乱」で有名)に連歌論書『吾妻問答』を贈っている。宗祇は戦に明け暮れながらも連歌に心を寄せる武将達に深い情を抱いていたことが理解できる。宗祇の師匠である心敬(京都の寺の権大僧都)は武蔵国品川で廻船問屋を営む鈴木道印と懇意で、毎年のように品川を訪れ、連歌を詠み合っていた。宗祇も鈴木道印と親しくなっていたので、東国下向に際しては、船便など大層世話になっている。連歌師を迎える民は武士がそうであったように、大感激し喜んだのであろう。宗祇は越後を七度訪れている。七回目は最晩年の八十歳の時である。この後、美濃を目指して帰る途中の箱根湯本で没した。宗祇は大変越後がお気に入りであったのであろう。上杉氏、また長尾氏との関係も極めて良かったと思われる。残念ながら時間の関係で、氏の発表は宗長の話までは届かなかった。次の機会に続きを是非お願いしたいと感じた。▽三番目は寺尾弘之氏の「宇喜多秀家と八丈島」。宇喜多秀家が八丈島へ流罪となったことは、よく知られるところであるが、氏は長年の研究と実際に八丈島を訪れて史料の調査や役所での聞き取りを踏まえて、大変面白い発表であった。先ず、宇喜多家の経歴からスタート。秀家の代に豊臣政権の五大老の一人となる。秀吉没後の関ヶ原の戦で、秀家は西軍についたために敗走、追われる身となった。『備前軍記』によれば、家臣・進藤三左衛門など五名に守られて伊吹山に潜伏していた。その後、美濃・大坂を経て薩摩島津氏を頼った。暫く島津氏に匿われるが、慶長八年(1603)、「秀家が島津氏に庇護されている」との噂が広がり、島津氏は止む無く、徳川家康に秀家を引き渡した。しかし、秀家は島津氏や前田氏(秀家の妻は前田の娘豪姫)からの懇請を得て死罪を免れ、駿河久能山に幽閉された。慶長十一年(1606)遂に八丈島へ流罪となった。従臣十三名を連れての島送りであったが、帯刀は許されていた。約五十年後の明暦元年(1655)十一月、享年八十四歳で没した。当初は墓石は無かったが、元禄年間に秀家から四代の秀親が供養塔を立て、天保年間には九代の秀邑が現在の墓(五輪塔)を建てている。八丈島での流人生活がどのようなものであったか、氏は詳しく研究されていた。秀家から始まった八丈島への流人は幕末までに、大名から小者、女を含めて約千八百名に達した。島では耕作地が少なく、慢性的に食料不足、魚を取るにも幕府から小舟を作ること(江戸中期まで)を禁じられており獲れず、人が潜って貝類や海藻を得る程度であった。野牛は六百五十頭程いたが食しなかった。馬はいなかった。餓死者が頻繁に多数出た。流人は島民と一緒になって田畑の開墾、さつま芋(天保期から)、絹織物(黄八丈)の生産などを行った。島には秀家の次男の子孫・近藤富蔵が幕末に書き残した『八丈実記』があり、全六十九冊中、四十冊を東京都が買い上げているという。
〈レポート 松葉屋幸則〉
【連絡先】〒422・8045
静岡市駿河区西島363の55篠原旭(会長)方
◎関西
★大阪歴史懇談会
*9月11日(土)兵庫歴史研究会と合同見学会実施。スーパー猛暑の中JR伊丹駅改札に正午集合。約40名弱のタフな高齢者ばかりであった。企画案内者の兵庫歴研柴谷武爾氏の第一声は、熱中症で倒れられたら大変なので、気分がすぐれなくなったら団体行動より抜けて下さいと─。まず駅横の有岡城跡に行く。伊丹市文化財ボランティアの会の池田利男氏他三名が説明下さる。室町時代に伊丹氏が伊丹城に拠っていたが、戦国時代には荒木村重が伊丹氏を追い出し、織田信長の輩下として最盛期には三十万石を領有したという。昭和五十四年、国史跡に指定され、史跡公園として野面積の石垣が一部再構築された。天正六年(1578)村重は信長に叛旗を翻し、城下町全てを城郭の中に取り込んだ惣構えの城郭に十ヶ月に及び籠城したが、天正七年九月、村重は支城である尼崎に落ち、十一月には有岡城は落城する。城内に残った村重の妻子・家臣は殺され、自身は豊臣秀吉の茶人として生きのび天正十四年(1586)堺で病死(五十二歳)している謎の多い人物である。本会には荒木村重研究会の会員でおられる石川道子先生に顧問になっていただき古文書講座を担当していただいている。本丸近くの荒村寺は村重を弔うため建立され「心英道薫禅定門」と記された大きな位牌がある。墨染寺には、石塔9層の供養塔がある。次に伊丹郷町の北の入口に当たる「北の口」から川西の多田神社への参詣道として栄えた多田街道と西国街道の交差点には、多田満仲の建立と伝えられる自然石の古碑「辻の碑」を見学。付近には酒米を搗くための水車が小ぶりながら再建されて情緒豊かである。次に八幡神宮跡を見学、和泉式部の供養塔(鎌倉期)を見学。宝塚市平井に住んでいた平井保昌が和泉式部の最後の夫であり、摂津守として赴任した時に一緒に来た事から、この辺に和泉式部の供養塔が建立されても不思議ではない。伊丹緑道では楠の大木やテイカカズラ・タラノキ等自然観察にはもってこいの道を歩く。次に猪名野神社に参拝す、古くは牛頭天王ノ宮と呼ばれていた。伊丹郷町の総氏神である。境内には惣構えの有岡城の「岸の砦」跡の土塁が残存している。八月二十八の「岸の砦」のV字型の堀の発掘一般向けの見学会には約二百名の歴史ファンが参加された。幅3.7㍍・深さ3㍍の敵を防ぐ空堀であった。次に旧岡田家住宅(造り酒屋)見学。江戸前期の店舗で伊丹の酒造りの歴史をビデオとボランティアガイドの方に説明を受ける。伊丹から江戸へ送られた「下り酒」は江戸の人々に大変珍重された。伊丹の北部鴻池村に山中鹿之介の甥新六幸元が遠縁を頼って住みつき、酒造りを始めた。最初は濁り酒を造っていたが、慶長五年(1600)清酒の醸造に成功し、新六の居宅跡には「恋の池稲荷祠碑」があり、清酒発祥の地と記されている。延宝二年(1674)に建てられた旧岡田家住宅と隣接する白雪長寿蔵ブルワリーミュージアムの酒造器具類の展示説明を聞きながら、巨万の富を築いた伊丹の酒造りの酒匠の当時を思う。灘の生一本の台頭で、現在では白雪、大手柄老松等数えるのみとなった。
〈レポート 安居隆行〉
【連絡先】599・8123
大阪府堺市東区北野田561の28 松坂定德(会長)方
★関西歴史散歩の会
*9月5日(日)JR摂津富田駅を1時に出発した70余名の参加者は梶谷忠大講師の案内で古い町並みの「酒蔵と寺の町」富田界隈を散策した駅から900㍍のところに14世紀末(明徳年間)に禅宗の臨済宗妙心寺派の寺として創建された普門寺がある。室町時代の管領(将軍補佐役)細川晴元が出家してこの寺に入ったり、十四代将軍足利義栄が滞在しており、永禄年間(16世紀後半)には、普門寺城といわれ今も境内に当時の土塁が残っている。明暦元年(1665)、明国(元、中国)の高僧隠元が氏の黄檗山万福寺開山まで六年間滞在している。この間、異国の仏法に触れんがため、また異国の文化を学ばんがため、近郊は素より日本各地から大名、武家、僧侶、大檀那たちが数多く訪れ、混雑を極めたので幕府は一日の訪問客を二百人までとすると定め、高槻藩を預かる永井家が監視していたという。隠元が齎した隠元豆は今も愛用されている。普門寺と隣合わせに本照寺がある。15世紀の初め、応永三十四年に本願寺(浄土真宗の本山)7世紀存如上人が創建し、後に「富田御坊」といわれた。巨大な御堂はまるで城郭のようで屋根の反りも独特の傾斜をもつ。これは敵の放つ火矢が屋根に刺さらず滑り落ちるように工夫された形である。境内には富寿栄の松と呼ばれる30㍍の枝をはる老松があったが、今は巨大な根株だけが横たわっている。本照寺から南へ進むと教行寺がある。寛正六年(1465)本願寺八世の蓮如上人が細川勝元(応仁の乱の東軍の主将)からこの地を与えられ創建した。蓮如上人は越後国吉崎御坊を出て、若狭より丹波を経てこの摂津富田に入って「富田道場」を開いたので、摂津地区における一向宗(浄土真宗)の一大拠点となった。普門寺に並ぶ三輪神社の絵馬所には明治天皇・皇后が行幸啓された際、高槻駅付近で婦女子が富田踊りをお見せして旅のお慰めをした様子の絵馬がある。高槻市の北にある阿武山から豊富な地下水が湧出するので、この水を使った酒造業が栄え、17世紀には二十四軒の造り酒屋が軒を並べ、海路で江戸へ出荷していたが、地の利がある灘や伊丹の銘酒に押されて次第に衰微し、寿酒造と清弦酒造の二つになった。江戸期の富田には京都と大坂を結ぶ水路(淀川)、陸路(西国街道)の両方からの至便の地であるだけに昔から人の往来も激しく多くの文人墨客が訪れている。松尾芭蕉の弟子である俳人、宝井其角もその一人で、「けさ たんと(沢山)のめや あやめの とんらさけ(富田酒)」下から読んでも同文となる回文ハイクを詠んでいる。あやめ(菖蒲)は富田の酒の銘柄。
〈レポート 中山隆夫〉
【連絡先】〒567・0071
大阪府茨木市郡山2の15の17
下村治男方
℡072・643・7691
FAX072・643・7405
◎会報紹介(事務局到着順/平成22年9月~平成22年10月)
★『杉並郷土史会史報』第223号(杉並郷土史会)
*内容=「高円寺の気象神社」長沢利明/「杉並郷土史会の赤米・九州で収穫」西トミ江/「瑞宝中授章 都文化功労賞を受章 大谷光男先生 近況」/「行事予告」/ほか
★『北摂の歴史』第145号(関西歴史散歩の会)
*内容=「摂津の那須与一の墓」山村裕/「歴史散歩ご案内」/ほか
★『城だより』第501号(日本古城友の会)
*内容=「「三木城と寄衆の付城(対城)を行く(10月・第564回例会のご案内)」/「11月・第565回例会のご案内」/「セミナー等のご案内」「新聞記事」/ほか
★『会報』第313号(大阪歴史懇談会)
*内容=巻頭言 骨董と歴史(その二)」中澤祐一/「8月例会報告(第288回)平成22年度本会定時総会」/「京都の大名墓について(四)」田村紘一/ほか
★『江南郷土史研究会会報』第380号(江南郷土史研究会)
*内容=「木下藤吉郎を天下人にした仕掛け人前野将右衛門・蜂須賀小六実録(二十八)」松原清史/「平成22年度秋期〈武功夜話研修会〉」/「会報通信」/ほか
★『民俗文化』第564号(滋賀民俗学会)
*内容=「建部伝内賢文の書の評価論5」中村武三/「熊から身を守るための智恵─希少生物との共存と天気予報─」馬場杉右衛門/「〈逃げ水〉雑記」吉岡郁夫/「杖のフォークロア3」北野晃/「米原市丹生渓谷の城4─新城発見 江竜奥の城2─」長谷川博美/ほか
★『くり』第164号(伊賀流忍術復興保存会)
*内容=「忍術継承者・川上先生にご質問」/「信州松本藩芥川流忍術8」/「日本一の夏まつり・真田出陣ねぷた」/「第169回忍びの集いの報告」/ほか
★『静岡歴研会報』第129号(静岡県歴史研究会)
*内容=「奈良県桜井市・橿原市方面を探索」篠原旭/「9月5日(日)第89回研究会 松本、鈴木、寺尾各氏発表」/ほか
★『東京産業考古学会(TIAS)ニューズレター』第84号
(東京産業考古学会)
*内容=「行事予定」/「報告 見学会〈予科練平和記念館・ツムラ漢方記念館〉」八木司郎/「第12回理事会の議事概要」/「中央線(神田─飯田橋間)の産業遺産をめぐるウォーキングツアー」/「茨城県阿見町の赤煉瓦建築物(4)〈ツェッペリン大格納庫〉」/ほか
★『成政ファン』第80号(佐々成政研究会)
*内容=「はじめに」事務局佐々克典/「〈銀杏の樹蔭に〉5章」/「私の〈佐々成政〉探求(四)~続・尾張名古屋を巡る~」佐々洋三/「〈さっさ〉という名前、私の体験例」佐々克典/ほか
★『歴研神奈川』第267号(神奈川歴史研究会)
*内容=「蒙古襲来と北条時宗」井上誠一/「海軍善玉論を斬る」山崎俊幸/「神奈川歴研8月例会レポート」竹村紘一/「続古代逍遙三ヶ月忘備録 釜山(2)金海」近藤正一/「漢字の歴史(七)」池田勝宣/ほか
★『神道フォーラム』第35号(神道国際学会)
*内容=「十五年を越えて新たな歴史へ歩み出す 神道国際学会」/「日々雑感」/「連載・神道DNA〈所在不明高齢者と敬老の日〉」三宅善信/「神道界あれこれ」/「悠久の社史を如実に示す宝物の数々」/ほか
★『中文会ニュース』第44号(中国の歴史と文化を学ぶ会)
*内容=「中文会第一回理事会報告」/「国旗解説〈青天白日旗〉」/「平成22年7月例会風景」/「詩 雪迎え」朝倉宏哉/「特集 遣唐使〈円仁)の足跡見つかる?」/「新中国語辞典【跟風】」/ほか
★『龍馬タイムズ』第94号(東京龍馬会)
*内容=「水戸と土佐の田中光顕」竹村紘一/「龍馬の母なる海・浦戸湾(下)」内川清輔/「龍馬考 Ⅰ」田村金壽/「こんな事もあったぜよ。」森義弘/ほか
★『北海道れきけん』第74号(北海道歴史研究会)
*内容=「アイヌを訪ねて(その二)─松林哲五郎の旅日記より─」久々湊昭三/「デフレの歴史」田中貢/「事務局だより」/ほか