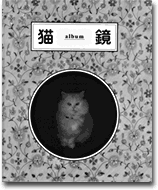大好評全国発売中!
須田相模守満親
信濃に発祥した須田一族、上杉謙信・景勝二代に仕え、豊臣秀吉が認めた須田満親
信濃須田一族
志村平治 著
A5判/192頁
定価2000円(税別)
信濃国高井郡須田郷(長野県須坂市)に発祥した須田氏、須田満親は若くして村上義清に諫言するなど将才をみせ、上杉謙信に仕え川中島合戦などで活躍する。また、その外交政治能力を買われ、景勝の近侍、上杉氏の奏者として政略・知略を発揮、その後、越中松倉城代、信濃海津城代などを勤め、豊臣秀吉に認められ豊臣姓を賜った。その須田満親を中心に信濃須田一族を描く
【主な内容】
一、須田氏の起源
二、須田満親の登場
三、満親と川中島の合戦
四、満親、越中に出陣
五、満親と御館の乱
六、満親、松倉城代となる
七、佐々成政との攻防
八、須田満親の野望
九、満親、海津城代となる
十、豊臣相模守満親
十一、満親、没す
購入のお申込は歴史研究会へ
【申込方法】葉書に書名と冊数をお書きになり、ご投函ください。
電話・FAXでも受け付けます。
【会員特典】代金後払い。代金は定価の3割引です。
発送手数料は何冊でも一回につき380円です。
【申 込 先】〒141-0031 東京都品川区西五反田2の14の10の504
歴史研究会サービスセンター
TEL 03・3779・3127 FAX 03・3779・5063
歴研[地名研究ブックレット]
加須と大桑─なぜ「かぞ」と「おおが」なのか─
野本誠一 著
A5判/62頁
定価800円(税別)
【主な内容】
第一章 日本書紀の検討
第一節 須を「ス」に読む(『日本書紀』岩波書店版)
第二節 須を「ソ」と読む(『日本書紀』八木書店版)
第三節 子と父について
第二章 和名類聚抄の検討
第一節 加須乃の字がある
第二節 石西郷の検討
第三節 淡甘郷の検討
第三章 国語辞典の父と昨日
第一節 倭訓栞
第二節 大言海と大日本国語辞典
第三節 現代版国語辞典
第四章 昨日と當昨日の検討
第一節 日本書紀(岩波書店版)の昨日と昨夜、「きず」「きぞ」と「きねふ」
第二節 万葉集(岩波書店版)の「きそ」
第三節 地元の歌集より
第五章 加須の地名
第一節 加須の地勢概要
第二節 加須市の地名(調査報告書第3集)の検討
第三節 加須の地名、加須良と加須山
第六章 武蔵志と新編武蔵風土記稿
第一節 父の地
第二節 父の古墳と子たちの古墳
第七章 先学の方々の諭稿(抜粋)
第一節 加須の字義及び草原郷の疑義について
第二節「カゾー」のいわれ
第三節 加須とその地名の変遷
購入のお申込は歴史研究会へ
【申込方法】葉書に書名と冊数をお書きになり、ご投函ください。
電話・FAXでも受け付けます。
【会員特典】代金後払い。代金は定価の3割引です。
発送手数料は何冊でも一回につき380円です。
【申 込 先】〒141-0031 東京都品川区西五反田2の14の10の504
歴史研究会サービスセンター
TEL 03・3779・3127 FAX 03・3779・5063
若井正一著
邪馬台国吉備説を提唱
吉備の邪馬台国と大和の狗奴国
発行所=総合出版社[歴研]
A5判/144頁
定価1260円(税込)
本書は邪馬台国吉備説を提唱するものです。そこで描くのは、三世紀に、吉備と大和との間で繰り広げられた壮絶な戦いです。それは後に吉備の桃太郎伝説の素材になりました。そして、その戦いの帰趨はその後の我が国を決定づけました。
邪馬台国の所在地を巡っては、有力な学者が大和説を声高に唱えるや、それで決まりというムードにあります。曰く、「邪馬台国は大和王権である。なぜなら、その訓みは、ヤマタイ国ではなくて、ヤマト国だからだ」と。本当にそうでしょうか。誰も疑問を抱かないこの命題に挑むことが本書の最大の特徴です。
いつ、どのようにして我が国は建国されたのか。それが本当のテーマです。ここに邪馬台国を論ずる所以があります。なぜならそれはヤマト国(邪馬台国)だからです。
【目次より】
プロローグ 岡山の桃太郎伝説
第一節 九州説、大和説、そして吉備説
第二節 『魂志』倭人伝の史料性とその意義
第三節 「共立」倭国が孕む「乱」
第四節 『古事記』・『日本書紀』による
大和王権の台頭
第五節 九州説、大和説への批判
第六節 女王国と邪馬台国
第七節 邪馬台国と大和王権
第八節 吉備の鯉喰神社に卑弥呼は眠る
エピローグ 温羅伝説と桃太郎
購入のお申込は歴史研究会へ
【申込方法】葉書に書名と冊数をお書きになり、ご投函ください。
電話・FAXでも受け付けます。
【会員特典】代金後払い。代金は定価の3割引です。
発送手数料は何冊でも一回につき380円です。
【申 込 先】〒141-0031 東京都品川区西五反田2の14の10の504
歴史研究会サービスセンター
TEL 03・3779・3127 FAX 03・3779・5063
毛利亮太郎 著 『上野焼尊楷渡来の研究 毛利吉成説の確立』
A5版 294ページ 定価3000円(税別)
発行=総合出版社[歴研]
付 萩焼坂高麗左衛門(李敬)
高取焼の高取八蔵(八山)
薩摩焼の星山仲次(金海)
豊臣秀吉が始めた文禄・慶長の役は焼物戦争ともいわれ、多くの焼物と陶工を得て来た。これに伴い陶工の渡来や、窯の時期について問題を残し、決着を見ていない事柄が多い。本書の主テーマは福岡県の中部で焼かれている上野焼を創めた上野喜蔵(尊楷)を連行して来たのは果して誰か、尊棺連行者の決定を問題にする。
というのは連行者に二説あって、一つは地許豊前に残る伝承と文書によるもので文禄元年、地許小倉城主毛利吉成によって渡来し、慶長三年には七十余名も伴って来たという吉成説。他の一つ清正説は慶長三年、隣国熊本城主加藤清正に従って来て、先ず唐津に逗留、その間に帰国し、陶法を学んで帰り逗留中、吉成に替わって入部していた細川三斎に招かれて来たとするものである。
著者は平成十年、先祖附の分析によって形成過程を調べ、清正説は事実の記載ではなく、創作されたものであるとした。つまり、清正説の偽説と吉成説の真説が仮説として成立したことになる。次の作業は仮説の検証になる。この連行問題は文禄・慶長の役の時のことであるから、まず、吉成と清正の進路図の作成が必要であった。そして、その間における主な戦い・会議・民衆の反応等を調べ、両将と尊楷の出会いの場所と時の想定と確認・渡来の時期・方法・経費・年代・同朋七十余名の得方と機会・再渡来の方法と可能性・岩屋高麗窯の開窯年代と陶工の割り振り方・開窯当時の陶工等の人数・陶工の生活事情・窯場人口の状況と藩の施策・その後の人口動態・上野焼初期の陶工や唐津の具体的な実情も知る必要がある。また細川三斎が宮津から伴って来た陶工又介関係の情報・窯場に関わる諸史料も活用し、尊楷連行者を主観を排し客観的、合理的に決定して行く必要がある。また、連行者決定の資料の信憑性の検討の為、高取八山、李敬、金海(星山仲次)のことも扱い、上野焼第一の窯問題で菜園場窯のことや『上野焼四百年』並びに陶工又介の経歴形成に関連して木島孝之氏の論文にも言及し、拙書が出した結論の妥当性の維持を図った。 (著者)
購入のお申込みは歴史研究会へ
【申込方法】全国誌『歴史研究』の会員応答係行葉書に書名と冊数をお書きになり、投函 ください。電話・FAXでも受け付けます。
【会員特典】代金後払い。歴研本ですので3割引(税別)でおわけいたします。
なお、送料は無料ですが取次手配料として1回につき380円いただきます。
【申 込 先】〒141-0031 東京都品川区西五反田2の14の10の504
歴史研究会サービスセンター
TEL 03-3779-3127 FAX 03-3779-5063
『信濃に発祥した岩井一族、上杉謙信・景勝二代に仕え、直江兼続を支えた岩井信能 』
信濃岩井一族
岩井備中守信能
志村平治 著
A5判/192頁
定価2000円(税別)
信濃国高井郡岩井(長野県)に発生した岩井氏は、越後の上杉謙信に仕え、岩井昌能は川中島合戦などで活躍する。その子信能は謙信の小姓としてその薫陶を受け成長「尋常の大将にあらず」と称される程の武将となる。直江兼続と意気投合し上杉景勝の近世大名化への基礎造り、長野県飯山町の基礎造り等に貢献した。その岩井信能を中心に信濃岩井一族を描く。
【主な内容】
一、泉氏と岩井氏
二、高梨氏と岩井氏
三、岩井満長(昌能)登場
四、信能、登場
五、御館の乱と岩井氏
六、武田氏の滅亡と信能
七、信能、飯山城代となる
八、飯山城修築と城下町造り
九、会津移封
十、米沢へ移封
購入のお申込は歴史研究会へ
【申込方法】葉書に書名と冊数をお書きになり、ご投函ください。
電話・FAXでも受け付けます。
【会員特典】代金後払い。歴研本ですので、代金は定価の3割引です。
発送手数料は何冊でも一回につき380円です。
【申 込 先】〒141-0031 東京都品川区西五反田2の14の10の504
歴史研究会サービスセンター
TEL 03・3779・3127 FAX 03・3779・5063
思い出とともに昭和を振り返る
『昭和は遠く』
第一章 昭和は遠く
名刺/秀行と周平/囲碁談義/たそがれ清兵衛/生年月日と名前/幼時の記憶/中野電信連隊の軍旗祭/ツェッペリン伯号のこと/付、メッサーシュミットの設計図/十六むさし/泰山木/耳で読んだ新聞/荻窪にもあった二・二六事件/新宿武蔵野館/戦艦 陸奥と長門/予科練 受験/伝書鳩で決まった人生/徴兵検査/獣医学校へ/空襲/戦中戦後の学生生活/ギブソンのギター/病原性好塩菌と小型円型ウィルス/猫の狂犬病/サマータイム/三菱重工ビル爆破事件/萩窪駅/ドイツの地名/ネアンデルタール/ドイツの地図から/ドイツの温泉/平衡感覚/絵と書/三碧木星/〝やばい〟/つつがなく/披露宴のスピーチ/箸/黄昏
趣味いろいろ
ハワイ音楽/犬関係/エアデール・テリアも使役犬ですか?/コリーの毛色の組み合わせ/ドーベルマンの毛色/ゴールデンの毛色は/ラブラドールはなぜイギリス原産/アルサシアンとはシェパード犬のことですか?/良いシェパード犬の仔犬の見分け方/荒川選手の3秒/オモト関係/大川製の肥料差し/疑問/鏡に映る姿/柴犬の尾/繁殖にあたってのジンクス/『新編武蔵風土記稿』について/科の木/井草生まれの本因坊六世知伯
第二章 ルーツを尋ねて
一、井口一族
先ずは、その出自から/道灌状から/井口姓へ改姓の周辺
二、村岡五郎平良文について
坂東八平氏の祖/父祖ならびに子孫
三、常州時代
発姓の地村岡
四、武州時代
愃持神社と恒持庄/平恒望/妙見信仰/武蔵村岡/
『今昔物語集』に登場する良文
五、相州時代
相模国府/平塚市田村/相模村岡/村岡城址/御霊神社
六、総州時代
良文終焉の地/良文の館跡/大友城址/源頼信、平忠常を攻める
七、おわりに
参考書籍・文献
井 口 昭 英 著
四六版 222ページ
非売品
戦後労使の新時代 粉擾の間に立って
『第一線労働基準監督官の回顧録』
加藤卓雄 著
B6判/192頁/定価=本体2000円+税
第一部 労働法の基礎知識
一 労働三法制定のあらまし
二 労働省・労働基準監督機関の設置
三 労働基準監督官の権限と使命
四 労働時間、休日の変遷の経過
第二部 新進労働基準監督官 我が道を行く
第 一 話 賃金の代りに「この牛を渡せと監督官は命令せよ!」
第 二 話 業務上災害(労災)になるかならないか
第 三 話 夜間臨検
第 四 話 細君の熱意が夫・杣人の労働災害補償を稔らす
第 五 話 残業と逢瀬の夜を偽れどたび重なれば親も知りなむ
第 六 話 夫のクレーン運転士試験合格は私の裏工作と宣伝した悪女の離婚騒動
第 七 話 出張中、旅館二階の張り出し手摺りから転落死、労災か
第 八 話 通勤災害は業務上(扱)
第 九 話 グレーカラー・エグゼンプションもある
第 十 話 使用者自ら労働安全衛生法
第十一話 大型プロジェクトの災害防止に挑んだ監督官の手記
第十二話 発電所土地造成17・5トンの爆破作業指示
第十三話 林道工事の劣悪な飯場からにげだし、救いを求める
第十四話 労災・障害補償費不正受給詐欺集団との対決
『大野寺ゆかりの空海建立 十四か寺』
大塚唯士 著
A5版 116ページ 定価1200円(税別)
「発刊の意義について」 徳島歴史研究会会長 笹田孝至
大野寺は、天智天皇の勅願寺といわれる徳島県内最古級の名刹で、その後空海によって十四の関連寺が建立されたと伝えられる。大塚さんは、阿波郡市場町の吏員時代から今日まで、長年にわたって現地踏査や伝聞収集を続け、地籍図・古地名小字名等を丹念に調べあげ、これに遺構や各種史料を重ね合わせて五キロ四方に及ぶ寺城と寺院跡を探し当てた。寺域のある阿波郡は、令制の国名「阿波国」の由となった地名を有し、徳島県内でも謎と空白部分の多い地域である。天智天皇の時代、聖地として大野寺が建立された阿波郡市場町域は、当時いかなる位置を占めていたのか。また、その前後には、どのような歴史が繰広げられてきたのか興味はつきない。地元の方はもとより、より広く多くの方に高評いただくことを願っています。
【主な内容】
空海の誕生
創建当時の大野寺の位置について
大野寺所在地の変遷
①阿定坊 梵光寺(仏殿庵) ②良珎坊 薬師庵
③宝憧寺 ④案内山 妙瞳寺 現篠原山常慶寺
⑤王子山最法院光福寺 ⑥智賢坊 薬師庵
⑦実相坊 輪蔵庵 ⑧得度山潅頂院切幡寺
⑨真如坊 観音庵 ⑩宝珠山虚空蔵院真福寺/
古虚空蔵 宝珠山真福寺/虚空蔵(田渕こくぞう) 宝珠山真福寺 ⑪宮ノ坊 善人寺 ⑫賢墳坊 永 福寺 ⑬南泉坊 円常寺 ⑭岡ノ坊
七福神社
空海(弘法大師)の略年譜
空海の考案 いろは文字
四国霊場番外納経所 光明庵(別名無銭庵)
堂が池大師堂について
[特別項]般若心経の畧解について
『平安僧兵奮戦記』
川村一彦 著
判型=A5判 96頁
定価=本体800円+税
この本は奈良仏教から平安仏教へ、遷都されて最澄と空海の出現によって、鎮護国家祈願の仏教から、一般大衆化されていく中、奈良の南都の興福寺や東大寺の勢力と、新興勢力の比叡山の天台宗山門派と寺門派との対立、朝廷への覇権を巡り「僧兵」を持っての嗷訴による熾烈な戦いの記録である。
【主な内容】
第一章 僧兵だった弁慶
第二章 僧兵の台頭
一、僧侶と流浪僧
二、荘園制度と有力寺院
第三章 寺院の人間構成
第四章 僧兵の出自と役割
第五章 朝廷と仏事
第六章 南都寺院の仕組み
第七章 南都僧兵紛争記
一、永久の嗷訴
二、院政と僧兵
第八章 北嶺の寺院の仕組み
第九章 北嶺の僧乱記
一、宗内抗争
二、山内紛争
第十章 南山と諸国の僧乱記
一、根来寺の僧兵
二、熊野の僧兵
三、大山寺の僧兵
法政大学史学会評議員・湯本軍一先生推薦の書
『信濃高梨一族』
上杉謙信を擁立、川中島で戦った名族の戦国史
志村平治著
A5判/192頁 定価1890円(税込)
出版を祝して…湯本 軍一
【主な内容】
一、高梨氏の起源
高梨氏の起源/ 高梨氏起源の諸説
二、源平の合戦と高梨氏
源平の合戦と高梨氏
三、鎌倉時代と高梨氏
鎌倉時代と高梨氏
四、高梨経頼と南北朝争乱
建武の親政と中先代の乱
足利尊氏、建武親政に抗する
中先代の乱の余波
南北朝の争乱
高梨氏衆中裁判 ほか
五、国人一揆
島津・高梨氏の押領の停止
高梨氏、小菅社の別当職の改任
国人一揆、守護職斯波氏に反抗
高梨氏の総領制武士団
六ケ郷用水 ほか
六、高梨氏同族一揆
守護家小笠原氏の分裂と高梨氏同族一揆
高梨政高、上杉勢を高橋に破る
政高、幕府への取りはからいを依頼する
政高、幕府方小笠原光康と戦う
七、越後の動乱と高梨政盛
高梨政盛の登場
政盛、山田高梨家を追放する
政盛、本拠を間山「石動館」に移す
信越国境の要衝高梨口
善光寺附近の攻防 ほか
八、文化人高梨澄頼
高梨澄頼の登場
澄頼と和歌
小館・鴨ヶ岳城完成す
島津貞忠との和睦
澄頼、将軍義稙に馬を献進 ほか
九、高梨政頼の登場
高梨澄頼、歿す
為景、政頼に救援を頼む
三分一原の合戦
長尾晴景、高梨氏を遠ざける
政頼、従四位下に叙される ほか
十、川中島合戦と政頼
長尾景虎、川中島出陣のこと
景虎、上洛する
善光寺のこと
弘治元年の戦い
高梨氏軍団の切り崩し ほか
十一、高梨喜三郎、誅殺される
御館の乱と喜三郎
高梨喜三郎、誅殺される
十二、高梨頼親の旧領信濃復帰
信濃旧領復帰
新発田重家攻め
頼親、上条義春、旗下となる
頼親、信濃本領安堵
上杉氏、真田昌幸を支援する ほか
十三、高梨頼親、改易
文禄の役に出陣
文禄三年の高梨氏の分限
高梨頼親、改易
十四、その後の高梨氏
会津移封
米沢高梨家、再興
寛文九年分限帳
尾張高梨家のこと
仙台高梨家のこと
十五、関山国師
高梨関連史跡 高梨系図Ⅰ
高梨系図Ⅱ 高梨氏年譜
高梨氏関連生没年表 参考資料
『風林火山の女たち 信玄をとりまく二十四人』
中津攸子著
B6判/192頁定価1575円(税込)
【主な内容】
武田信虎の側室・今井夫人
信虎、武田十八代継承/信虎の政略結婚/ほか
武田信玄の母・大井夫人
武田家と大井家の和を結ぶ大使/信玄の誕生/戦中の生活/ほか
今川義元の妻・定恵院
大井夫人の最初の子/武田と今川/父子の確執/ほか
武田信玄の正室・三条夫人
信玄との婚儀/三条家/信玄の実力/ほか
諏訪頼重の正室・祢々
祢々の結婚/虎王誕生/諏訪頼重包囲/和睦/ほか
武田勝頼の母・諏訪御料人
信虎と頼満/頼重の最期信玄の望み/勝頼の誕生
武田信玄の側室・油川夫人
甲斐の国乱れる/信縄と信恵の和睦/ほか
木曽義昌の妻・真理姫
真理姫の母/木曽義昌に嫁ぐ真理姫の輿入れ/ほか
穴山信友の妻・南松院
武田の一族、穴山氏/南松院の婚/亀石/ほか
北条氏政の妻・黄梅院
黄梅院の婚/甲相駿同盟破れる/ほか
武田義信の妻・今川夫人
信玄、信濃を征す/信虎の動き/ほか
武田勝頼の妻・遠山夫人
信玄父子の不和/勝頼の婚信勝誕生/信長包囲網/ほか
秋山信友の妻・織田夫人
信長包囲網/織田夫人の再婚/勝頼の長篠城包囲/ほか
諏訪勝右衛門の女房
木曽義昌の謀反/義昌征伐/武田軍崩壊/高遠城攻撃/ほか
勝沼信友の娘・理慶尼
武田王国の崩壊/新府城をあとに/ほか
武田勝頼の妻・北条夫人
氏政の妹、勝頼に嫁ぐ/北条夫人の人柄/ほか
徳川家康の側室・秋山夫人
穴山信君/秋山家の至誠/於都摩の覚悟/ほか
木曽義昌の母・木曽御料人
武田氏と信濃の諸将/木曽御料人の甲府入り/ほか
信玄の八男・小山田左衛門の妻
名門小山田家/織田軍迫るの報/ほか
葛山信貞の娘・了然禅尼
葛山十郎信貞逝く/了然禅尼関東に下る/ほか
穴山梅雪の妻、見性院
豊かな穴山氏/信玄の次女/穴山梅雪の動き/密使/ほか
織田信忠の許婚・松姫
松姫の誕生/婚約解消/高天神城攻防/ほか
上杉景勝の室・菊姫
信玄逝く/菊姫の婚/関が原の戦い/ほか
仁科五郎盛信の娘・豪姫
高遠の四季/信松禅尼と名乗る/極楽寺に眠る/ほか
武田関係略史
武田氏関係系図
◎歴史チャレンジ本
歴史浪漫〈大河ドラマシリーズ〉
『風林火山の世界』
歴史浪漫編集委員会編
発行所=総合出版社 [歴 研]
A5判/192頁/定価1260円(税込)
【主な内容】
「風林火山の基礎知識」編集部編
────────────────────────────
小説篇
「落城 榛名の風」戸処 徹
「信玄の最期・異聞」近藤 等
「武田信玄公お慕いの記〈第五回〉」美保真央里
────────────────────────────
論考篇
「武田家重臣、先祖秋山信友」秋山
「勝頼と理慶尼」竹村紘一
「信玄の海賊衆(水軍)」藤田衣風
「信玄の負け戦」藤田衣風
「戸石ノ会戦 ─『甲陽軍鑑』の虚実─」伊東久彦
「川中島合戦の真相はこうだ」高月恭平
「武田信玄の謎」杉崎 巌
「上総武田氏の興亡」中根一仁
「甲斐武田氏と常陸国との関わり」鈴木 安
「小山田氏と武田氏について」高橋慶伍
「武田信玄と鉄砲」澤田 平
「武田信虎・武田氏を隆盛させた名将」曽根 新
「武田氏復活に生涯を懸けた見性院」吉田裕志
────────────────────────────
随想篇
「後継者をめぐる武田家の悲劇」高橋 彰
「郷土の偉人武田信玄公に学ぶ」佐野三郎
「企業経営と風林火山」高橋信彦
────────────────────────────
紀行篇
「戦国の武将たちと激戦地」引田一三夫
────────────────────────────
【コラム】
「風林火山」関連基礎資料文献目録
「風林火山」関連文献・図書
信玄のかくし湯
【歴史浪漫地図】
信濃周辺諸城配置図
【巻末特別付録】
「風林火山」に集う・祭る
山本勘助の実在を示す[市河文書]
武田氏系図
「風林火山」と武田氏関連年表
 『海からみた卑弥呼女王の時代』 『海からみた卑弥呼女王の時代』
道家康之助 著
A5判/96頁/定価1050円(税込)
★本書で解ける三つの謎
一、この時代の「洛陽への海の道」を探究することにより、倭国が公孫氏に服属した実態。
二、倭国にきた二人の郡使の旅行記の相違点を究明することにより、陳寿は、二人の旅行記を誤って一括、倭人伝を編纂した。
三、問題の「水行十日陸行一月」は、邪馬台国が九州から大和に、狗奴国との戦争中、遷都した際、日本海側経由のルートの一部だった。
右の二、三の場合、「広志」の逸文は、謎解きのキーワードとなった。
【主な内容】
第一章 洛陽への海の道
1、どんな船で航海したか
2、本格的な帆船は隋・唐の時代から
3、航法と持衰
4、海と河(運河)のル―ト
第二章 卑弥呼の水軍
1、倭人国の喪失
2、公孫氏に属す
第三章 公孫淵の二股膏薬
1、呉の公孫氏懐柔工作
2、公孫淵、呉に遣使
第四章 卑弥呼の朝貢
1、公孫氏の滅亡
2、魏に服属を決める
3、朝貢は明帝の死の直前
第五章 二つの旅行記
1、魏略は明帝の事績まで
2、旅行記の相違点
第六章 女王国の位置
1、後漢書倭伝の原史料は魏略
2、女王国(邪馬台国)はどこか
第七章 黄幢と戦中遷都
1、黄幢は何のためか
2、戦争勃発
3、戦中遷都
第八章 張政を急遽倭国に派遣
1、宗女台与を立て王となす
2、元邪馬台国へ視察行
3、倭地参問
追 録 帯方郡はどこか
1、帯方郡の二説
2、浅 堆
3、郡治の所在
 歴研ブックレット 歴研ブックレット
『蒲生氏郷と家臣団』
──文武両道、秀吉に次ぐ未完の天下人──
横山高治 著
A5判/152頁/定価1200円(税込)
【主な内容】
第1章 蒲生飛騨守氏郷
1 蒲生飛騨守氏郷
2 蒲生郡の名家 蒲生家
3 近江源氏を離れ 織田家へ
4 伊勢大河内攻めに初陣
5 秀吉に接近 松坂・会津へ
6 キリシタン氏郷とローマ使節
7 氏郷の死と蒲生家の悲劇
第2章 氏郷没後の蒲生家三代
1 秀行の跡目相続
2 秀行、会津に復帰
3 忠郷の襲封
4 忠知、松山に転封
5 挽 歌
第3章 蒲生家家臣団
1 蒲生氏郷の将士加封
2 蒲生家の両輪
(1)伊勢平氏の名流、 関一政
(2)北畠武士の栄光、 田丸具直(直昌)
3 蒲生家支配帳(分限帳=家臣録)
随想 蒲生武士の古里
1 蒲生家発祥の近江日野
2 希望に燃えた伊勢松坂
3 懐旧 痛恨の会津若松
蒲生系図/蒲生家四代略年譜
【特別再録】栄光の近江源氏「佐々木氏」

『祇園精舎の鐘の声』
平家一族終焉の地、下関生まれの作者が訪ねる源平合戦鎮魂譜
「平家物語」わたしの旅
真砂早苗 著
A5判/160頁 定価1575円(税込)
まえがきに代えて『寂光院』
祇園精舎の鐘の声/仮本堂
第1章 娑羅双樹の花の色
『平家物語』の底糸/娑羅の白い一日花/釈尊の沙羅と平家の沙羅 他
第2章 語られた『平家物語』
第3章 伊勢平氏の故郷
安濃津/産品/上総介/坂東八平氏/伊勢平氏の始まり/忠盛 他
第4章 清盛の為した仕事
音戸の瀬戸開削/厳島神社造営/高野山大塔修築落成/兵庫築港 他
第5章 夜の厳島
第6章 大三島
多島海/大山祇神社/宝物館/河野通信の鎧/義経の鎧/頼朝の鎧 他
第7章 屋島
第8章 備前備中
有木別所跡/瀬尾兼康/藤戸
第9章 竹生島
竹生島/連絡船/乗客三人/ニュートウリョウ/祈りの石段/宝厳寺 他
第10章 「宇治川の先陣」
生食と麿墨/いざ戦場へ/梶原景季と麿墨/佐々木高綱と生食 他
第11章 義賢・義仲の故郷
大蔵合戦/大蔵館の跡/義賢の墓所/鎌形八幡/班湲寺/菅谷館 他
第12章 頼朝の故郷熱田
頼朝の母/熱田さま/誓願寺
第13章 頼朝と政子偕老同穴になれず
鎌倉白旗公園/寿福寺/落椿
第14章 修禅寺
修禅寺物語/範頼/頼家暗殺/因縁の血筋/指月殿
第15章 源義朝の最期知多半島野間
野間の町/大御堂寺/義朝の墓/木太刀奉納/妻の驚愕/絵解き 他
第16章 熊野水軍の根拠地紀伊田辺
紀伊田辺へ/弁慶/熊野信仰の玄関口/熊野水軍の根拠地/闘鶏神社
第17章 高野山
高野山/平維盛/宿坊/護摩壇山/落人維盛の伝承
第18章 熊野
熊野詣で/熊野本宮大社/平重盛参詣/熊野速玉大社/那智大社 他
第19章 安宅関
義経都落/逃避行/安宅関
第20章 能登平時忠配流先
曽々木海岸/平家にあらざれば/時国/上時国家/下時国家
第21章 平泉
遮那王鞍馬脱出/再び平泉へ/弁慶の最期/高館・義経堂 他
第22章 義経の首藤沢市白旗神社
義経最期/首実験/白旗神社
第23章 大宰府
防衛の地/都府楼跡/博多の津/清盛と大宰府/大宰府落ち
第24章 筑後柳川沖端の六騎
筑後柳川沖端町/沖端川/郷土資料館/有明海/トンカジョン白秋/御花
第25章 椎葉への船旅
あとがき 自分の山にのぼれ
関門海峡/転勤/歴史を歩く/自分の山にのぼれ 他
年表/皇室系図/藤原氏系図/平家系図/源氏系図/本書で歩いた場所
主な参考文献
『宮本武蔵研究論文集』
武蔵一筋──長年の地道な研究成果を世に問う
福田正秀 著
A5判/248頁 定価:本体4000円+税
【主な内容】
大坂の陣と出頭人戦略
一、はじめに
二、大坂夏の陣、徳川方の証明
三、三木之助の系譜
四、本多家の武蔵
五、小笠原家の武蔵
六、島原の陣と武蔵
七、おわりに
武蔵の出自は田原氏か?
一、生きていた田原家貞
二、祖父母墓碑の謎が教えていた
三、武蔵は田原氏か
四、おわりに
武蔵の関ヶ原東軍の証明
一、はじめに
二、証明(一)『兵法大祖武州玄信公傳来』
三、証明(二)「慶長七・同九年黒田藩分限帳」
四、証明(三)黒田二十四騎と慶長五年免許状
五、証明(四)足跡
佐々木小次郎はいなかった―考証・巌流島―
一、巌流島の決闘は史実か
二、相手の名は佐々木小次郎か?
三、津田小次郎説(一)『兵法大祖武州玄信公傳来』
四、津田小次郎説(二)『兵法先師伝記』
五、おわりに
武蔵・弥四郎 秘密の御前試合
一、はじめに
二、『二天記』と雲林院氏顕彰碑文
三、柳生宗矩の紹介状を発見
四、弥四郎の正体
五、おわりに
資 料 篇
一、『五 輪 書』(抜粋─序文と空の巻─)
二、武蔵自筆書状(有馬直純宛・長岡佐渡守宛)
三、独行道
四、小倉碑文(宮本武蔵彰徳碑)
五、泊神社棟札「田原家傳記」
六、宮本家系図
七、宮本武蔵年譜
研究余録
一、寺尾孫之丞の墓発見(『五輪書』相伝者)
二、素晴らしい出合い
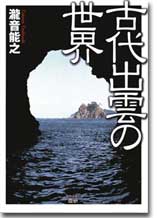 『古代出雲の世界』 『古代出雲の世界』
『古事記』『日本書紀』にはみられないもうひとつの日本古代史
神話の国・出雲の風土と原像を読む
瀧音能之著(駒澤大学文学部助教授、島根県古代文化センター客員研究員)
B5判/141頁/定価:本体2000円+税
【内容】
第一部 風土記にみる古代の出雲
第一章 出雲の風土
1風土記
風土記撰進の官命/風土記という名称/五風土記と風土記逸文
2『出雲国風土記』
編纂の主旨/内容と特色
3「イズモ」とは何か
出雲国の成立/国名の由来/「出雲」の語源
出雲=厳藻説/地名由来の謎
4古代の景観
狭布の稚国/河川/平野部/入海と水海/島根半島
第二章 出雲の社会と文化
1出雲国の行政
政治の中心地/出雲国司/出雲国の正倉/郡内の政務/交通路/軍団と軍事施設
2出雲の氏族と出雲国造
郡司層を構成した氏族/建部郷の氏族/出雲臣/出雲国造家/神火相続/出雲国造神賀詞/古伝新嘗祭
3海の幸・山の幸
水産物/農産物/植物/動物・鳥類/特産品/玉作り/鉄の生産と目一つの鬼
4生活と信仰
恵曇浜の開発/市のにぎわい/海に開かれた洞窟──古代の死生観/寺院の建立/国分寺と国分尼寺
第三章 出雲の神話と神々
1出雲の神話
二つの出雲神話/ヤマタノオロチ退治神話/スサノオ神の原像/国譲り神話/杵築大社の造営/国引き神話
2四大神
熊野大神/佐太大神/野城大神/大穴持命
3神々の系譜
神魂命の御子神/スサノオ神の御子神/大穴持命の御子神
第二部『訂正出雲風土記』
(千家俊信大人校訂・文化三年刊行)本文
総記/意宇郡/島根郡/秋鹿郡/楯縫郡/出雲郡/神門郡/飯石郡/大原郡/仁多郡/巻末記も
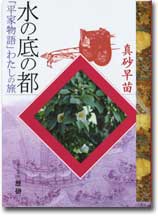 『水の底の都』 『水の底の都』
今や夢、昔や夢とまよはれて
「平家物語」わたしの旅
真砂早苗 著
A5判/274頁 定価1890円(税込)
京都・神戸・伊豆・木曽・下関……「平家」の舞台に身を沈め、
残された断片に往時の声を聴きつづける旅の終わり……
いま「物語」は微かな風にそよいで蘇る!
【主な内容】
六波羅模様
朱雀大路/保元、平治の乱/六波羅平家町/清盛はん 西八条邸の楠 盛子と徳子/鹿ノ谷の陰謀/好敵手、後白河院/神護寺の似せ絵/小松殿/御輿 振り/祇王と仏/右京の恋
福原の夢
福原ニュータウン/音戸の瀬戸/兵庫築港/福原遷都/清盛塚
伊豆の流人殿
蛙ガ小島の頃/旗挙げ/石橋山/そして富士川
木曽を吹く風
倶梨迦羅山/老い武者、実盛/兼康の生き方/朝日将軍/粟津の松原
一の谷あたり
都落ち/捲土重来/生田の森/山の手の戦い/奇襲、坂落し/武士の生き甲斐/一の谷今昔/敦盛寺/小宰相/総帥、宗盛
屋島巡礼
屋島台地/義経急襲/那須与一遺聞/維盛出奔/流浪の幼帝/巡礼の海
厳島の海
厳島神社/平家納経/二位尼/弥山の山影
平家入水
関門海峡/たぎりて落つる潮/浪の下の都/見るべき程の/平家蟹/幼帝墓陵/戦犯処分/平孫始末記
寂光院への遺
敦賀街道/寂光院春秋/大原御幸小原菊
落人村情歌 あとがきにかえて
湯西川余情/山陰の浪高く/ひえつき節
追 記
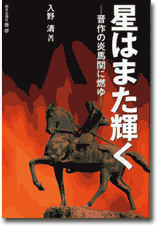 『星はまた輝く』 『星はまた輝く』
――晋作の炎馬関に燃ゆ――
入野 清 著
A5判/244ページ
定価=2000円+税
──この本は、幕末第二次征長(四境)戦争で、圧倒的に優位とされた幕府軍に奇兵隊を率いて勝利し、連合国の黒船外交の前に植民地化されかねない日本国を自主独立へと導いた男の物語です
【主な内容】
第1章 高杉家と長州藩毛利家
晋作の誕生と幼年時代/高杉晋作、結婚する/吉田松陰先生を知る/桜田門外の変おきる/丙辰丸の盟約/関東、北陸試撃行/世子小姓役となる ほか
第2章 長州藩、攘夷を決行する
朝廷、攘夷祈願と節刀の儀を行う/幕府攘夷決行日を五月十日とする/長州藩、攘夷を決行する(馬関戦争)/晋作、萩、草庵に入る ほか
第3章 奇兵隊の誕生
奇兵隊の軍中規則/小倉藩との対立/小倉藩弾劾書/先鋒隊と奇兵隊との区別/先鋒隊と奇兵隊の争い ほか
第4章 八月十八日京の政変と長州藩
孝明天皇、大和国行幸決まる/八月十八日、政変おきる/七卿都落ち/俗論党の台頭/奇兵隊小郡へ移る/薩賊、会奸 ほか
第5章 禁門の変おきる
晋作、又兵衛説得ならず/晋作、野山獄に入牢/周布、獄中の晋作を訪う/池田屋騒動おきる ほか
第6章 四ヶ国連合艦隊の下関砲撃と講和使節正使
四ヶ国連合艦隊への襲来延期策の失敗/横浜鎖港問題とパリ廃約/井上に第四大隊を付与する/晋作、講和正使となる/晋作らに身の危険せまる/晋作ら第二回講和交渉を欠席する/第三回交渉 ほか
第7章 晋作、決起す
五卿、筑前渡航を決心/薩摩への疑惑/晋作決起す/晋作の決起演説/俗論派、正義派を斬罪に処す/幕府第一次征長兵撤退と五卿渡海 ほか
第8章 第二次征長(四境)戦争前夜
晋作、佐世への手紙/英国行きを希望/伊藤に同行を求む/下関に戻る/下関替地問題と外国応接掛の辞任ほか
第9章 第二次征長(四境)戦の戦端開く
大島口への攻撃/芸州口の戦/小倉口の戦/坂本龍馬、乙丑丸で参戦す/小倉城炎上す/石州口の戦/油屋の火事 ほか
第10章 症状悪化の晋作、野村望東尼を救う
晋作の皮鞄/野村望東尼の救出/晋作、捫虱処に移る
第11章 晋作の炎、馬関に燃う
谷家の創立/巨星落つ
第12章 星はまた輝く
薩摩、長州藩に倒幕の密勅下る/討幕派諸藩兵の集結/坂本龍馬、中岡慎太郎の遭難 ほか
『太平洋戦史文献総覧〈全1巻〉』
遂に成る太平洋戦争の記録資料文献の宝庫
――戦史・手記・回想録・日誌・現地報告等を地域別に分類整理集成
井門 寛編著(元国立国会図書館副館長)
B5判・函入・656頁・定価=本体二八〇〇〇円+税
〔主な内容〕
1 ハワイ地域・米国本土
真珠湾攻撃/九軍神伝/米本土攻撃
2 マレー・シンガポール地域
陸戦記―一部空戦記を含む
海戦記
3 ビルマ地域
陸戦記/空戦記/加藤建夫伝
4 比島・蘭印地域
陸戦記(比島 山下裁判)
蘭印―一部空戦記を含む
海戦記(比島海域・蘭印海域
―インド洋を含む)
空戦記(神風特攻隊・学徒兵)
5 南太平洋地域
陸戦記(ソロモン諸島・ビスマルク諸島・ニューギニア)
海戦記(珊瑚海の戦・シドニー攻撃)
空戦記(山本五十六の死)
6 中部太平洋地域
陸戦記(マリアナ諸島・小笠原諸島・その他の地域)
7 北太平洋地域
陸・海・空戦記
8 満・蒙地域
陸戦記(ソ連抑留記)
9 国内
陸戦記・沖縄
海戦記(沖縄海域・本土海域)
空戦記/市民の罹災記録/原爆の記録/軍事裁判・戦犯/その他
10 戦史・写真・絵画、軍人伝記
陸戦史/海戦史/空戦史写真・絵画陸軍関係・海軍関係・航空隊関係
付録=関係地図/終戦時における陸軍主要部隊編成一覧/連合艦隊主要艦艇要覧/太平洋戦争関係年表/著(編)者索引
 『対馬・壱岐史を追う』 『対馬・壱岐史を追う』
古代日本の政治経済文化の探求Ⅰ
荒井登志夫 著
A5判/64頁 定価840円(税込)
対馬と壱岐の古代の姿を追求し、両島が大陸との架け橋であったほか、対馬は強力な武力を有して古代国家の創立に関わっていたと窺われること、壱岐は占いと実り豊かな島であったことを指摘。また、対馬の金田城は、現在の城山ではなく名称の如く金田の地にあったはずであるとして、所在地の推理を行っている。
第一章 対馬の古代史を追う
1 対馬の環境
2 古代の対馬
(1)対馬の考古学
(2)文献等が伝える古代の対馬
ア 文献等の記述 イ ?知
(3)信仰と占い
ア 信仰と占いの島 イ 和多都美神社海中の鳥居の謎
第二章 金田城は金田の地に見出すべし ──金田城所在地論
1 「金田城跡」の見学
2 現「金田城」への疑問
3 銀山発見と金田城の築城
4 金田城は金田の地に
5 敵の進路を塞ぐ佐須の山河
第三章 壱岐の古代史を追う
1 壱岐の環境
2 壱岐の古代
(1)古代の壱岐
(2)原の辻遺跡の特徴
(3)三重の環濠を巡らせていた理由
別表 対馬・壱岐出土の金属製の利器
1 銅矛
2 銅剣
3 対馬からの鉄剣・鉄刀の出土状況
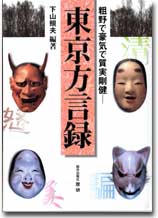 『東京方言録』 『東京方言録』
武蔵野方言の収集、二十年の労作!
下山照夫著
A5判 280頁 定価2100円(税込)
すべての言葉の歴史は古代から継承され、時代ごとの領主、支配者と配下の連中により徐々に変遷して現在に至っていると考えられよう。言葉は貴重な文化であり、人間は自己の意思を言葉の表現により共存して生きながらえたのである。どんな言葉と雖も生存上重要であった。またどのような文言であり表現であっても、永年伝えられた言葉は言葉として語り残さねばならない。いやな、へんな言葉だからといって消え去らすことは不自然である。そして言葉は過去・現在・未来へと承継する義務が我々にはある。(あとがきより)
【主な内容】
一、武蔵野語をはじめ歴史的に関わりある東京方言を二十余年にわたり収集した。
一、収集した方言は東京二十三区内及び都下の旧家に通用したものである。
一、ここでは、二五〇〇語余を選び、あいうえお順に配列した。
一、一方言に対し、一解釈とした。
一、文法上、語音と変格活用は方言の特徴といえよう。その点を、留意した。
いを「え」に、かを「け」に、
たを「て」に、なを「ね」に、
ひを「し」に、まを「め」に、
やを「え」に、等。
一、関東のべえべえ言葉なる特徴が窺える。
一、武蔵野語は粗野で豪気で質実剛健の気風が漲ぎる。但し善良で人情味に溢れる。
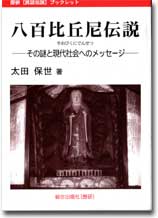 『八百比丘尼伝説』 『八百比丘尼伝説』
──その謎と現代社会へのメッセージ──
太田保世 著
A5判/96頁/予価1050円(税込)
【主な内容】
第一章 八百比丘尼伝説の概要
第二章 何が「謎」なのか?
第三章 各地の「八百比丘尼伝説」
一 隠岐の八百比丘尼伝説
二 会津の八百比丘尼伝説
三 若狭(小浜)の八百比丘尼伝説
四 能登の民話での八百比丘尼
五 佐渡の八百比丘尼伝説
六 安濃町の八百比丘尼伝説
七 栃木県西方町の八百比丘尼伝説
八 その他の土地の八百比丘尼伝説
第四章 八百歳まで生きられるか?
第五章 八百比丘尼は一人か?
第六章 山岳宗教などとの関係
第七章 遊行女婦
第八章 朝日長者伝説との関わり
一 松浦の小夜姫
二 大分の朝日長者伝説
三 南会津下郷町の朝日長者伝説
四 戦場ヶ原の猿麻呂伝説
五 その他の伝説――朝日さす夕日輝く――
第九章 八百比丘尼はなぜ死んだか?
第十章 生と死の諦観
第十一章 神話・民話の世界
第十二章 超高齢社会と八百比丘尼
第十三章 美しく老いるために
一 学び続け、教え続けること
二 義務性を失わないこと
三 社会性を失わないこと
四 未来を考え、未来を語ること
五 自然な佇まいをもつこと
『墨俣一夜城』
──秀吉出世城の虚実と蜂須賀小六──
牛田義文 著
A5判/336頁 定価3570円(税込)
【主な内容】
第一章 信長の美濃侵攻以前
一 蜂須賀小六と織田信秀・信長
二 岩倉城家老稲田氏の受難と蜂須賀小六
三 蜂須賀党の肥大化
第二章 信長の西美濃作戦
一 永禄三年の墨俣侵攻
二 永禄四年の墨俣侵攻(森部合戦)
三 永禄五年の墨俣侵攻(軽海合戦)
四 森部・軽海、両合戦は一連の合戦か
五 『美濃国諸旧記』等と木下藤吉郎
六 西美濃侵攻の実体
第三章 信長の東美濃作戦
一 信長の小牧築城
二 川筋衆(川並衆)
三 川筋衆と松倉城(坪内一族)
四 前野将右衛門長康の出自(生駒・坪内・前野)
五.犬山落城とその時期
六 竹中半兵衛の稲葉山城占領(美濃の内乱)
七 東美濃攻略戦と藤吉郎
第四章 墨俣一夜城
一 小六の臣従
二 墨俣築城問題の要点
三 墨俣一夜城に関する通説と異説
四 築城否定説の論拠
五 江戸期や蜂須賀家の築城話
六 『生駒家譜』と『蜂須賀家記』
七 蜂須賀党の面々とその記録
八 墨俣築城の存否と年次の問題─築城否定説は正しいか
九 『信長公記』『重修譜』等との問題点
十 『武功夜話』に対する非難の当否
十一 伏屋一夜城の問題
第五章 終 章
一 墨俣は軍事上の要所である
二 築城否定説に対して
三 結 語
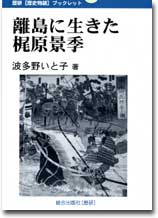 『離島に生きた梶原景季』 『離島に生きた梶原景季』
波多野いと子 著
A5判/68頁 定価840円(税込)
梶原景時の子──梶原景季
宇治川の合戦では名馬・磨墨を駆り、佐々木高綱と先陣を競いあった。平家追討時には源範頼の本隊に加わって活躍し、一ノ谷・生田の森の合戦では、箙に梅花の枝をさして奮戦。平家武者から「花箙の源太」と呼ばれて喝采をあびたという。文武両道に長けた若武者。その生涯を描く。
【もくじ】より
第一章 興津からの脱出
第二章 美濃の根尾谷入り
第三章 播磨へ
第四章 甑島上陸
第五章 播磨回想
第六章 甑島内
第七章 島の梶原館
第八章 城氏の乱・豊丸羽黒入り
第九章 刻を越えて
◎歴史チャレンジ本
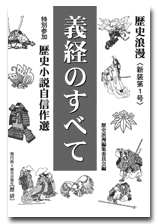 『義経のすべて』 『義経のすべて』
[特別参加] 歴史小説自信作選
歴史浪漫編集委員会編
A5判/168ページ/定価2100円(税込)
【主な内容】
源義経の基礎知識………編集部編
─────────────────────────────
小説篇
源九郎義経………佐藤清治郎
源氏三代と北条政子の生涯………外処 徹
─────────────────────────────
論考篇
義朝第一の郎党・鎌田政家とその一族………竹村紘一
義経北行伝説と為朝南行伝説
──二人の英雄とアイヌ・沖縄──………片倉 穰
源義経阿波国桂浦(勝浦)に上陸………福良敬之
みちのくに何故?「蒙古之碑」と
「マルコ・ポーロとフビライ像」………内ヶ﨑晴男
義経・弁慶・「泉田」中野………中野嘉弘
打倒平氏の一番槍は妖怪退治の勇者………足立武之
─────────────────────────────
随想篇
日本史こぼれ話 鹿も四つ足、馬も四つ足………加藤 蕙
源義経はどこで生まれたか………椋本千江
義経と私………田守典子
源平合戦と芭蕉の風景………常磐恵一
寿永版「風とライオン」………引田一三夫
─────────────────────────────
紀行篇
早春の京都に源義経と
平家一門ゆかりの旧跡を訪ねて………川本斉一
[特別参加]歴史小説自信作選
武田信玄公お慕いの記〈第四回〉………美保真央里
怨嗟の雷………町井 譲
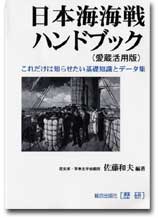 『日本海海戦 ハンドブック〈愛蔵活用版〉』 『日本海海戦 ハンドブック〈愛蔵活用版〉』
これだけは知らせたい基礎知識とデータ集
佐藤和夫 編著(歴史家・軍事史学会理事)
B6判/96頁 定価:本体800円+税
◆主な内容
第1篇 日本海海戦の基礎知識
プロローグ バルチック艦隊を迎撃するまで/
マカロフ中将と藤井較一大佐/
黄海海戦・蔚山沖海戦/人事異動/
バルチック艦隊の大航海/
旅順口閉塞と203高地/要塞・旅順/
バルチック艦隊の対馬海峡通過予測の是非/
密封命令/藤井較一参謀長の信念/
島村速雄司令官のタイミング/敵艦見ユ…/
会敵/丁字戦法/丁字戦法の有無/降伏/
エピローグ 日本海海戦の意義/参考文献
【基本資料】
バルチック艦隊の航路
バルチック艦隊の予想航路
日本海軍艦隊編制表
日本海海戦タイムテーブル5月27~28日・戦果
第2篇 日露戦争年表
第3篇 日露戦争 参考資料・図書
【付録データ】
日本海海戦時の日本連合艦隊指揮官幕僚
ロシア太平洋第2艦隊(バルチック艦隊)指揮 官・幕僚
第4篇 日露戦争主要人名辞典
日本側人名辞典=秋山真之・安保清種・
荒尾文雄・有馬良橘・飯田久恒・伊知地季珍・
伊知地彦次郎・伊集院五郎・伊集院俊・
瓜生外吉・大山巌・小倉鋲一郎・片岡七郎・
加藤友三郎・桂太郎・金子堅太郎・上村彦之丞・
川嶋令次郎・清河純一・黒井悌次郎・
児玉源太郎・小林躋造・小村寿太郎・斎藤孝至・
佐藤鉄太郎・四竈孝輔・嶋村速雄・下條於兎丸・
下村延太郎・鈴木貫太郎・竹内重利・武富邦鼎・
筑土次郎・寺垣猪三・出羽重遠・東郷平八郎・
東郷正路・永田泰次郎・乃木希典・日高壮之丞・
百武三郎・平岡貞一・藤井較一・三須宗太郎・
村上格一・明治天皇・森山慶三郎・山崎鶴之助・
山路一善・山下源太郎・山田彦八・山本英輔・
山本権兵衞・山本安次郎・吉田清風
ロシア側人名辞典
アレクセーエフ・ウィッテ・ウィトゲフト・
エッセンカシーニ・クロパトキン・
ニコライ2世・ネボガトフ・ベゾラゾフ・
マカロフ・ロジェストウェンスキー・
ローゼン・ルーズヴェルト
第5篇 日本海海戦基礎データ集
日本海海戦時の主要艦艇/
日露戦争での海軍諸作戦/
連合艦隊解散之辞/海軍用語ミニ知識
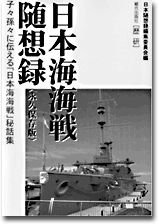 日本海海戦100周年記念 日本海海戦100周年記念
『日本海海戦随想録』
子々孫々に伝える「日本海海戦」秘話集 増補改訂版
A5判/320頁 定価3150円(税込)
二〇〇三年五月に発売された『日本海海戦随想録』は、大好評のうちに、わずが三ヶ月で完売となりました。そこで二〇〇五年の「日本海海戦一〇〇周年記念」を機に、内容をさらに充実させた『日本海海戦随想録〈永久保存版〉』が、刊行されました。好評の初版内容はもとより、増補改訂版のために新原稿・新情報を加え、さらに充実した内容となっております。
◆主な内容
第一篇 名随想発掘「日本海海戦」
これまでに書かれた日本海海戦をテーマにした名著・入 手不可能な雑誌等から名作を発掘し、一挙掲載
【執筆者】東郷平八郎/秋山真之/小笠原長生/佐藤鉄太
郎/鈴木貫太郎/セメヨノフ/佐藤市五郎/筑土龍男
第二篇 名士が語る「日本海海戦」
日本海海戦関連の諸団体・神社の方、また戦史研究家・ 国際関係研究家の方々に研究や論考を依頼。
【執筆者】外山三郎/北澤法隆/平間洋一/飯倉章/喜多 義人/並河義孝/津島勝二/川野晄明/福地誠夫/常廣 栄一/金森正/川島裕/手塚正水/中島洋/羽鳥紀道/
稲葉千晴/佐藤和夫
第三篇 子孫が語る「日本海海戦」
日本海海戦ゆかりの子孫の方々に原稿を依頼し、子孫に 直接伝えられた逸話や知られざるエピソードなどを収録。
【執筆者】山本衞/東郷宏重/東郷民子/保坂宗子/小宮 保/藤井和子/安保二見男/山村百合子/殖田久荘/東
郷彪/東郷一雄
第四篇 公募随想「日本海海戦」
日本海海戦ならば自分もひとこと!参加したい!と思っ ている一般の研究家・著述家に公募。在野の研究家・著 述家の方々の珠玉の作品を集成する。
【執筆者】中名生正己/岡本陽子/高月恭平/竹村紘一/ 藤田衣風/都宮一充/杉崎巌/村上喜代志/村田武一/
永井秀/稻垣直/吉岡健二/中谷碩男/加藤卓雄
第五篇 論考・随想「陸戦編」
永久保存版刊行に際し、新たに加えられた論考集
【執筆者】野澤日出夫/杉崎巌/中名生正己/吉岡健二/
神島礼/兒玉真由美/下田和伸/藤田衣風/岡本憲和
第六篇 一〇〇年目の動き
〈コラム〉日本海海戦エピソード・街角にみる日本海海戦ほか
 150年の時をへて蘇る 150年の時をへて蘇る
『新選組随想録』
語り継ごう幕末剣士集団の実像と秘話
日本随想録編集委員会編
A5判/160頁
定価2520円(税込)
歴史上のできごとや、活躍した人物に思いを馳せ、歴史をエッセイで綴る、〈歴史に学ぶ人生訓シリーズ〉の第一弾として『日本海海戦随想録』を刊行。同書の大好評に応え、第二弾として、『宮本武蔵随想録』を刊行いたしました。シリーズ第三弾は『新選組随想録』です。平成十六年、NHK大河ドラマで「新選組!」が放送されましたが、「史実と違う」「誤解しないで欲しい」「これだけは知っておいて欲しい」と、新選組への思いが胸に溢れている方々が多いのではないかと思います。そこで、日頃、新選組に心を寄せられているみなさんに、ご寄稿いただき、随想集にまとめました。さまざまに描かれてきた新選組の知られざる姿を、随想の中から描き出します。ぜひ、お楽しみ下さい。
【主な内容】
第一篇 新選組回想録
赤誠一途の道をゆく…………釣 洋一
第二篇 論考・随想
新選組前史……………………………竹村紘一
新撰組 副長助勤 安藤早太郎……………永井 秀
新選組の武士道……………………横山忠弘
新選組と土佐藩浪士……………吉岡健二
私の新選組……………………………金剛ゆみ
土方歳三と私………………………児玉公生
高台寺党の復讐………………………松本 茂
誠の歌・新選組士魂……………石田良雄
神道無念流剣客 横倉喜三次の生涯……………大久保甚一
容保公と近藤勇………………長山ゆき子
推定憶測詳述私考論……………川本斉一
埼玉の豪農根岸友山と新撰組……………齋藤健司
池田屋事件……………………………岡本憲和
松平容保が京都守護職に任命された理由を探る………………………近藤圭二
基督教信者になった宮古湾海戦の勇者……………山口春音
清河八郎と新選組………………小野光雄
幕末維新に開花した新選組 花のロマンと逆進性……………………横山高治
第三篇 新選組隊士への手紙
新選組隊士の皆様へ……………西尾 薫
新選組隊士 伊東甲子太郎さま………岡本小百合
新選組隊士の皆様へ………上原恵美子
土方歳三様……………………………児玉公生
斎藤一様……………………………倉原さや香
近藤勇様……………………………長山ゆき子
沖田総司様……………………………金剛ゆみ
隊士ご一同様………………………神津 圭
芹沢 鴨様……………………………宍戸仁美
第四篇 資 料
新選組年表/写真コラムほか
 『葦原中つ国の世紀』 『葦原中つ国の世紀』
──日本古代史解明の手引──
荒井登志夫 著
A5判/64頁 定価840円(税込)
【主な内容】
第1章 古代国家の国名と国家像
1 古代の日本は「倭国」と呼ばれているが、「倭」とはいかなる意味か
2「葦原中つ国」とはいかなる国か。また、記紀には「葦原の水穂国」という国名も登場 する。これについて解説されたい
3 後漢書の建武中元2年(西暦57)の「倭奴国」と永初元年(107)の「倭国」(あるいは 「倭面土国」)の関係はどのように考えられるか
4 志賀島出土の金印に記された「委奴国」とは魏志倭人伝の「奴国」と同じか。また、 「倭面土国」という国名表記もあるということだが、これは何か
5「倭国大乱」の実像をどのように考えるか
6 志賀島から「倭奴国王」の金印が発見されるに至った背景はどのように考えられるか
第2章 出土遺物と出雲
1 銅鐸は祭祀に用いられた祭器とされているが、どのような宗教的意義を持つものか
2 銅鐸がイザナギノ命を祭る祭器であるならば、妻のイザナミノ命を祭る祭器はなかっ たのか
3 西日本から大量に出土している銅利器はどのような意義を持つものか
4 出雲から銅鐸あるいは銅利器が大量に発見されているが、出雲とこれらの祭器の関連 について説明を求む
第3章 邪馬台国問題
1 邪馬台国の所在地は大和か九州か
2 邪馬台国は日本のいつの時代に当たると考えられるか
3「奴国」、「不弥国」及び「投馬国」はどこか
4 邪馬台国に対立していたとされている「狗奴国」とはどこか
5 狗奴国が北陸(くぬがみち)ないし丹波国とするならば、何ゆえ大和国から程近いこ れらの地域が筑紫北部や吉備国に比べ平定が遅れたのか
6 邪馬台国時代の国家(クニ)とはどのようなイメージで捉えればよいのか
7「卑弥呼共立」とはどのような意味か。また、卑弥呼に政治的な権力はあったのか
8 魏志倭人伝に記された「一大率」などの倭の諸国の官制はどのように理解されるか
9 卑弥呼に下賜された魏鏡は三角縁神獣鏡であると言われるが、この鏡は国内では多量 に出土し、大陸ではまったく出土していない。これはなぜか。また、伝世鏡論について どう思うか
10 卑弥呼は誰か
11 モモソヒメの出自、さらには兄弟はどうなっているか
12 モモソヒメが卑弥呼ならば都はどこに置いたのか
13 卑弥呼の墓はどこか
14 卑弥呼の年齢は魏志倭人伝に「巳に長大」と記されているが、モモソヒメは何歳ぐらい まで生きたのか
15 書紀の箸墓造成の記述である「昼は人が作り夜は神が作る」とはどういうことか
16 卑弥呼がモモソヒメであるとすると、古事記や日本書紀に女王として現れないことを どのように理解するのか
17 魏の使節のたどったルートはどのようなものか
18 卑弥呼が魏の皇帝からもらった金印はどこに行ってしまったのか
19 卑弥呼は女王に就いて相当の期間を経た後魏国に使節を派遣しているが、西暦238 年ないし239年に至って初めて使節を派遣した理由は何か
第4章 ハツクニシラス・ヤマトタケル・日高見国
1 神武天皇のほかに崇神天皇も、ハツクニシラススメラミコト(御肇国天皇)と称された のはいかなる訳か
2 ヤマトタケルの出自はどうなっているか
3 ヤマトタケルが東国遠征で歩んだところから三角縁神獣鏡という銅鏡が出土している ということだが、これはどのように考えられるか
4『古事記』と『日本書紀』とでは、ヤマトタケルのたどったルートが異なっているよう に思われる。どちらに信をおくことができると考えるか
5『日本書紀』に記載されているヤマトタケルが東国遠征でたどった道は、広範囲に亘り かつジグザグで不自然な感じがする。なぜこのような道順をたどったのか
6 崇神天皇時代に東海道に派遣された建沼河別命とヤマトタケルが混同されているおそ れはないか
7 ヤマトタケルが攻めた日高見国とはいかなる意味の国で、どこに存在したのか
 『魏志倭人伝の世紀』 『魏志倭人伝の世紀』
──日本古代史解明の手引Ⅲ──
荒井登志夫 著
A5判/64頁 定価840円(税込)
三世紀前半ころの我が国の国情を描いた詳細な記録が残されている。『魏志倭人伝』である。そもそも、この文献が存在しなかったならば、邪馬台国も女王卑弥呼も遣魏使難升米も人々は知るはずもなかったし、邪馬台国論争が起こりようはずもなかった。長い邪馬台国論争を経た今日、『魏志倭人伝』の有する意義はいずれにあるのであろうか。そしてまた、この文献に秘められた謎をどこまで解くことが可能となったのか、と改めて問うてみたい。
第1章『魏志倭人伝』の世界
1『魏志倭人伝』について概略説明されたい。また、編著者はどういう人であるか
2『魏志倭人伝』がまとめられるに至った経緯はどのようなものか
3 倭国との通交のころ、「魏国」はどういう状況にあったのか
4『魏志倭人伝』はどのような構成を採っているか。その構成の分析からなにか分 かることがあるか
5 陳寿が参照した『魏略』、『魏書』の執筆の基となった「原報告書」の作成者 はどのような人物か
ほか、2テーマ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
第2章 欠史八代と倭国大乱―女王卑弥呼誕生の背景―
1「欠史八代」と呼ばれる時代はいつに当たるのか。また、倭国大乱の真相とはど のようなものであったのか
2 倭国大乱はどのように開始されたと考えられるのか
3 吉備道征討が引き金となって、いかにして倭国大乱に発展したと考えられるのか
4 女王モモソヒメとその父母について概説されたい
5 欠史八代の大臣に共通する特徴は何か
ほか、2テーマ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
第3章 遣魏使たちの正体―『魏志倭人伝』の登場人物を追う―
1 女王卑弥呼を補佐して国を治めた「男弟」には誰が該当するか
2 遣魏使を挙げられたい。第一回遣魏使の大夫「難升米」には誰が該当するか
3 第一回遣魏使の副使「都市牛利」には誰が該当するか
4 第二回遣魏使及び第四回遣魏使を務めた「伊聲耆・掖邪狗」には誰が該当するか
5 第三回遣魏使の「載斯烏越」には誰が該当するか
6 卑弥呼の部屋に入室し、飲食を給し辞を伝えた男子とは誰か
ほか、2テーマ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
第4章「鉄の時代」へ―魏国との通交目的とは―
1 魏国との通交が可能及び必要となった要因を挙げると、どういうことになるか
2 倭国から魏国に提供した貢物は、景初二年の第一回の遣魏使派遣のときは少な かったのに対し、正始四年及び正始九年ころの遣魏使のときは大幅に増えている
何ゆえ最初から多くの貢物を用意しなかったのか
3 葦原中つ国が魏国に使節を派遣した具体的な目的は何であったのか
4 魏国との通交で葦原中つ国に伝えられた軍事技術としては、
どのようなものがあったと考えられるのか
5 前期古墳から出土する鉄製の武器・武具類などをもって、
何ゆえ魏国との通交によりもたらされたと断定できるのか
ほか、2テーマ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
表1 倭奴国と倭面土国の遣使と倭国大乱 表4 遣魏使の比定結果
表2 古代の大臣等発令者一覧 表5 鉄器類が出土した前期古墳の例
表3 遣魏使及び魏使一覧 表6 巻向型前方後円墳の副葬品
 『前方後円墳の世紀』 『前方後円墳の世紀』
──日本古代史解明の手引Ⅱ──
荒井登志夫 著
A5判/64頁 定価840円(税込)
『葦原中つ国の世紀』(平成17年4月・歴研)に続く「日本古代史解明の手引」の続編。畿内などに残る巨大な前方後円墳はわが国の貴重な文化遺産であり、まとめて世界遺産に登録されて然るべきところであろう。しかし、この巨大な古墳の築造については、いくつもの謎が残っている。著者は、『日本書紀』などの文献をフルに活用し、さまざまな大きさに造られている前方後円墳の規格の決定要因と築造の方法について、前方後円墳は個々の被葬者の「享年(行年)」が反映されている可能性が高いと指摘。さらに、巨大な前方後円墳が継続して築造可能となったわけは農閑期における人民の総動員であったことを解明している。
第一章 前方後円墳の形成
―――――――――――――――――――――――――――
1 前方後円墳とはそもそも何か、についてまず説明されたい
2 前方後円墳が造られ始めたころ、葦原中つ国の葬儀はどの ように行われていたと考えられるのか
3 巨大な前方後円墳が全国的に築造されて行くことが可能と なった理由は何か
4 前方後円墳の築造を行った人々は奴隷のような立場の人か、 それとも一般の人民であったのかまた、卑弥呼=モモソヒ メの造墓は、生前あるいは死後いずれとみるべきか
5 前方後円墳の築造はどのような時期に行われたのか
6『日本書紀』には農業用ため池の造成が記されているが、 それはどのような時期に行われたのか
7 前方後円墳の築造に人民が協力したわけはどこにあるのか
ほか、5テーマ
―――――――――――――――――――――――――――
第二章 遺物・三角縁神獣鏡
―――――――――――――――――――――――――――
1 三角縁神獣鏡の出土状況について説明されたい。また、三角 縁神獣鏡以外に前期古墳に副葬されていた銅鏡はないのか
2 銅鏡、とりわけ三角縁神獣鏡を前方後円墳の被葬者が副葬 されている意義について説明されたい
3 三角縁神獣鏡の配付者の意図及びその受領者の得た利点は どういうところにあったと見るべきか
ほか、1テーマ
―――――――――――――――――――――――――――
第三章 古代歌謡に隠された思い
―――――――――――――――――――――――――――
1 モモソヒメの時代、我が国には文字がなかったはずである が、どのようにして前方後円墳の築造を可能とし、また、 地方との連絡を行っていたと考えているか
2『崇神紀』の中には、大神神社創始のころ同神社に崇神天皇 が出かけた際の歌が掲載されている。この歌の意味すると ころは何か ほか、2テーマ
―――――――――――――――――――――――――――
第四章 巨大な神籠石と磐井
―――――――――――――――――――――――――――
1 福岡県八女市の岩戸山古墳について概説した上、被葬者と される磐井について説明して欲しい
2 北部九州などに所在しているいくつかの神籠石には何らか の特徴が見られるのか
3 北部九州などに見られる神籠石の築造目的及び用途につい て説明されたい ほか、1テーマ
―――――――――――――――――――――――――――
表1 古代天皇の埋葬までの期間と埋葬月
表2 崇神紀、垂仁紀及び景行紀に見えるため池の造成
表3 6通りの享年反映原則が適合する陵墓
表4 椿井大塚山古墳及び黒塚古墳の概要
表5 北部九州の神籠石
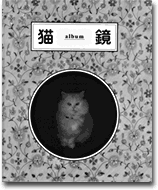 『album猫鏡』 『album猫鏡』
愛猫の自然な姿を写した、こころなごむ写真集
写真・文 松尾洋子
判型=252㍉×214㍉
46ページ
定価1,500円+税
ニコの銀色の目に映っているものはなぁに
ニコの小さなピンク色のお鼻に届くもものはなぁに
ニコのお耳に聞こえる音はなぁに
ニコが小さな手でじゃれているものはなぁに
ニコが大先輩のモコが大好きなのはなぁぜ
ニコが好きなのはどんな人
ニコはどんな夢をみているのかしら
──彼女は自分の姿を鏡に映してみる──
ニコ(♀・血統書つきのペルシャ猫)と、
モコ(♂・雑種)の2匹が描き出す
猫たちの世界、
そして猫の視線の先に見える人の世界──
|
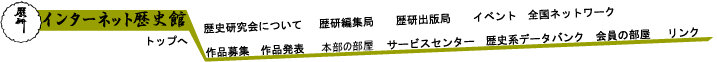
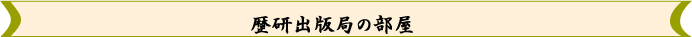
 『海からみた卑弥呼女王の時代』
『海からみた卑弥呼女王の時代』 歴研ブックレット
歴研ブックレット
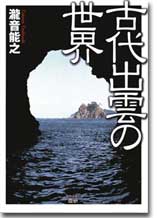 『古代出雲の世界』
『古代出雲の世界』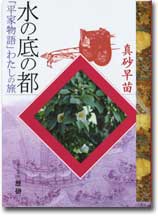 『水の底の都』
『水の底の都』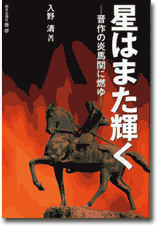
 『対馬・壱岐史を追う』
『対馬・壱岐史を追う』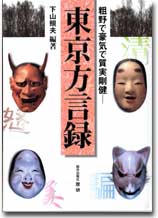 『東京方言録』
『東京方言録』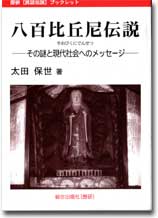 『八百比丘尼伝説』
『八百比丘尼伝説』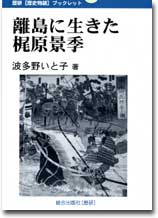 『離島に生きた梶原景季』
『離島に生きた梶原景季』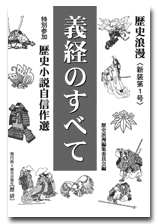 『義経のすべて』
『義経のすべて』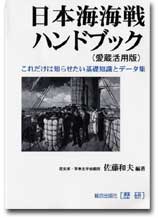 『日本海海戦 ハンドブック〈愛蔵活用版〉』
『日本海海戦 ハンドブック〈愛蔵活用版〉』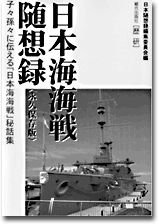
 150年の時をへて蘇る
150年の時をへて蘇る 『葦原中つ国の世紀』
『葦原中つ国の世紀』 『魏志倭人伝の世紀』
『魏志倭人伝の世紀』 『前方後円墳の世紀』
『前方後円墳の世紀』