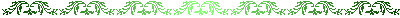■ 線上の雫 ■
窓の外は、目の眩むような白光。
「暑い…。」
思考も何も追いつかぬままに口をついた唸るような呟きに眉を顰め、クラウスは最後の書類に走らせていたペンを置
いた。あとは上司のチェックを入れるだけ。じっと座っていることすら何だか苦痛に感じられてきて、紙束を揃えながら
立ち上がると、部屋の椅子の上でこれまたのびている、という形容がふさわしい父親の視線とぶつかった。
この部屋に他に誰がいるという訳でもないのだが、先程の思わず漏れた台詞はクラウスにとってかなりの不覚だっ
た。未だ自分を律することすらできぬのかと苛立たしささえ覚え、彼はひとつ頭を振る。どうやらこの猛烈な暑さのため
か、攻撃的になっているらしい。
「……父上、何か冷たいものでもお持ちしましょうか。」
「ん?ああ…いやいい、自分で行こう。」
その前に、風呂にでも行くかな、と軍を率いるいつもの姿からは想像も出来ない覇気のなさで返し、キバはくつろげた
襟元をぱたぱたと扇ぐ。しかし暑いな、と恨めしそうな父の声を背中に、クラウスは窓の外をちらりと見上げた。大分と
傾きつつある太陽は、それでもまだまだ元気だ。湖のほとりに建つこの城はただでさえ湿度が高くなりがちではあるの
だが、それにしてもこの湿気はただごとではない。
「父上、もう少しのご辛抱ですよ。もうすぐ夕立になります。」
天候も読めないようでは軍師としてやっていけない。クラウスの言葉にキバはそうか、と頷き腰を上げた。湯気の中を
泳いでいるかのようなその姿に、クラウスは苦笑する。
「あまり長居はされませんよう。」
「…分かっておる。」
きっちりと釘を刺す息子に片手を上げて、キバは襟元を直すと部屋を後にする。レオナの所で誰かに捕まると、それ
こそ帰ってなどこなくなることをクラウスは良く知っていた。風呂にゆったりと入って汗を流し、気分良く上がる頃には陽
も落ちて酒場もさぞかし賑わっていることだろう。
父の背中を見送って、クラウスは溜息をつく。別に酒を飲むなと言っている訳ではない。父親のささやかな楽しみを奪
うなど、気の毒に過ぎるというものだ。ただ、量が問題なだけであって。
「さて、と。」
ひとつ声をかけて気持ちを切り替える。額にかかる前髪がうっとおしい。最近忙しさにかまけてほったらかしになって
いたから、この書類を届けた後で切りに行くのもいいかもしれない。それから図書館に寄って調べ物をして、その上で
キバを迎えに行くとちょうどいい時分だろう。
ざっと道程を頭に思い描く。最初の目的地である四階の部屋は、風のほとんど通らないここよりも少しは過ごしやすい
かもしれない、そんなことをぼんやりと考えながら、クラウスは自室の扉をくぐった。
「あ、クラウス!」
部屋を出た瞬間の、突然の大声。急激に現実に引き戻されてぱちぱちと瞬きをするクラウスに、ものすごい勢いで走
り寄ってきた…というか急ブレーキをかけて立ち止まったのは、トラン共和国大統領のご子息殿だった。その手には彼
には非常に似合わない、銀盆とグラスがふたつ。しかも片方は空のように見える。
「シーナ殿、どうなさったのですかそんなに慌てて。」
「何か涼しそうだよな〜、クラウスって。」
会話が全く噛み合っていない。何で何で?と覗き込んでくるシーナにクラウスは苦笑する。むしろ不思議なのはあんな
にすごい速度で走ってきたのに一滴も中身を零していない彼の方であるのだが。
「暑いですよ。」
「だってあんまり汗かいてないじゃん。ひょっとして、平熱とか低いクチ?」
「…まあ、そうですけど…。」
「あ、それであんまり水分摂らないだろ?」
そう言われればそうかもしれない、畳み掛けてくる質問にクラウスは頷く。仕事中などは没頭するあまりに食事も忘れ
るくらいであるからして。
「それはよくない!!」
突然の大声に、気持ちクラウスはのけぞった。シーナが一歩、ずずいと近付く。
「だから、これ飲みな、ほら。」
言葉と共に押し付けられる銀盆。ひやりとした温度が手に心地良い。
「はあ…。」
「俺からのプレゼント。ほら、嬉しいだろ?」
そんな台詞と共に様になったウインクを投げ、じゃあな、と身を返しかけたシーナの動きが不意に止まった。
「シーナ!」
同じく大慌てで走ってきたのは、同僚の副軍師の少女だった。あまりの勢いに少しずれた眼鏡を彼女は片手で直
す。
「あなたは、もう!何するのよ!!」
「ちょうどいい所にアップル。行こうぜ。」
「何言ってるのよ!返してお盆。どこやったの?!」
上機嫌のシーナに取られた腕を振りほどいたアップルは、半ば呆然と様相を見守るクラウスの持つ銀盆に駆け寄っ
た。
「あー!ちょっと、シーナあなた、飲んだわね?!飲んだでしょ!!」
「うん、美味しかった。」
「当然よ!私が!シュウ兄さんのために!!淹れたのに!!!」
「もういいじゃんそんなの。な、アップル、今日暇な連中が花火大会やるんだって。行こうぜ。」
「どうせ今から雨よ!」
「夕立だろ?すぐ止むって。ほら。」
「ちょっと、離してよ馬鹿!」
「じゃあクラウス、またな。」
再度腕を取って、ずるずるとアップルを引き摺りながらシーナが手を振る。階段をアップルの悲鳴が反響しつつ下って
ゆくのが、動けないでいるクラウスの耳に長く尾を引いた。
「…ええと。」
静けさを取り戻した廊下で、クラウスは手の中のものを改めて見下ろす。空のグラスがひとつ。それから、汗をかきつ
つあるグラスがもうひとつ。
涼やかなミントの香りが鼻腔をくすぐり、クラウスの笑みを誘う。憧れの兄弟子とのティータイムは思わぬ妨害にあっ
てしまったという訳か。これは目的の半分なりとも、せめて遂げさせねばなるまい。書類を落とさないように抱えなおし
て、クラウスは階段へと足をかけた。
+++
「失礼します。」
いつものとおりに声をかけて四階の部屋に足を踏み入れたクラウスは、零さないように注意していたグラスから上げ
た瞳を瞬かせた。
「シュウ殿?」
滅多に部屋から出ない正軍師殿の、これまた滅多に動く事のない机の前、根でも生えているのではと疑いたくなる定
位置の椅子は、極めて珍しい事に空だった。
カーテンが僅かに揺れて、さらりと音をたてる。今日は確か用事はなかったはずだが。
早くしないと氷が溶けてしまう、と周囲に走らせた視線の先、奥の部屋への入り口が僅かに開いていることに気付い
て彼は眉を寄せた。書類だけなら黙って置いて行くのだが。しばしの逡巡の後、グラスを手にクラウスはそっと扉を押し
開ける。
開け放たれた窓、椅子の背に無造作に掛けられた上着。どうやら部屋の主は仮眠中であるらしかった。
こんなおかしな時間に寝るなど、一体どうなっているのか。知らず溜息が漏れる。大方昨日も寝ていないのだろう。軍
主殿が交易に夢中でほぼ休戦状態といってもいい今、そんなにせっぱつまった仕事がある訳でもないのだが、絶対的
に不足気味の文官の負担はどうしても大きくなってしまうのが現実だった。
覗き込んだ寝台の上で横になって目蓋を閉じる上司と手にしたグラスを見比べて、クラウスはどうしたものか、と前髪
をかき上げた。大体、こんなまだ陽も出ている自分に、こんな風に眠っていることなんて滅多にない、というか初めてで
あるのに、何故わざわざこんな日に、とこんな尽くしの状況に憎らしささえ覚えてくる。
それもこれも皆この気候のせいだ、などと八つ当たりも百も承知で、クラウスは窓の外に視線を移した。早く雨が降れ
ば少しは涼しくもなろうに。グラスの壁面を滑る雫が指を濡らす。それに追い立てられるようにもう一度窺った顔は、仮
面のように微動だにしない。
兄さんが眠っている所って、見たことがないの。
少し寂しそうにそう呟いた少女。そして、ひょっとしたらほんとに寝てないのかも、と冗談っぽく笑って見せたその顔を、
ふとクラウスは思い出した。それから、嵐のように通り過ぎていった先程の、たくさんの表情。
彼女があんなことを言ったのは、一体いつだったか。同じ副軍師という役職に就いているうえで、同じ時間を過ごす機
会もしばしばあったが、そんな風に仕事以外の話をすることはほとんどなかったような気がする。
年齢の割に落ち着いているとはいうものの、クラウスの眼に少女の姿はとても眩しく映る。
そして安堵するのだ。彼女はまだ大丈夫。
グラスの中の液面がゆらり、と波立った。同時に少女の大切な人の影も揺れる。
鼻でもつまんでやろうか。物騒な考えがちらりと頭を走った。
「俺の寝顔がそんなに珍しいか?」
「…っ!」
突然にかかった低い声に危うく手を滑らせそうになって、クラウスは慌ててグラスを持ち直す。
声の主は眼下で唇を吊り上げ、半身をゆっくりと起こす男。
「…別にそんなことはありませんよ。」
「そうだろうな。」
「………一体いつから起きていらしたのです。」
「さあ?」
やはり鼻と言わず首でも締めてやれば良かったか。いや、あのまま手を滑らせて差し上げるべきだったかもしれな
い。ゆっくりと眼を細めたクラウスの視線の先で、シュウは顎を上げる。
「で?」
「書類を届けに。それから、アップルさんがこれを。」
「何だ、珍しくもお前の手土産かと思った。」
「…いつも手ぶらで申し訳ございません。」
直接渡すと寝台の上に雫が落ちそうで、結局クラウスはサイドボードにグラスを乗せる。から、という涼しげな音に氷
が辛うじて生き残っているようで、ほっと息をついたその瞬間。
不意に大きな手が伸びてきて、差し出したままだった手首を掴んだかと思うと勢い良く引き寄せた。突然のことに体の
平衡を崩したクラウスはそのまま寝台に倒れこむ。
「シュウ殿?!」
半ば押さえ込まれるような体勢に、抗議の声が上がる。しかし非難の対象である男はまったくもって涼しい顔だった。
「この暑い中やめて下さい!」
「…嫌だ。」
「仕事はどうされるんですか!」
「お前がやったんだったら確認はいらんだろう。」
さらりと言い放たれてクラウスは一瞬言葉を失う。つ、と冷たい黒髪が頬を撫でた。
「…シュウ殿だって暑いでしょう?!」
「暑い。」
「だったら!」
見上げた先で、闇色の瞳に一瞬影が走ったような気がした。
知っている。その深淵を、底の無い闇を、自分も幾度となく覗き込んでいるから。
そして、表面にはけして出さないけれども、彼女にそれを知らないままでいて欲しいと彼が願っていることも。
「どうせすぐに雨が来る。」
そのまま抱き寄せられて、息が詰まる。
「………最近、暑くてあまり寝ていないんだ。」
付き合え、という耳元での囁きはどこか遠く。クラウスは緩々と息を吐く。
自ら望んで近付いた淵、そう在りたいと願った姿。選んだ道を後悔などはしていないけれど。
それでも彼の底のない瞳に、そこに映る自分の姿に、痛ましいものを感じざるを得ないのだ。そしてそれは同時に、
疎ましくもあり、いたわしくもあり、忌々しくさえあり…それから。
そんなことを考えること自体が、今まで手にかけてきた数え切れない人間達を貶める行為、そのものであるというの
に。
そうして彼はそっと睫毛を伏せる。
「…人を安眠枕の代わりにするのはやめて下さい。」
シュウが微かに笑ったのが、伝わってくる振動で分かった。
彼女達は、無事に花火ができるのだろうか。窓に手を伸ばしながら、クラウスはそんなことをぼんやりと思う。
閉まった硝子に、大きな雨粒がぽつり、と当たった。
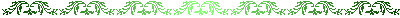
今更言うまでもないことですが、緑月様は何てステキな小説を書かれるのでしょうか。
シーナとアップルの生き生きした会話に引き込まれ、シュウとクラウスのお互いの出方を
窺っているような妖しい会話に溜息が出てしまいます。
この小説のお陰でウチのサイトに来た方も無駄足を踏まずにすんだことでしょう。
ああ、何て他人まかせな私。