メイドアタック
※メイドアタック※
東京魔人学園外法帖に登場する敵モンスター「メイド」(幕末なのに何故?/笑)が繰り出す技の一つ。
序盤の敵の中では結構強力。
同様の技に「ご主人様、お茶の時間です」というのがある。
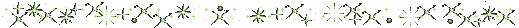
「あー、ホワイトデーか。めんどくせぇな」
「文句言わないの。公式サイトにメッセージ入れればいいじゃん、って提案したの自分だろ」
あっさりとカミューに切り替えされてシードは唸った。
『確かにあの時はそれが一番楽な方法だと思ったんだけどさ』
シードだってチョコレートは嫌いじゃない。けれど程々の量という物があるだろう。先月のバレンタインデー以降、シー
ドはチョコが少し嫌いになりつつあった。
なにしろファンから事務所に送られてきたチョコレートの数たるや凄い物で、最初は「私たちにも分けて下さいね」なん
て言って喜んでいた事務所のスタッフの女の子達が「これ、捨てたらダメですかね」と言いだしたくらいなのだ。
もちろん、捨てたりはしなかったが、本当に問題だったのは「ホワイトデーはどうするんですか」とクラウスが言いだし
た時だった。
ファンの子がお返しなんて期待しているはずもないのだから、どうするもこうするもないだろうとシードは思っていたの
だが、律儀者のマイクロトフが「やはりしないとまずいだろう」なんて言いだしたので慌てたのだ。マイクの言うことを黙っ
て聞いていたら一人一人に返事を書くなんて言い出しかねない。だからサイトにメッセージを入れようって言ったのだ。
だけど…。
「俺はイラストも描かなきゃいけないんだよ」
「しょうがないだろう。それも自分で言いだしたんだから」
つい勢いで余計なことを言って自分で自分の首を絞めてしまったのだ。
カミューに「ほら」とスケッチブックを手渡されて諦めたのか、シードは色鉛筆を取り出した。
カミューは思わず微笑んでしまった。
「どうせ、似合わねーとか思ってンだろ。俺は水彩とかも好きなんだよ」
「何も言ってないだろ」
ふん、とシードはいじけたように背中を向けて絵を描き始めたのでカミューは苦笑して自分のメッセージをパソコンに
打ちこみはじめた。
「俺が最後?」
しばらくしてシードが声をかけてきた。
「いや、あとクラウスが残ってる。今日大学の帰りによるって言ってたから…へえ、上手いもんだね」
シードが得意そうにスケッチブックを掲げていた。
「もっとメカニックな絵を描くのかと思ってた」
「そういうのも好きだけどさ、女の子向けだとこんな感じかなって」
画用紙の中で花が咲きこぼれている。
「でもシードのファンって男の子も多いんだから、特に女の子におもねらなくても」
「ホワイトデーだろ」
「あ、そうだった」
珍しくカミューがボケをかまして思わず二人で笑っていると、クラウスがバタバタと駆け込んできた。
「遅くなってすみませんっ」
両手に抱えていた荷物を近くのデスクの上に置くとパソコンの前にすっ飛んできた。
「そんなに慌てなくても大丈夫だよ。明日アップできれば良いんだから」
「はい」
答えながらカタカタと打ち始めた。それを後ろから後ろから覗き込んでシードが口元を綻ばせた。
「おっ、クラウスちゃん、可愛いこと書いてるじゃないか」
「もうっ、見ないでください」
「いいじゃん、明日になったら日本中の女の子が見るんだから」
「ダメですってば。シードすぐちゃかすんだから」
クラウスには迷惑かもしれないが、こうやって一々ちょっかいを出してからかうのもシードなりの愛情表現である。
「どうしたんだ、この荷物」
マイクロトフの声に振り返るとマイクとシュウが戻ってきたところだった。
「あ、散らかしちゃってごめんなさい」
「いや、別に良いんだが…。これ、お菓子か?」
「はい。ホワイトデーの、大学の友達に返す分なんです」
「随分貰ったんだね。これだけあると大変だろう」
カミューが感心するのも道理で、大きな紙袋二つ分もある。
「大学の友達に手渡しされると断れなくて、後で数えたら凄いことになってたんです。みんな気を遣って義理でくれるんで
すよね」
いや、そうじゃないだろうと全員が思ったが、取り合えず突っ込む人間はいなかった。
「でも大学ってそろそろ休みなんじゃないの」
「ホワイトデーのパーティをやろうってことになって、そこに多分みんな来るからまとめて返すんです」
「主催はシーナか?」
「はい」
だろうな、とシュウが呟いた。
「だけど、そうなると来年からが大変だよね」
「来年ですか?」
カミューの心配そうな声にクラウスは首を傾げている。
「だって確実に本人からお返しがもらえるって事をファンが聞きつけたら、来年からみんな大学の前で待ってるかもしれ
ないよ」
「あ…」
カミューに指摘されてクラウスは初めて気付いたようだった。
「でも今まで渡してたのに今年からお返ししないのも変ですよね」
「だな。『クラウスったら芸能人になったらお高くとまっちゃってお返しもくれないの』って陰口叩かれるかもな」
「でも高校からの友達にだけ返すのは、他の女の子にもっと失礼ですよね」
シードは半分からかっているのだがクラウスは真剣だった。
「そうだっ」
何故か一緒になって考え込んでいたマイクロトフが手を叩いた。
「いっそのこと来年のバレンタインデーには大学に行かなければいいんだ」
「あ、そうですねっ」
うん、と顔を見合わせる二人に残りの三人は吹き出してしまった。
「な、何だ。カミュー、俺はそんなに妙なことを言ったか?それともやっぱり敵に後ろを見せるようなやり方は不誠実だろ
うか」
カミューは何も言えずに笑い転げている。
「敵に後ろを見せるのが不誠実って、なんだよ。それは」
「ファンが敵か」
シードとシュウに突っ込まれてマイクロトフはしどろもどろだ。
「とにかく、来年からバレンタインデーには仕事を入れるようにクルガンに言っておかないとね」
カミューがクスクスと笑いながら助け船を出した。
「てことで、これは明日女の子達に渡してやりな」
そう言いながらシードが紙袋の中を覗き込んでいる。
「おっ、これ、本命の子か?」
確かに一つだけ、明らかにお菓子とは違う綺麗にラッピングされた箱があった。
「あ、それはメイドさんにあげるパシュミナなんです」
「なにっ、メイド?」
そう、クラウスの家にはメイドがいる。お手伝いさんでもなく家政婦さんでもない、正真正銘のメイドだ。それを初めて
知った時、どんなに驚いたことか。
シードにとってメイドなんて別世界の生き物だった。海外ミステリーとかゴシックホラーとかエロゲーとか、とにかくそん
なところにしか生息しないと思っていたのに、ごく身近な日常生活の中に潜んでいたのである。
「メイドかあ。メイドと言えば、禁断の聖地だよな」
「は?」
クラウスを無視してシードは続けた。
「なーんかロマンを感じるんだよな。ドリームっていうか未知との遭遇っていうか…そう思わない?」
同意を求めてぐるりと見回したがシードが期待したような反応は返ってこなかった。
マイクロトフはウームと腕組みをしているし、シュウはつまらなそうに手元の本をパラパラとめくっている。カミューにい
たっては先ほどからの笑いのツボにはまっているのか俯いた肩が震えていた。そして『こいつは最初から期待してなか
ったけど』と思いながら見たクラウスは案の定キョトンとした顔をしていた。
「ああもう、どうしてお前らってそう品行方正ぶってるのかなあ。もっと本能に忠実になれよ」
「だって急に目を輝かせて何を言い出すかと思ったら」
ようやく笑いを納めたカミューが睫にたまった涙を指先で弾いた。
「クルガンが聞いたらなんて言うかと思って」
そう言ってまたクツクツと笑う。
「うっ、それは…それとこれとは問題が違うだろうがっ」
こんな所でクルガンの名前を出さなくてもいいじゃないかっとシードはカミューを睨みつけた。
「別に俺がメイドとどうこうしたいって話じゃないんだよ。ただ、一般的な男全般の傾向として、メイドは特別な存在だろっ
て言ってるの。お前らだって興味あるだろっ。もう、クルガンに余計なこと言うなよ」
「何でクルガンに言ったらいけないんですか?」
「何でもいいからダメなのっ」
クラウスは理由が分からないままシードの勢いに押されて頷いた。
このメンバーの中でクラウスだけがシードとクルガンの仲を知らない、と言うか気付いていない。色恋沙汰には滅法疎
いのだ。
だから日常生活にメイドがいても平気なんだろうな、とシードは思っていた。普通、健全な男子ならメイドがいる生活で
何もおこらない方がおかしいじゃないかと、これもちょっとばかり偏った考えが頭の中にあったのだ。
『でもまあ、こいつはある意味普通じゃないし』
結構酷いことを考えているシードである。
「それよりホワイトデーにお返しをあげるっていうことはバレンタインにメイドさんからチョコレートを貰ったのか?」
「はい」
クラウスは嬉しそうに答えた。
「お前、もしかしてそのメイドのこと、好きなんだ」
「はいっ」
これまた即答だった。シードは嬉しくなっていた。
何と言ってもシュウの表情が微妙に変わったのがシード的には楽しい。
「今まではバレンタインのお返しって私がケーキを作ってたんですけど、デュナンになってちょっと自由になるお金も出
来たでしょう?」
少し赤くなって話すクラウスは可愛い。さしずめ、初月給でプレゼント、みたいな感覚なのだろう。
「で、そのケーキを二人で仲良く食べる訳ね」
「父と三人で食べるんです。今年はパーティがあるけど、その時間には間に合うように帰らないと」
あー、だからクラウスには彼女も彼氏もいないのだろうと、何となくみんな納得していた。
「親父さんも一緒って事は、親父さんにもチョコくれるんだ」
「当たり前じゃないですか」
だよなあ、ご主人様とメイドの関係ったら基本中の基本だもんな、とシードは心の中で呟いた。
シードの名誉のために言っておくが、決してシードが好んでその手のゲームをやっているわけではない。シードは2次
元の絵空事より3次元の実践を好む方だ。ついでに言うとその相手は常にクルガンだったりする。けれど友達がやって
るゲーム画面等を覗き込んでかなり洗脳されているらしいのは明らかだった。(おい)
「お前はメイドさんが好きなんだよな。…親父さんはどう思ってるんだ?」
「父ですか。やっぱり好きだと思います。そうでなければ長くいてもらうはずないし」
「へー、結構長いんだ、そのメイドさん」
「はい」
「ていうことは、年上のメイドさんなんだ」
クラウスはニッコリ頷いた。
そうかあ、ご主人様とメイドの関係っていうのもありだけど、年上のメイドに憧れる純情なお坊ちゃまっていうのもなか
なか…。
「何をニヤニヤしてるんだ」
突然、後ろからクルガンの声がしてシードは慌ててしまった。いつから聞いていたのかクルガンが苦笑している。
「違うって、俺は別に何も…」
「メイドがそんなに好きだとは知らなかったな」
怒ってるわけではないらしいが嫉妬されてるわけでもないというのがちょっと寂しいシードである。
「しょうがないだろ、俺は庶民の出なんだから。メイドなんて見たことないんだよ」
「そうなんですか?」
クラウスが目を丸くして聞いてきた。全くこいつはもう、とシードも苦笑してしまった。
「だからメイドって憧れるんだよ。そもそもあのコスチュームが日常性からかけ離れてるだろ。頭に白い小さな帽子みた
いの乗っけて、フリフリのレースがついててふわっとしたスカートでさあ。色が紺っていうのがまたストイックな雰囲気を
醸し出しているっていうか」
「そんな服、着てませんよ」
これにはクルガンを除く全員が「えっ」と声を上げた。何だかんだ言いながら、やっぱり男はメイドに夢を見ているらし
い…。
「クルガンは会ってるから知ってますよね」
「そうだったな」
クルガンが頷いたのを見てシードが断然抗議した。
「着てないのかよ。着せなきゃダメじゃないか、メイド服」
「…でも、多分嫌がると思うし」
「そういう問題じゃないだろう。そこはちゃんとご主人様の権限で」
クラウスはウーンと考え込んでいる。
「…でも、あんまり似合わないと…」
「おまえはっ」
シードはクラウスの頭をパコッと叩いた。
「メイドさんに失礼だろっ、そんなこと言ったら」
「……ごめんなさい」
クラウスは両手でシードに叩かれたところを押さえて謝りながらも、釈然としない顔をしていた。
「で、お前んとこのメイドさんは一体どんな服着てるんだよ」
「私服だから普通の服です。赤いスカートとか。あ、赤が好きみたいで外出する時はつばの広い赤い帽子を被ってるん
ですよ。とってもおしゃれなんです」
かなり派手なメイドさんらしい。
「そうかあ、やっぱり本物は小説とかゲームとは違うんだな」
シードが感心したように呟くとクラウスはコクコクと頷いている。
「シード君、他に質問は?」
カミューはもう完全に面白がっているらしい。
「質問って…そうだ、メイドさんってどんな料理を作るんだ?やっぱり毎日フルコースとか作るのか?」
「まさか」
「でも洋食なんだろう?」
マイクロトフが口を挟んだ。普段は大抵聞き役なのに食べ物の話になると混ざってくるのが可笑しい。
「いえ、和食が多いです。煮物とか酢の物とか凄く美味しいですよ」
「煮物…」
「ええ、父が肉料理が好きだからなるべくお野菜をとりやすいようにって考えてくれてるんです」
「ああ、そういうことか」
夢をぶち壊されないですんでシードは少しホッとした。
「クラウスの好物も作ってくれるんだろう」
「…中華は苦手みたいであまり」
そりゃあ、メイドさんが中華を作るってのはあんまり絵にならないよな、とシードは深く納得していた。
「クラウスは中華が好きなのか。俺と同じだな」
「え、本当ですか」
「今度一緒に食いに行くか?」
シュウに誘われてクラウスは嬉しそうだ。
「メイドさんってやっぱり『ご主人様、お茶の時間です』とか言うのか?」
何となく二人がいい雰囲気になりそうだったので、極力それを阻止すべくシードは強引にメイドに話を戻した。
別にシュウに恨みがあるわけではない。ただ、シードにとっては人間的にもベーシストとしてもクルガンが世界で一番
だと思っているのに、当のクルガンが自分以上だとシュウを評価しているのが悔しいのだ。だから何となく気がつくとい
つもシュウに突っかかってしまう。ついでにクラウスとのことでチャチャを入れると、シュウが微妙に反応するのでそれを
見るのが楽しいのである。(怖いもの知らずめ、とよくクルガンに注意されていた)
そんなシードの思惑も知らないでクラウスはあっさりとシードに向き直った。もちろん、シュウは忌々しそうにシードをチ
ラリと見ていた。
「ご主人様じゃなくて旦那様ですけど。よく3人でお茶するんです」
「へぇ、本当に仲良しなんだな」
感心したようにマイクロトフが言うと、クラウスは嬉しそうに頷いた。
「ええ、ずっと一緒だったし大好きなんです。それにいろんな事を教えてくれるし」
そう言ってクラウスは何故かポッと赤くなった。
一瞬、微妙な空気が流れた。
ほぼ全員が、クラウスが年上でちょっと派手めの綺麗なメイドさんにあーんな事とかを教えられている図を想像して、
それを慌てて打ち消したようだった。
「お前に限ってそれはないよな。まだ全然お子様だし」
シードの呟きに反発したのは当のクラウスだった。
「もう、シードったらすぐ私を子供扱いして。私だってもう大人なんですから知ってることだってたくさん…」
「分かった。分かったから皆まで言うなっ」
クラウスが自分の体験談を話し出すんじゃないかと慌ててシードが止めに入った。
「つまり、メイドさんはお前がちゃんと大人になれるように教育してくれてるって事?」
「はいっ」
元気な答えにシードの方がたじろいだ。
「相変わらず分かってるのか分かってないのか分からないヤツだが。でも良かったな、クラウス。実は俺、お前のこと心
配してたんだぞ」
「だから私はシードが考えてるほど子供じゃありません」
「そうか、そうだよな。お前だって19だもんな。しかし、お前をその気にさせるなんて凄い偉大なメイドさんに思えてきた
ぞ」
「とってもステキな人なんですよ」
「ふーん、会ってみたいな」
するとクラウスはパッと顔を輝かせた。
「よろしかったら、これからうちにいらっしゃいませんか?今日は父も家にいますし、一度みんなにきちんとご挨拶したい
って言ってたんです。ご挨拶するのにわざわざ来て貰うのは申し訳ないですけど、でもちょうど良い機会だし」
もちろんシードに断る理由なんてあろう筈もなかった。
「シードったらそんなに張り切らなくても」
カミューが苦笑している。
「まーたまた、気持ちは俺と一緒のくせに。お前らだってメイドさんに興味あるから来たんだろ」
確かに車内が妙に浮かれた雰囲気になっていたのはシードのせいばかりではなかった。一番舞い上がっているのは
クラウスかもしれない。みんなを家に呼べるのが嬉しくて仕方がないらしい。
「シュウ。お前も楽しみだろ、クラウスが大好きなメイドさんに会えるんだぞ」
そうじゃなくても機嫌が悪そうなのに、敢えて猫に鈴を付けるというか火に油を注ぐというか藪を突っつくような真似を
してみるシードである。
「お前もメイドに礼儀を教えて貰ったらどうだ」
らしくもなくシュウが挑発に乗ったのは、やっぱりかなりイライラしているからかもしれない。
「俺は礼儀よりも別のこと教えて貰いたいなあ」
やっぱりシードも大分浮かれてるかもしれない。
「大丈夫ですよ。とっても優しく教えてくれるから」
やっぱりクラウスの言うことは核心をついているのかピントがずれているのか誰にも分からない。
そんなこんなでクラウスのマンションに着いた時にはシードの胸は訳の解らない期待で一杯に膨らんでいた。。
クラウスの住んでいるマンションは聞きしにまさる豪華さだった。普通なら口をあんぐり開けて見てしまいそうだったの
だが(事実マイクとカミューはそれに近い状態だった)シードには別の大いなる目的があるから、そんなことで驚いてい
る場合ではなかった。
「ご足労をおかけして申し訳ありませんな」
にこやかにシード達を出迎えたのはメイドさんではなくてクラウスの父親、キバだった。さすがに超一流企業の重役を
務めているだけあって貫禄十分だが、暖かみのある笑顔が人柄を表していた。(か、もしくはクラウスがいるんで目尻
が下がっていたのかもしれない)
キバに先導されてデュナンご一行様は一体どれくらい広いんだというリビングに通された。
「なあ、クルガン」
シードは囁いた。
「あれ、家系なのかな」
もちろん、キバの頭のことだ。
「せっかく綺麗な髪なのに、クラウスも可哀想に」
するとクルガンがクックッと笑った。
「バカ、何の心配をしている」
「だってさ」
「あれは剃っているんだそうだ。ユル・ブリンナーのファンらしい」
「誰だ?それ」
するとクラウスが振り向いてシーッと人差し指を唇に当てた。
「その話はしないで下さい。また母との馴れ初めを聞かされちゃう。話しだしたら止まらないからやめてくださいね」
「へー、お前がそんなこと言うなんて珍しいな」
「私はいいんですけど、シード、2時間もそんな昔話聞きたいですか」
「やだ」
クラウスが頷き「懸命な判断だ」とクルガンが呟いた。どうやらクルガンはクラウスをスカウトしに来たときに聞かされ
たらしい。
「どうかしたのか?」
「いいえ、なんでもありません、父上。みんな適当に座ってください。今、お茶をお持ちしますから」
クラウスがてきぱきと言った時、コンコンとドアをノックする音がしてガチャッと扉が開いた。
おお、ついにメイドさんの登場だな、とシードはガラにもなく緊張した。
「あ、タキさん。すみません」
クラウスが声をかけると「いいんですよ」と言って小さくて可愛いおばあさんが紅茶のセットが乗ったワゴンを押してき
た。
「何だ、お客に手伝わせてるのか?俺達が来ちゃって良かったのかな」
そうクルガンに囁いていると、小さなおばあさんはしずしずと頭を下げた。
「皆様、いらっしゃいませ。メイドのタキでございます」
「ひえっ?」
思わず奇声を上げてしまったシードの横でクルガンがぷっと吹きだした。
「大勢で押し掛けてすみません」
相変わらず如才ないカミューが挨拶を返したがすぐに俯いて肩を震わせていた。
「タキさん、シードがタキさんに会うのをとっても楽しみにしていたんだよ」
「まあ、こんなおばあちゃんに会うのを楽しみにしてくれるなんて嬉しいですよ」
「あのね、シードもいろんな事、教えて欲しいんだって」
「まあ、何を聞きたいのやら。猫が顔を洗ったとき?それとも長屋に住んでるシド坊やの事かしら。シドはね、すぐには
仲間にならないから取り合えず先に進めるといいですよ」
「………」
「ダメージ無限大ってところだな」
いきなり復活したシュウが低い声で呟いて、カミューは我慢できずに爆笑している。
「どうしたんですか、みんな」
不思議そうなクラウスをシードは呆然と見つめていた。
『そうだ、こいつに色っぽいことの一つでも期待した俺がバカだったんだ。だけど、まさか、ほんとに、ここまでお子様だ
なんて一体誰に想像できるんだ』
みんなが楽しくお茶を始めてからも、まだシードは茫然自失の態であったとかなかったとか…。
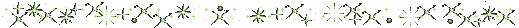
一応ホワイトデー企画のつもりなのですが
外法帖ネタですみません。
外法帖をやっている方は1割り増し、面白く感じるかも(ホントか?)
シードファンの方にはただただひたすら申し訳ないです。
頭が湧いてるのは海棠の方ですね。うぅ…
クスッとでも笑っていただけたら幸いです。
実はウィンダミア家のメイドはタキというのは最初っからの決定事項でした。
じゃないとクラウスの貞操が危険だから。(爆)
それから、2月3月って大学生は大学に行くんでしょうかね。
あんまり行ってなかった気がするんですが、遠い過去の話なので忘れてしまいました。
なので、その辺はあまり突っ込まないでくださいね。(^^ゞ
外法帖ネタですみません。
外法帖をやっている方は1割り増し、面白く感じるかも(ホントか?)
シードファンの方にはただただひたすら申し訳ないです。
頭が湧いてるのは海棠の方ですね。うぅ…
クスッとでも笑っていただけたら幸いです。
実はウィンダミア家のメイドはタキというのは最初っからの決定事項でした。
じゃないとクラウスの貞操が危険だから。(爆)
それから、2月3月って大学生は大学に行くんでしょうかね。
あんまり行ってなかった気がするんですが、遠い過去の話なので忘れてしまいました。
なので、その辺はあまり突っ込まないでくださいね。(^^ゞ
