A Grade Separation
|
+++ A Grade Separation +++ 目の回るような忙しさ。 戦の直後のあわただしいなか、何故か仕事が滞るのに苛立っていたシュウは、その理由を医務室からの報告に見 つけた。 クラウスが、大事ではないが怪我をしたらしい。治療のためにしばらく仕事に就けないということだった。 文官の面々が凍りつく。青年への心配もあるが、唯でさえ多い仕事量の増加を真っ先に憂えた。 医務室は重症の兵士であふれ返っていた。看護士や衛生兵、魔法兵がばたばたと走り回り、必死の治療が続けら れている。 皆に一言二言、声をかけながら、シュウは診察室の奥、ホウアンの寝室のドアを開けた。 文官の事務室に負けない程、本と書類で埋まった部屋の片隅に、簡素な机と、患者用の寝台がひとつ。 寝ているのはクラウスだった。 「シュウ殿っ!? …っつ」 シュウの突然の来訪に驚いた様子で体を起こそうとし、表情を歪ませる。 「いいから寝ていろ」 軍の幹部クラスを兵士と混ぜて寝かすのは、双方に与えられる心理的負担を考えると宜しくないというホウアンの指 示で、クラウスはこの部屋に移動させられた。 「すみません、ご迷惑を」 シュウはベッドに腰をかけ、クラウスに顔を向ける。 「謝らなくていい。具合は」 「まだ診察結果は聞いていませんが、捻挫と…少し打っただけですから」 気丈に微笑むクラウスは、本当にいつもと変わりない。そうかと頷いて、シュウは、クラウスを心配していた盟主にど う説明しようかと考える。そうして、何とはなしに浮かんだ、疑問とも言えない事を舌に乗せた。 「それにしても、負傷など珍しいな。余所見でもしたのか」 刹那、クラウスの表情が強張る。 訝しく思い覗き込むと、ふと目が合って。 鮮やかに、その陣形が浮かび上がる。 気が付いてしまった。 その聡明さ故か、それとも二人の距離故か。 シュウは、青年の反らされた視線に確信を持つ。 それまで胸の端にすらなかった事実が明瞭な輪郭を描き。胸中に湧き上がるざらりとした不快なものが、薄笑いを 面に上らせる。 「そう言えばあの時、向うの前衛に赤毛の将がいたが」 クラウスは強く布団を握り締め、首を横に振った。 「…違います」 鳶色の髪が枕に落ちる。枕の白い色の所為か、肌もが病的なまでに白く見えた。 「知り合いか。…躊躇ったか?」 「…違います」 苦しげに、もう一度囁かれた否定の言葉。シュウはそれを黙殺する。 唯でさえ浅くない傷を、更にえぐる様な真似。 ―…悪趣味な。 シュウは他人事のように思い、指先でクラウスの額に触れる。 「…そんなに帰りたければ」 はっ、と、藤色の目が見開かれる。クラウスはシュウの手を払いのけ、僅かに上体を起こしてねめつけた。 「貴方が…っ、それを言いますか!」 胸を裂く様な熱と冷たさをもって、束の間、視線が絡み合う。 「それくらいになさい」 空間を破ったのは鋭い叱責だった。戸口には、薬箱を抱えたホウアンが厳しい表情で立っていた。 「肋骨にひびが入っているのですよ。動くのもつらい筈です」 ホウアンの言葉にシュウは瞠目してクラウスを見たが、すぐに顔を曇らせて目をそらした。 クラウスは視線を握り締めた己のこぶしに据え、ひたと押し黙っている。 「邪魔をした。…頼む」 シュウは声を落として告げると、頷くホウアンの横をすり抜ける。そして扉の側に、ナナミが険しい顔をして立ってい るのに気が付いた。 「…何だ」 ナナミはだまってシュウの手首をつかむと、医務室から外へと連れ出し、廊下の隅に引っ張っていく。 「何で、あんな酷いこと言うの!?」 「…立ち聞きとは、あまり褒められんな」 「なっ…! ちがう、そうじゃなくてっ。クラウスさん、あたしをかばって怪我をしたの! 悪いのはあたしなのっ」 「…何だって?」 ナナミはシュウの上着をつかんでまくし立てる。 「王国兵が退却するっていうから、皆の救護に行ったら、何人かに囲まれて…。そしたらクラウスさんが助けに来てく れて…っ。それなのに…何も知らないくせにどうして酷いこと言うのっ」 少女の大きな目がゆらりと光る。 「か、帰りたいか、なんて…っ、そんなのっ…」 涙がこぼれるのが早いか、ナナミはうつむく。小さなこぶしが、何度かシュウの胸を打った。 「…酷いよ…」 「…酷い…話だ」 治療が済み、自室のベッドに横たわりながら、クラウスはつぶやく。 肋骨3本にひび、手甲をつけていたが、腕で剣を受けたのはまずかった。右手が使えないほど痛む打撲傷と左足の 捻挫。紋章で治療はしてもらったのだが、4、5日はこの鈍痛と付き合わねばならないという。 左手を持ち上げ、クラウスは髪を掻き揚げる。 あの時否定はしたが、実の所シュウの言うとおりだった。 ナナミに切りかかろうとした兵士が自分の姿を認め、裏切り者が、と叫んで矛先を変える。その向こうに。 風になびく赤い髪、赤と白の装い。彼が振り向いて―…目が合った気がした。 重く鼓動する後悔と罪悪感。それが、王国に対するものであると気付いてしまって、目眩がした。 そして、この様だ。 "あなたが、それを言いますか" 当然だと、クラウスは思う。 帰りたいと、あの国に捕らわれたいと。 新同盟軍にありながらハイランドを恋う事を黙認されているにも拘らず、より多くを願う自分を責めるのはシュウにと って当然の権利だった。 「…裏切り者…」 …貴方なら、私を止めてくれるのではと。 無意識に甘えてしまう事の、なんという浅ましさ。 シュウは自室にもどって煙草に火をつけた。 ナナミの救援部隊が矢面に立たされたのは、明らかに自分の失策だった。 それにクラウスは巻き込まれ、傷を負った。 馬鹿だと思う。 何故あんなことを。 ゆらりと胸を覆ったのは怒りか、憎しみか、そんな薄暗い感情だった気がする。あれは何だ。 …嫉妬、か? 「馬鹿馬鹿しい…」 声に出して否定して、空いた手で髪をかき混ぜた。 …苛々する。 手にしえないものを想い求め、その気持ちに寄って背筋をぴんと伸ばしているクラウスの生き方を勇ましいと思う。 美しいと、思う。 それが揺らいだとき、彼は余りに頼りなくて、痛ましい姿を、直視していられない。 羨むほどの強さをもって、前を見ていてくれと。 理想を押し付けるのは余りに愚かで身勝手だ。 "そんなに帰りたければ" 苛立ちに任せ、答えが言えぬと解っていて投げつけた、諸刃の刃。 クラウスの目が潤んでいたのは錯覚か。 煙管から灰を落として放り投げる。 失い続けた彼に、俺はこれ以上何を求めようというのだ。 丸一日たった夜。 冴えた月の影が灯火と溶け合い、テラスの稜線を赤銅の輝きで描きあげる。 遠く獣の遠吠えと虫の音が、場内を動き回る人の気配を覆い尽くして、耳鳴りのような孤独感が空間を支配してい た。 乱れた足音が微かに響く。 蝋燭を手にしたクラウスは、テラスの先端で枠に左手をついた。ずしりと響く痛みが爪先まで届く。 「…つ…」 中腰で歯を食いしばっていた所で、不意に後ろから声がかかる。 「おい…無事か」 首だけ回すと、シュウが足早にやってきた。 クラウスに歩み寄って前から抱き起こすようにし、椅子を引き寄せて座らせる。 「す、みませ…ん…」 クラウスは横目でちらりとシュウを見る。同じように座ったシュウは唇の端を吊り上げ、腕を組んだ。 「…随分とよくなった様だが」 常と変わらない物言いに、クラウスも微笑みの形をつくる。 「ええ、おかげさまで。…どうなさったんです?」 「キバ将軍に、お前を連れ戻すよう泣きつかれた。怪我人は大人しく寝ているものだ」 クラウスの負傷で昨晩の宴会に出席しなかったキバは、酒場で数人の呑み仲間と祝杯をあげていた。体の本調子 でない息子がふらふらと出かけるのを自分では止められないと、酔いに任せてその場にいたシュウに零したのだっ た。 「泣きつかれたって…また悪乗りして呑ませたのでしょう…」 「少し勧めただけだが?」 肩をすくめたシュウに、クラウスは呆れたようにため息をつく。 「…父上も…貴方も、仕方がない人たちですね」 目線をシュウに戻すとそこには静かな表情があって、クラウスはぎくりと身をすくめた。 漆黒の眼が、真っ直ぐにクラウスを見る。 「ナナミから聞いた。…俺の過失だ」 要点だけの物言いにクラウスは息を呑む。目線をそらせず、それでも僅かに頭を横に振った。 「違います、貴方は何も―…。私の不注意です」 夜のしじまに落とされたような。広がる草の海は凪。城の明かりも一つ一つと消えていく。 すぐ上の階の明かりが落ち、自然と目をそちらに向けたクラウスは、再び顎を下げたときには微笑を浮かべてい た。 「己の腕を過信しすぎたようです。結果こんな体たらくで」 僅かに首を傾げ、その弾みで痛んだらしい、小さくうめいて傷ついた肋骨をかばう。 「…クラウス」 低く響く声、手を伸ばすには遠い。 上目にシュウを見、クラウスは勤めて明るく笑う。 「以後気をつけます。…もうよしましょう、この話は」 「…そうか」 シュウは、立ち上がろうとしたクラウスに手を差し出す。 その手を不思議そうに見つめていたが、クラウスは手を重ねてシュウを見上げ、シュウのほうは目を細めて見返し た。 「一人で立たずとも…たまには手くらいなら貸してやる」 菫色の眼が睫にけむる。震える唇がぎこちなく微笑みの形をとった。 「…嘘…」 輪郭を繋いだ点に重みがかかる。 月に雲がかかり、しんと深さを増した闇の音に、しばし二人の息が止まった。 深淵の暗さに沈んで、ただ一つそこにある手のぬくもり。 薄明の軌跡を描き、青年の手がシュウを引き寄せる。 痛めた右手もが、確かな強さで。クラウスはシュウの背に両手を回し、きつく体を寄せた。 骨が軋むほどに、強く抱いて。 「…痛くないのか」 されるがままのシュウは苦しげに言って、眉間に刻んだしわを深くする。 さらに腕に力がこもる。 吹いた突風に、テラスに残った最後の灯が消えた。 残るのは月と僅かな星。虫の音、獣の声。 脳髄を侵す痛苦。 ―…それから。 三千の嘘を重ねても、繋がらない二つの心。 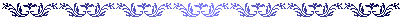 二人を喧嘩させたいなんて海棠はろくな事を考えません。 それなのに細雪様ったら、なんて素敵な小説を書いてくださったのでしょう。 クラウスが怪我という時点で海棠は身悶えておりました。 しかも何物にも代え難いくらい互いを思っているのに 微妙にすれ違ってしまう二人がたまりません。 本当にありがとうございました。 |

