愛と青春の日々 自立編(後編)
「マルロの友達ねぇ」
コウユウの兄はギジムと言った。人好きのするコウユウとはあまり似ていない厳つい顔で、クラウスを値踏みするよう
に頭のてっぺんから爪先までジロリと見た。
「こういう店でアルバイトしたことは?」
「ありません。でも頑張りますから」
「手際よく動いて貰わないとこっちも困るんだが、出来るのか」
いかにもとろそうだと言いたげで、見る人が見れば分かるんだろうかとクラウスはドキドキした。
「大体、なんだってウチを手伝いたいんだ?」
「…社会勉強です」
ギジムが爆笑した。
「あんた、いいとこのお坊ちゃんだろ。何もこんな店を手伝うことはないだろうに」
シュンとしたクラウスを見かねたのか、ロウエンが助け船を出してくれた。(ちなみにこちらも弟のマルロとはあまり似
ていない妙齢の美女である)
「いいじゃない、手伝ってくれるって言うんだから。人手が足りないのは確かでしょう。こんなに可愛いんだから、あんた
の鬼瓦みたいな顔より客受けがいいわよ」
ギジムは少し考えていたが「しょうがねぇか」と呟くとニカッと笑顔を見せた。
「じゃあ、頼むか。クラウスだったな。仕事はマルロに教えてもらってくれ」
「はいっ。ありがとうございます」
ギジムとロウエンは仕込みの準備に忙しいらしく、もうクラウスのことなど忘れたようにクルクルと働いている。コウユ
ウもブォォォと掃除機をかけ始めた。
「じゃあ、こっちへ来て。クラウス」
裏のエレベーターから従業員用の控え室に行くと、窓から事務所のビルが見えた。歩いて5〜6分くらいだろうか。と
ても目立つ容姿をしているくせにシードは平気でウロウロといろんな所を歩き回る。だからこの店のことも知っていたの
だろう。
クラウスが外を見ているうちにマルロはクリーニングしてあるユニフォームを出してくれた。
「これに着替えたら下に来てくださいね」
そう言って戻ろうとしたマルロを引き留めた。
「さっき、ギジムさん、大笑いしてたけど私何か変なこと言った?」
「変じゃないけど」
マルロは少し言いにくそうに言葉を切った。
「アルバイトの理由で社会勉強って言う人はあまりいないから」
「…そうなんだ」
「でも気にしないでください。こっちから手伝いをお願いしてるのに義兄さんが余計なこと言っちゃってすみませんでし
た。それより今日は頑張ってくださいね。ホント、結構忙しいんですよ」
マルロはにこやかに言って下に降りていった。きっと準備することがたくさんあるのだろう。
『きっとギジムさんにも世間知らずとか思われたんだろうな』
いきなり世間の荒波に揉まれたような気がするクラウスである。(をい)
「ダメだ、こんな事で一々落ち込んでたら」
そうでなくてもマルロの車はアルバイトをして買った物だと知ってちょっとショックだったのだ。「お金ならクラウスだって
稼いでるでしょう」とマルロに言われたが、確かにそうなのだけれどデュナンはクラウスにとって労働というには程遠かっ
た。好きなことをやらせて貰って、それでたまたまお金が入ってくる。しかもそれが大金であるだけに何だか自分がずる
をしているような気がしていた。
「頑張ろうっ」
新たな決意に燃えるクラウスであった。
マルロに言われるままバタバタと動いているうちに開店時間が近づいてきた。
忙しそうだった割にギジムもロウエンもクラウスの様子を観察していたらしく「客に目を配って注文だけ取ってくれれば
いいから」と命じられた。あまり役に立ちそうもない、と暗に言われているような物なのだが「足手まといだから帰れ」と
言われるのではないかと思っていた(ギジムにはそれくらいの迫力があった)クラウスは仕事をさせてもらえるだけで嬉
しかった。
「えっと、お客様を席に案内してお飲物を聞いて…」
教えられたことをブツブツ口の中で繰り返しているとギジムが苦笑している。
「おい、兄ちゃん。元気よく頼むな。腹の底から声を出して『いらっしゃいませ』って言ってみな」
「いらっしゃいませ」
「おう、なんだ。良い声が出るじゃないか。その調子で頼むわ」
「はいっ」
ステージで鍛えていて良かったと思っていると、コウユウの「っらっしゃいませ〜」と明るい声が響いた。
お客さんだ、とクラウスは飛び出していった。
「いらっしゃいませ。4名様ですね。こちらのお席へどうぞ」
最上級の笑顔で案内しようとしたが、学生とおぼしき客はクラウスの顔を見て固まっていた。いきなり間違えてしまっ
ただろうかと少し声が小さくなる。
「あの、こちらへどうぞ」
「え、あ、ああ」
席に着いてからも客は呆気にとられたようにクラウスを見ている。
「先にお飲物をお願いします」
答えは返ってこない。やっぱりどこかで間違えたのかもしれない。だが、ここに来るまでの手順なんて余りにも簡単で
どこを間違えたのか分からない。仕方なくおずおずと聞き直した。
「お飲物は」
「え、あ、ちゅ中生4つ…」
「ちゅうなま?ですか?あの、お飲物なんですが」
「だから、生ビールの中ジョッキを4つ」
「ああっ、それの略なんですね♪はい、かしこまりました」
新しい業界用語(?)を覚えてニコニコと答えたのだが、客はまだ呆然とクラウスを見ている。
ちゃんと注文が取れたのだからクラウスは間違えていないはずだ。だからお客さんの方が変なのかもしれない。無茶
苦茶な考えだったが、次の客もその次の客もみんな同じような反応だったので、そんな物なのかと思い直した。
1時間ほどして客席がほとんど埋まるようになると段々要領も分かってきて楽しくなっていた。ロウエンが「今日は注文
が多いねぇ」と言っていたので、いつもより忙しいのだろう。クラウスも客の様子を見て追加オーダーがあるかどうか分
かるようになっていた。というか、始終視線を感じていて目が合うお客さんのテーブルに行くと何故かみんな慌ててオー
ダーをしてくれるのだ。
「ねえ、君って」
OLグループのテーブルに行ったとき、一人が思い切ったように話しかけてきた。
「デュナンのクラウスに似てるって言われない?」
似てる、とは言われない。本人だから。でもそんなことは言えないから、笑って誤魔化すと「やだ、かわいー」という声
が上がった。
「そっくりよねえ」
ニコニコ。
「やっぱりぃ。私も似てると思ってたの」
お店のあちこちで「私もそう思った」「俺も」という声が上がりはじめた。図らずも一気に店中の注目を浴びることになっ
てクラウスはドギマギと赤くなっていた。
「やん、可愛い。クラウスくーん、次はこっちね」
「クラウス〜、こっちもオーダー」
「はい、ただいま」
すっかりそっくりさんにされてしまったが、客は面白がって注文するので大忙しのクラウスである。
余りにも忙しいのでマルロが「大丈夫?」と気を遣ってくれるが、クラウスは却って楽しかった。デュナンで大勢の人に
囲まれるようになってから、みんなでワイワイやっている賑やかな雰囲気が結構好きになっていたし、一人で本を読ん
でいるのとは違った楽しさがある。初めての体験という物珍しさもあって弾むような気分でテーブルを回っていた。
コウユウが自慢するだけあって本当に人気のある店らしい。さすがにピークの時間帯を越えたらしいのに、それでも
客足が途絶えない。
クラウスが新しい客のオーダーを取っているとすぐにコウユウの「いらっしゃいませ〜」という声が響いた。
『またお客さんだ。早くこのオーダーを取って次のお客さんにおしぼりを出さないと』
だが客はメニューを指差したまま固まっていた。視線は店の入り口に釘付けである。
「あの、お客様?」
そう言えば、さっきまでの賑やかだった店内のざわめきが波が引くように静まっている。
ようやく店の異変に気がついて『どうしたんだろう』と振り向いたクラウスも驚いた。見覚えのある赤い髪が見えたの
だ。
『シード、カッコイイ〜』
シードの燃えるような髪と精悍な容姿はどうしたって誤魔化しようがない。店の客は突然のスターの降臨に息を飲んで
見守っている。もう、存在感が違うのだ。憧憬の視線を一身に集めているのに全然動じていない、あくまでもさりげない
姿は余裕さえ感じられて、いつも一緒にいるクラウスでもドキドキするほど格好良かった。
思わず突っ立ったまま見とれているとシードの目が驚いたように見開かれてこちらに歩いてきた。
「あ、いらっしゃいませ〜」
「お前…いらっしゃいませって、何やってんの。こんなとこで」
「お手伝い」
「お手伝い?」
「あ、クルガンも一緒なんだ」
ニコニコと手を振ってから慌てて言い添えた。
「このお店、マルロの家の人がやってて今日はアルバイトが休みなんだって。だから代わりに手伝ってただけだから」
直後、店は悲鳴のような歓声に包まれた。
「いいのかよ、このままやらせて」
シードとクルガンは他の客の不躾な視線を浴びないようにとマルロが気を利かせて店の奥まった席に案内されてい
た。差し向かいで酒を飲みつつ、二人の視線はどうしてもクラウスを追っていた。
結局デュナンのクラウスと分かってもクラウスは相変わらずオーダーを取りに歩いている。それが客にとって嬉しくな
いはずがないから、引っ張りだことなっていた。
「まあ、本人も楽しんでいるみたいだし、いいだろう」
「優しいじゃん、いつもは煩く言ってるくせに」
「あの事件からこっち、少し落ち込んでいるようだったからな。こんな事でも気分転換になるならかまわんさ」
「フーン…あっ」
酔ったサラリーマンがクラウスの手を握って離さないのが見えた。「握手くらいいいじゃないか」と言ってるのが聞こえ
てきてシードはすっくと立ちあがった。
大股で歩み寄ってきたシードに圧倒されながらも、お酒という強い味方を得ているサラリーマンは少しも怯んでいなか
った。
「悪いけど、その手離してくれないかな」
「なんだよ、お前は」
構わずシードはサラリーマンの手首を掴んだ。
「イテテ」
「こいつ、俺の弟みたいなもんなんだ。あんただって、自分の娘が酔っぱらいに触られてたら嫌だろう」
ちょっと凄みをきかせたシードに、男は「冗談だよ、冗談」と笑って誤魔化している。
「悪いね」
そう言うとシードはそのままクラウスの手を引いて自分のテーブルまで連れてきた。
「気をつけないとダメだろうが」
席に着くなり説教を始めた。
「客も酒が入って気が大きくなってるんだから、ああいうトラブルは自分であしらえるようにしないと店に迷惑がかかるん
だぞ」
「はい」
「客じゃ護身術使って押さえつけるって訳にはいかないからな」
「あ、こういうのが本当のセクハラなんですね」
「そう」
クルガンは吹き出した。説教をしているシードというだけでも可笑しかったのに、クラウスのボケッぷりがツボにはまっ
てしまったのだ。
「もう、お前が心配でゆっくり飲んでられないだろ」
「ごめんなさい」
「ほら、向こうで呼んでるぞ」
「はーい、ただいま」
まだ肩を震わせているクルガンにシードが気恥ずかしそうな顔をして「なんだよ」と突っかかった。
「だって気になるじゃないか。危なっかしいっていうか…あ、そうだ。シュウ呼ぼう」
「え?」
「あいつがいれば見張っててくれるじゃん。そうしたらこっちは気兼ねなく飲めるし。クラウスが酔っぱらいに絡まれてる
って言ったら、あいつ飛んでくると思わない?」
「あまり挑発するなよ」
「分かってるって…あ、シュウ?今飲んでるんだけどさ…」
シュウが来たのは早かった。どこにいたのか知らないが、ほんの10分ほどで来たのにはクルガンも驚いた。だがそ
れ以上に驚いたのはクラウスだった。
「シュウ」
嬉しそうに言ったクラウスの声は、だが店の客の悲鳴だか怒号だか分からない歓声にかき消されていた。
居酒屋灯竜山は混乱の極みにあった。
相次ぐ人気ミュージシャンの登場に客は舞い上がっている。しかもそのうちの一人がオーダーを取りに来るのであ
る。
客の反応に気をよくしたシードは「マイクとカミューも呼ぼう」と言っているし、よく事態が把握できていないギジムとロウ
エンは客の回転が悪いというより、どのグループも居座ったように動かないのを見て「入れ替え制にしようか」などと話し
合っている。コウユウはコウユウで「注文しないんなら帰ってくんな」と言いながら、注文だけして残した客は許さねぇと
息巻いていた。
みんなが熱に浮かされたように騒いでいる中、クラウスは一人取り残されたように重苦しい気持ちを抱えこんでいた。
「クラウス、このヒレ酒、どのテーブルだっけ」
「あそこ。柱の所の」
「あ、あそこか。サンキュー」
片手に料理、片手に酒の乗った盆を持って器用にテーブルの間を縫って歩いているのはシーナである。本当ならシー
ナがいてくれてとても心強いはずなのに、どんどん気分が沈んでいた。どうしてかは分かっている。シーナはシュウと一
緒に来たのだ。
シュウの姿を見たとき飛び上がりたいくらい嬉しかった。なのに、その後ろからひょっこりとシーナが顔を出して、自分
でも笑顔が強ばるのが分かった。シーナが今日会う約束をしていたのは女の子ではなくてシュウだったのだ。その事実
がショックだった。それなのにシーナの言葉が追い打ちをかけた。
「あれ、知らなかった?俺たち結構仲いいの。この間も深夜のドライブしちゃったんだ。ね、シュウさん」
シュウは少し困ったような顔をしてシーナを見ている。
いつも通りに微笑んで「そうなんだ」と言ったけれど、胸の中は嵐のように訳の解らない気持ちが渦巻いていた。
知らなかった?って知るわけがない。シーナとシュウがいつそんなに親しくなったのか、全然気付かなかった。誘拐事
件の時に気安そうに見えたのは、ずっと以前から親しかったからなのかもしれない。
ドライブはシュウの車でしたのかな。やっぱりシーナは助手席に座ったのだろうか。
そう思ったら胸の奥がチクチクと痛んだ。
『そんなの酷い。だってあそこは私の席なのに…』
それが自分勝手な思いこみだというのは分かっていた。それでも「裏切られた」という思いを拭い去ることはできなか
った。二人が親しいからと言ってシーナとシュウを詰るのはお門違いという物だ。だが理性ではそう思っていても、泣き
たいような気持ちはどうしようもなかった。
物凄く変だ。二人が一緒だったからって、どうしてこんな気持ちにならないといけないのだろう。
「クラウス、疲れたんじゃない?」
沈み込んでいるクラウスを気遣わしそうにマルロが見ていた。
「いつもならそろそろ手が空いてくるんだけど、今日は忙しいから。ごめんね」
「ううん、どっちかというと私たちの方がご迷惑をかけてるみたいなのに」
「迷惑なんてことないよ。店が繁盛してくれると凄く嬉しいんだ。姉さんには苦労させちゃってるし」
「苦労?」
「僕って金食い虫だから。学費がね、奨学金を貰ってもうちの大学って授業料高いでしょう」
「うん」
でも授業料のことなどクラウスは考えたこともなかった。
「国立にすればよかったんだけど、どうしてもテスラ先生のゼミに入りたくって」
「そうだったんだ」
今まで自分はとても狭い世界でしか生きていなかったんだ。唐突にそんな風に思った。
「元気ないね。裏に行って少し座ってていいですよ。もうそんなに注文も入らないと思うし」
「平気。これでもライブで結構体力ついたんだから」
二人でクスリと笑いあった。
「疲れてるっていうより、自分があまりにも物を知らないなって思って」
「そんなの、僕だって一緒ですよ」
不思議そうに見たクラウスにマルロは少し赤くなりながら話し始めた。
「今日は僕も色々発見が多かったです。僕、クラウスの伝記を書くなんていってて何も分かってなかったなって。クラウ
スの容姿端麗なところとか、家柄が良くて芸術的な才能にも恵まれていてっていう表面的なことばかりに目がいって、あ
んまりクラウスの内面のこととか考えたことがなかった。本当は僕達と全然変わらない普通の子なのにね」
「ホント?普通に見える?私は一人では何も出来なくてデュナンでもみんなの足を引っ張ってばかりで、全然ダメだって
思ってて」
「全然大丈夫です。そういう不安みたいなのって、きっと僕達みんなに当てはまることなんですよ。だから僕も今度はそ
ういうクラウスの一面をちゃんと捕らえて伝記に取り組んでみようと思うんです」
「伝記って…それ、本気なの」
「もちろんです」
「でも、私の事なんて何も書くことないのに。それならシーナの方がもっと凄い経験してるし」
「シーナ?」
「うん、だってシーナのお父さんってトラン共和国の大統領だよ」
「ええっ」
「3年前の革命の時、シーナも参加していたし」
「ほ、本当ですか」
「うん、ね、シーナ」
シーナが「なになに?」と寄ってきた。
「シーナも革命に参加したんだよね」
「ああ、あれね。大変だったんだよ。オヤジは夏休みだけ参加する革命の戦士なんているかって怒るし、おふくろは危
険だからと思って留学させてるのに何で戻ってくるんだって泣くし。大騒ぎになって困ったよ」
「す、凄いじゃないですか。レパント大統領は現代の英雄ですよ。シーナも革命に参加したなんて凄いなあ」
マルロの目は完全にハート形になっていた。
「ね、だから伝記だったらシーナの方が適任だと思うんだ」
「おい、クラウス。そんなこと言って俺に押しつけるのかよ」
「押しつけるなんて人聞き悪い。本当のことを言ってるだけなのに」
クラウスとシーナが言い争っているとマルロが目をキラキラさせて宣言した。
「是非二人の伝記を書かせてください。人気ミュージシャンと革命の戦士の友情。凄く良い物が書けそうな気がします
っ」
マジかよ、とシーナが情けなさそうな声を出した。
暖簾をしまった後、一通り片づけを終えてからもクラウス達は店に残っていた。
何だかんだと言いながらシーナはマルロの質問に答えて革命の話をしている。シュウとクルガンはワープの曲のこと
で話し込んでいるみたいだ。
クラウスはそっとお盆を持って席を外した。シードが「こっちの方が気楽だ」と言って一人で座敷に座り込んで飲んでい
たから下げる物があれば持ってこようと思ったのだ。シーナの会話に入るのも、シュウの会話に入るのも何となく面白く
なくて、かといってジッとしていると嫌なことばかり考えてしまうから少しでも動いていたかったのだ。
衝立で遮られている座敷をひょこっと覗き込んでクラウスはドキリとした。シードは何かぼうっと考え事をしているらし
い。その横顔がとても寂しそうに見えたのだ。
いつも陽気で元気いっぱい、覇気に満ちているシードのそんな様子を初めて見たから、とても声などかけられなかっ
た。どうしよう、と佇んでいるとシードがフッと笑ってこちらを振り向いた。
「なーにぼんやり突っ立ってンだよ」
そう言うシードはいつものシードだ。けれど、さっきの表情が気になるクラウスは「あの」と言ったきり話の接ぎ穂が見
つからない。こんな時に気の利いた言葉の一つも掛けられない自分が歯痒い。
「こっち来いよ」
言われるまま座敷に上がり込むと「飲むか」と猪口を渡された。
「でも」
「飲んだことくらいあるんだろ」
コックリと頷いた。父が家で飲む時少し付き合うことがある。父が「なかなか強いじゃないか」と言っていたから強い方
なのかもしれない。
「だよなあ。今時飲んだことないヤツなんていないよな」
そう言いながら酒を注ごうとするのでクラウスは慌てて猪口を遠ざけた。
「ダメ」
「あーあ、つまんねぇな。クラウスちゃんは良い子だからな」
その言葉に少し棘を感じて、自分もモヤモヤしていたクラウスはムキになって反論した。
「だって、それで問題になったらみんなに迷惑掛けちゃうんだから。クルガンだって大変になっちゃうし」
シードは少しドキッとした顔をした。
「そうだよな。お前、本当に良い子な」
今度のシードは少し落ち込んでいるみたいだ。一体どうしたんだろうとクラウスはシードの顔を覗き込んだ。
「クルガンがお前のこと可愛がるの当然だよな」
「シード?」
「クルガン、まだシュウと話してたか?」
「うん、ワープの新曲がどうとかって。用事があるんだったら呼んで来ましょうか」
「いい、いい。別に用事じゃないんだ」
そう言ってから自嘲気味に呟いた。
「自分で呼んどいて…するなんて、俺も小さい男だよなあ」
クラウスはまじまじとシードを見た。シードがそんなことをいうとは思わなかった。いつも自信満々のシードにもそんな
負の感情があるなんて思ってもいなかったのだ。
シードはグイッと酒をあおると、手酌でどんどん杯を重ねた。見る間に酒が減っていく。いくら強いといってもピッチが
早すぎるだろう。
「シード、そんなに飲んだらダメですってば。帰れなくなっちゃいますよ。またクルガンに怒られるから」
するとシードの手がフッと止まった。
「俺さ、クルガンがいるからデュナンに入ったんだ」
「シード、酔ってるでしょう。クルガンがデュナンをスカウトしたんでしょ。それくらい私だって知ってます。騙そうとしたって
ダメなんだから」
「バーカ。クルガンは元々デュナンのベーシストだったんだよ」
それは初耳だった。
「すげぇ格好良かったんだぜ。俺、クルガンの側いっつもウロウロしててさ。ホウアンがギターのオーディションさせてく
れるって言った時はホントに嬉しかったなあ。これで一緒にプレイできるんだって思ってたのに…」
でも現・デュナンの最古参はシュウの筈だ。
「シュウは?」
「俺よりちょっと前に入ったんだ。その頃、クルガンが家の事情だか何だかで外れていたから、その間の助っ人ってこと
だったんだけどな。でも結局そのまま戻ってこなかったから」
クラウスは少しドキッとしていた。シードはさっきもシュウを呼んだことを後悔しているようなことを言っていた。
「シード、シュウが嫌いなの?」
「ん?あ、そんな風に聞こえたらごめん。別にシュウが嫌いなんじゃないよ。ちょっと難しいヤツだけど、あいつのプレイ
も好きだし曲も好きだよ」
そう言ってから「はぁっ」と溜息をついた。
「お前にそんな心配させるようじゃしょうがねぇな。こういうところが小せぇんだよな、俺は」
やっぱりシードは酔っているに違いない。クルガンを呼んでこようかと迷っているうちに訳の解らないことを言いだし
た。
「お前たち見てるとやっぱり追いかけさせなきゃダメだと思うんだよ」
「は?」
「でも俺なんて追いかけてばっかだもん。最初っからずっとそうだしさ。負けって決まってるようなもんだよな」
「何が?」
「もう、クルガンなんてさ、俺のことなんかどうでも良いんだよ」
「そんなことないですよ」
よく分からないがシードは酔ってる上に少し落ち込んでいるらしい。だから元気づけようと勢い込んで否定した。
「クルガンはいっつも私たちのことを考えてくれてるじゃないですか。どうでも良いなんて思ってないですよ」
「そうだよな。私たちのことを考えてくれてるよな」
シードは更にどんよりとした雰囲気になっていた。
「カミューとマイクロトフが羨ましいよ。どうやったらあんな風に揺るぎない仲になれるのか、俺には想像もつかないや。
でも、俺がいけないんだろうな。独占したがるから」
本当に、カミューだったらこういう時なんて言って慰めるんだろう。そもそもクラウスはシードが何を言ってるかよく分か
ってないから、気を揉むばかりで口を挟むことも出来ない。
と、俯いていたシードが顔を上げた。
「一度聞いてみたかったんだけどさ。お前の目から見てデュナンの人間関係ってどう思う?」
「どうって…」
もしかしたらクラウスの知らないところで仲が悪いんだろうか、と心配になってきた。
「誰と誰ができて…じゃなくて仲良いか、とか分かる?」
取り合えず、仲が悪い話ではないんだとホッとした。
「えっと、みんな仲良いですよね」
「その中で、特に気付いたのある?」
「特に、ですか?」
クラウスは少し考えた。
「えっと…マイクとカミューは仲良いですよね。一緒に住んでるし」
「ええっ、そ、そうなのか?」
シードがガバッと顔を上げたのでクラウスは驚いた。
「同じマンションに住んでるって言ってましたよ」
「マンションだろ。ああびっくりした。それは知ってるよ。一応部屋は別だからな、あいつらも」
「そうなんですか。同じマンションなら一緒に暮らした方が経済的ですよねえ」
「…お前って、時に大胆だよね」
「?」
「まあ、いいや。後は?」
後と言っても残っているのはシードとシュウとクラウスである。何と答えたものか困ってしまった。するとシードは意味あ
りげに笑って聞いてきた。
「シュウは誰だと思う?」
「シーナ」
何故か自然と口から出て、その自分の言葉にクラウスはズーンと落ち込んだ。だが、シードは目を丸くして、それから
爆笑した。
「報われないなー、あいつも」
落ち込んでいるところにあんまり笑われたのでクラウスもムキになった。
「シードはクルガンと仲良しですよねっ」
「…そう?」
「そうですよ。今日だって一緒だったしっ」
「それは、俺が誘ったからだよ」
「でもシードの言うことならクルガン何でも聞くしっ」
「それは俺が我が儘言うから、しょうがなく…」
「いっつもシードを見てるしっ」
クラウスはプンプンして言ったのだが、シードは真顔で固まっていた。
「嘘言うなよ」
「嘘じゃないですっ。最初にデュナンのライブを見せてくれたときだってクルガン、ずっとシードのこと見てましたもん。だ
からクルガンはシードのことが大事なんだなって思って」
「すいません、今のところをもう一度」
「え、今のところ?…嘘言うなよ?」
「それは俺が言ったんだ」
「えっと、んーーー」
「だから、誰が誰を大事にしてるって?」
「…クルガンがシード」
「そうかあ」
シードはニカッと笑うとクラウスをギュッと抱きしめた。
「ほんとーに可愛いぞ、お前」
クラウスはギュウギュウと抱きしめられて苦しくてジタバタと藻掻いていた。
「よーし、お兄さんは気分がいい。今夜はお前の言うこと何でも聞いてやるぞ」
「いいですよ、そんなの。それよりちょっと、離してくれませんか」
だがシードは額と言わず頬と言わずキスの嵐をふらせている。ああもう、とクラウスは諦めてされるがままになってい
た。大体、酔っぱらいをまともに相手にしても無駄なのだ。ずっと父を見ていてそれだけはよく分かっているクラウスで
ある。
「何したい?寿司食いに連れてってやろうか」
「いいから離してください」
髪をグシャグシャと掻き回されていい迷惑である。
「よーし、じゃあ焼き肉にするか?」
その時ハッと閃いた。
「夜のおもちゃ、教えてください」
耳元で囁くとシードが唖然とした顔をした。
「まだそんなこと言ってるのか?」
「だって誰かに聞くのもなんだか」
「そりゃ、そうだな」
少し考えてからシードは意外なことを言った。
「シュウは教えてくれなかったのか?」
「シュウ?ううん、もうその話はするなって」
「ばっかだな、あいつ。つけこんじまえばいいのに」
「つけ込む?」
「ああ、気にするなって。じゃあ、お兄さんが教えてやろっか、手取り足取り」
「はいっ♪」
嬉しくて返事をするとシードは心底呆れたという顔をした。
「あのなあ、お前分かってんの?」
「だからっ、分からないから聞いてるんでしょっ」
「こら、そんな大きな声出すなって。ムードがなくなる」
「ムード?」
「そ、大体お前、天下のシード様とこんなくっついていて何ともないわけ?」
「何が?」
キョトンとしていると「ちょっと傷つくなあ」とシードが苦笑した。
「たとえばさ、キスしたいなーとか思わない」
「全然。大体さっき散々…」
「こーら、お兄さんを怒らすんじゃない。ホントにおもちゃにしちゃうぞ。後悔するなよ」
「え?」
グイッと体重を預けられてアッという間に畳に押し倒されてしまった。いつもと角度が違うせいかシードが違う人に見え
る。しかもその顔が徐々に近づいてきてクラウスは焦った。
「ちょ、ちょっとシード、酔ってるでしょ、シードッ、わーーーーっ」
「お前らさっきから何を騒いで…」
次の瞬間、すごい勢いでシードが引き剥がされた。
「「何をやってるんだっシードッ!」」
クルガンとシュウの怒号が響いた。
「ちぇっ、なんで二人とも俺のことばっかり」
「お前が原因作っているんだろうがッ」
クルガンが怒鳴りつけ、シュウが「何をされた?」とクラウスに問いただしてきた。
「何にもしてないって、まだ」
「まだって言うのは何なんだっ」
「煩いよ、クルガン」
「全く、少し目を離すと好き勝手なことばかりして」
「わーったって。それよりクラウス、続きはちゃんとシュウに教えてもらえよ」
シードにウインクされて戸惑いながら見上げると、緊張した面もちのシュウと目が合ってしまった。
「シュウ、クラウスに優し〜く教えてやれよ」
「いい加減に死ろっ、お前は」
とにかく先に失礼する、とクルガンはシードを引きずるようにして帰っていった。きっと物凄くクルガンに怒られるだろう
にシードはなんだか嬉しそうだった。
帰りはいつものようにシュウの車である。が、ここにシーナも座っていたのだと思うとなんだか気が晴れない。
『別に私が特別ということはないんだ』
それが寂しい。
クラウスの中では「夜のおもちゃ」については、もうどうでも良くなっていた。いくら鈍いクラウスでも、あそこまでシード
にされたらどうやらセックスと関係のあることらしいということは気がついた。だからみんな困ったり怒ったりしていたの
だろう。
だから、それはもういい。それよりシーナの事の方が大問題だと思っていた。
「シュウさんが可哀想じゃん」
あの騒ぎの後、いきなりシーナはそう言ったのだ。
「そりゃ、相手を振り回した方が勝ちって俺も言ったよ。けど、あれはやり過ぎだって。あんまり調子に乗ってると見放さ
れるぞ。大体、人の気持ちを踏みつけにするなんて、お前らしくないよ」
シーナはかなり怒っているみたいだった。
「調子に乗ってる訳じゃ」
「分かってる。お前は全然意識してないでやってるんだろ。でもそれってもっと罪が大きいっていうことは分かってた方が
いいと思うぞ」
何でシーナにこんなに怒られなければいけないんだろう。何で私はシュウの事が何も分からないのにシーナはなんで
も分かっているんだろう。
惨めな気持ちでいるクラウスに、シーナは更に意外なことを言った。
「シュウさん、今日全然お酒飲んでないだろ。きっとクラウスのこと送っていこうと思ってるんだよ。だから早く一緒に帰り
な」
「え?」
それからシーナは叱られてしょんぼりしているクラウスの代わりに「シュウさーん、クラウスのこと送ってやってよ」と声
を張り上げたのだった。
シーナが何を考えているのか、クラウスには全然分からない。
それに、本当はシーナに叱られたことよりも「見放されるぞ」という言葉が堪えていた。見放されるということは嫌われ
るということだろう。
シュウに嫌われる。それだけはイヤだ。断じてイヤだった。
「どうした?疲れたのか」
ずっと黙りこくっているクラウスにシュウが心配そうな声をかけた。
「シーナ、置いてきちゃったね」
「そんなことを気にしていたのか。あいつなら大丈夫だろう。あの近くに友達のマンションがあるらしい。居酒屋を手伝っ
ていたのも友達が帰ってくるまでの時間潰しみたいだし」
「そうなの?」
「電話の様子から察するにな」
そうか、今日一緒だったから知ってるんだ。
「シュウってシーナと仲良しだったんですね。知らなかった」
「仲良しって訳じゃない」
「でも、今日も一緒だったんでしょう」
「あ、あぁ、まあ…」
何故かシュウは言葉を濁して、それきり会話は続かない。気詰まりな沈黙のままマンションに着いてしまった。
「今日はありがとうございました」
そそくさと降りようとしたクラウスをシュウが慌てて引き留めた。
「その、ちょっと、これを持っていけ」
後部座席から何やら包みを取り出した。
「これ、何ですか?」
無造作にグイッと押しつけられた箱は綺麗にラッピングされている。
「気に入らなければ捨ててもいい」
怒ったような顔でシュウは言ったが、これはどう見たってプレゼントだろう。少なくとも、こんな大げさにリボンの付いて
いる物をプレゼント以外で貰ったことはない。
「え、でも、誕生日じゃないのに」
「だから、いらなければ捨てても」
「そんなっ、捨てたりなんてしませんっ。開けてみてもいいですか?」
「ああ」
ぶっきらぼうな中にどこか恥ずかしそうな響きの混ざった返事を聞いてクラウスはいそいそとリボンをといた。
「可愛いっ!」
箱から出てきたのは真っ白なテディベアだった。
「お前のは近所の子にあげたと言っていただろう。だから」
「それを覚えててくれたんですか」
「ああ、まあ。しかし、いろんな種類があるんで驚いた。ぬいぐるみのブランド物なんて聞いたことがなかったぞ、俺は。
それにしてもシーナはこの手のことには詳しいな。どこの店の何がどうだとか、俺にはさっぱりわからん」
何も聞いていないのに一人で喋り続けるシュウを余所にクラウスはテディベアを抱きしめていた。
「この子はシュウが選んでくれたんですか」
「そうだ」
「ありがとう、シュウ」
今までの不安も何もかもがいっぺんに吹き飛んで、クラウスの長い一日は最高の終わりを迎えたのだった。
そして…。
極上の笑顔と共に胸に飛び込んできたクラウスを抱き留めながら、どうして俺はここで理性が飛ばないのだろうとシュ
ウは己のクールな性格を少しばかり呪っていた。
が、まあいいだろう。少なくとも二人の間にあった距離が大分縮まっていることは確かなようだから。
コウユウの兄はギジムと言った。人好きのするコウユウとはあまり似ていない厳つい顔で、クラウスを値踏みするよう
に頭のてっぺんから爪先までジロリと見た。
「こういう店でアルバイトしたことは?」
「ありません。でも頑張りますから」
「手際よく動いて貰わないとこっちも困るんだが、出来るのか」
いかにもとろそうだと言いたげで、見る人が見れば分かるんだろうかとクラウスはドキドキした。
「大体、なんだってウチを手伝いたいんだ?」
「…社会勉強です」
ギジムが爆笑した。
「あんた、いいとこのお坊ちゃんだろ。何もこんな店を手伝うことはないだろうに」
シュンとしたクラウスを見かねたのか、ロウエンが助け船を出してくれた。(ちなみにこちらも弟のマルロとはあまり似
ていない妙齢の美女である)
「いいじゃない、手伝ってくれるって言うんだから。人手が足りないのは確かでしょう。こんなに可愛いんだから、あんた
の鬼瓦みたいな顔より客受けがいいわよ」
ギジムは少し考えていたが「しょうがねぇか」と呟くとニカッと笑顔を見せた。
「じゃあ、頼むか。クラウスだったな。仕事はマルロに教えてもらってくれ」
「はいっ。ありがとうございます」
ギジムとロウエンは仕込みの準備に忙しいらしく、もうクラウスのことなど忘れたようにクルクルと働いている。コウユ
ウもブォォォと掃除機をかけ始めた。
「じゃあ、こっちへ来て。クラウス」
裏のエレベーターから従業員用の控え室に行くと、窓から事務所のビルが見えた。歩いて5〜6分くらいだろうか。と
ても目立つ容姿をしているくせにシードは平気でウロウロといろんな所を歩き回る。だからこの店のことも知っていたの
だろう。
クラウスが外を見ているうちにマルロはクリーニングしてあるユニフォームを出してくれた。
「これに着替えたら下に来てくださいね」
そう言って戻ろうとしたマルロを引き留めた。
「さっき、ギジムさん、大笑いしてたけど私何か変なこと言った?」
「変じゃないけど」
マルロは少し言いにくそうに言葉を切った。
「アルバイトの理由で社会勉強って言う人はあまりいないから」
「…そうなんだ」
「でも気にしないでください。こっちから手伝いをお願いしてるのに義兄さんが余計なこと言っちゃってすみませんでし
た。それより今日は頑張ってくださいね。ホント、結構忙しいんですよ」
マルロはにこやかに言って下に降りていった。きっと準備することがたくさんあるのだろう。
『きっとギジムさんにも世間知らずとか思われたんだろうな』
いきなり世間の荒波に揉まれたような気がするクラウスである。(をい)
「ダメだ、こんな事で一々落ち込んでたら」
そうでなくてもマルロの車はアルバイトをして買った物だと知ってちょっとショックだったのだ。「お金ならクラウスだって
稼いでるでしょう」とマルロに言われたが、確かにそうなのだけれどデュナンはクラウスにとって労働というには程遠かっ
た。好きなことをやらせて貰って、それでたまたまお金が入ってくる。しかもそれが大金であるだけに何だか自分がずる
をしているような気がしていた。
「頑張ろうっ」
新たな決意に燃えるクラウスであった。
マルロに言われるままバタバタと動いているうちに開店時間が近づいてきた。
忙しそうだった割にギジムもロウエンもクラウスの様子を観察していたらしく「客に目を配って注文だけ取ってくれれば
いいから」と命じられた。あまり役に立ちそうもない、と暗に言われているような物なのだが「足手まといだから帰れ」と
言われるのではないかと思っていた(ギジムにはそれくらいの迫力があった)クラウスは仕事をさせてもらえるだけで嬉
しかった。
「えっと、お客様を席に案内してお飲物を聞いて…」
教えられたことをブツブツ口の中で繰り返しているとギジムが苦笑している。
「おい、兄ちゃん。元気よく頼むな。腹の底から声を出して『いらっしゃいませ』って言ってみな」
「いらっしゃいませ」
「おう、なんだ。良い声が出るじゃないか。その調子で頼むわ」
「はいっ」
ステージで鍛えていて良かったと思っていると、コウユウの「っらっしゃいませ〜」と明るい声が響いた。
お客さんだ、とクラウスは飛び出していった。
「いらっしゃいませ。4名様ですね。こちらのお席へどうぞ」
最上級の笑顔で案内しようとしたが、学生とおぼしき客はクラウスの顔を見て固まっていた。いきなり間違えてしまっ
ただろうかと少し声が小さくなる。
「あの、こちらへどうぞ」
「え、あ、ああ」
席に着いてからも客は呆気にとられたようにクラウスを見ている。
「先にお飲物をお願いします」
答えは返ってこない。やっぱりどこかで間違えたのかもしれない。だが、ここに来るまでの手順なんて余りにも簡単で
どこを間違えたのか分からない。仕方なくおずおずと聞き直した。
「お飲物は」
「え、あ、ちゅ中生4つ…」
「ちゅうなま?ですか?あの、お飲物なんですが」
「だから、生ビールの中ジョッキを4つ」
「ああっ、それの略なんですね♪はい、かしこまりました」
新しい業界用語(?)を覚えてニコニコと答えたのだが、客はまだ呆然とクラウスを見ている。
ちゃんと注文が取れたのだからクラウスは間違えていないはずだ。だからお客さんの方が変なのかもしれない。無茶
苦茶な考えだったが、次の客もその次の客もみんな同じような反応だったので、そんな物なのかと思い直した。
1時間ほどして客席がほとんど埋まるようになると段々要領も分かってきて楽しくなっていた。ロウエンが「今日は注文
が多いねぇ」と言っていたので、いつもより忙しいのだろう。クラウスも客の様子を見て追加オーダーがあるかどうか分
かるようになっていた。というか、始終視線を感じていて目が合うお客さんのテーブルに行くと何故かみんな慌ててオー
ダーをしてくれるのだ。
「ねえ、君って」
OLグループのテーブルに行ったとき、一人が思い切ったように話しかけてきた。
「デュナンのクラウスに似てるって言われない?」
似てる、とは言われない。本人だから。でもそんなことは言えないから、笑って誤魔化すと「やだ、かわいー」という声
が上がった。
「そっくりよねえ」
ニコニコ。
「やっぱりぃ。私も似てると思ってたの」
お店のあちこちで「私もそう思った」「俺も」という声が上がりはじめた。図らずも一気に店中の注目を浴びることになっ
てクラウスはドギマギと赤くなっていた。
「やん、可愛い。クラウスくーん、次はこっちね」
「クラウス〜、こっちもオーダー」
「はい、ただいま」
すっかりそっくりさんにされてしまったが、客は面白がって注文するので大忙しのクラウスである。
余りにも忙しいのでマルロが「大丈夫?」と気を遣ってくれるが、クラウスは却って楽しかった。デュナンで大勢の人に
囲まれるようになってから、みんなでワイワイやっている賑やかな雰囲気が結構好きになっていたし、一人で本を読ん
でいるのとは違った楽しさがある。初めての体験という物珍しさもあって弾むような気分でテーブルを回っていた。
コウユウが自慢するだけあって本当に人気のある店らしい。さすがにピークの時間帯を越えたらしいのに、それでも
客足が途絶えない。
クラウスが新しい客のオーダーを取っているとすぐにコウユウの「いらっしゃいませ〜」という声が響いた。
『またお客さんだ。早くこのオーダーを取って次のお客さんにおしぼりを出さないと』
だが客はメニューを指差したまま固まっていた。視線は店の入り口に釘付けである。
「あの、お客様?」
そう言えば、さっきまでの賑やかだった店内のざわめきが波が引くように静まっている。
ようやく店の異変に気がついて『どうしたんだろう』と振り向いたクラウスも驚いた。見覚えのある赤い髪が見えたの
だ。
『シード、カッコイイ〜』
シードの燃えるような髪と精悍な容姿はどうしたって誤魔化しようがない。店の客は突然のスターの降臨に息を飲んで
見守っている。もう、存在感が違うのだ。憧憬の視線を一身に集めているのに全然動じていない、あくまでもさりげない
姿は余裕さえ感じられて、いつも一緒にいるクラウスでもドキドキするほど格好良かった。
思わず突っ立ったまま見とれているとシードの目が驚いたように見開かれてこちらに歩いてきた。
「あ、いらっしゃいませ〜」
「お前…いらっしゃいませって、何やってんの。こんなとこで」
「お手伝い」
「お手伝い?」
「あ、クルガンも一緒なんだ」
ニコニコと手を振ってから慌てて言い添えた。
「このお店、マルロの家の人がやってて今日はアルバイトが休みなんだって。だから代わりに手伝ってただけだから」
直後、店は悲鳴のような歓声に包まれた。
「いいのかよ、このままやらせて」
シードとクルガンは他の客の不躾な視線を浴びないようにとマルロが気を利かせて店の奥まった席に案内されてい
た。差し向かいで酒を飲みつつ、二人の視線はどうしてもクラウスを追っていた。
結局デュナンのクラウスと分かってもクラウスは相変わらずオーダーを取りに歩いている。それが客にとって嬉しくな
いはずがないから、引っ張りだことなっていた。
「まあ、本人も楽しんでいるみたいだし、いいだろう」
「優しいじゃん、いつもは煩く言ってるくせに」
「あの事件からこっち、少し落ち込んでいるようだったからな。こんな事でも気分転換になるならかまわんさ」
「フーン…あっ」
酔ったサラリーマンがクラウスの手を握って離さないのが見えた。「握手くらいいいじゃないか」と言ってるのが聞こえ
てきてシードはすっくと立ちあがった。
大股で歩み寄ってきたシードに圧倒されながらも、お酒という強い味方を得ているサラリーマンは少しも怯んでいなか
った。
「悪いけど、その手離してくれないかな」
「なんだよ、お前は」
構わずシードはサラリーマンの手首を掴んだ。
「イテテ」
「こいつ、俺の弟みたいなもんなんだ。あんただって、自分の娘が酔っぱらいに触られてたら嫌だろう」
ちょっと凄みをきかせたシードに、男は「冗談だよ、冗談」と笑って誤魔化している。
「悪いね」
そう言うとシードはそのままクラウスの手を引いて自分のテーブルまで連れてきた。
「気をつけないとダメだろうが」
席に着くなり説教を始めた。
「客も酒が入って気が大きくなってるんだから、ああいうトラブルは自分であしらえるようにしないと店に迷惑がかかるん
だぞ」
「はい」
「客じゃ護身術使って押さえつけるって訳にはいかないからな」
「あ、こういうのが本当のセクハラなんですね」
「そう」
クルガンは吹き出した。説教をしているシードというだけでも可笑しかったのに、クラウスのボケッぷりがツボにはまっ
てしまったのだ。
「もう、お前が心配でゆっくり飲んでられないだろ」
「ごめんなさい」
「ほら、向こうで呼んでるぞ」
「はーい、ただいま」
まだ肩を震わせているクルガンにシードが気恥ずかしそうな顔をして「なんだよ」と突っかかった。
「だって気になるじゃないか。危なっかしいっていうか…あ、そうだ。シュウ呼ぼう」
「え?」
「あいつがいれば見張っててくれるじゃん。そうしたらこっちは気兼ねなく飲めるし。クラウスが酔っぱらいに絡まれてる
って言ったら、あいつ飛んでくると思わない?」
「あまり挑発するなよ」
「分かってるって…あ、シュウ?今飲んでるんだけどさ…」
シュウが来たのは早かった。どこにいたのか知らないが、ほんの10分ほどで来たのにはクルガンも驚いた。だがそ
れ以上に驚いたのはクラウスだった。
「シュウ」
嬉しそうに言ったクラウスの声は、だが店の客の悲鳴だか怒号だか分からない歓声にかき消されていた。
居酒屋灯竜山は混乱の極みにあった。
相次ぐ人気ミュージシャンの登場に客は舞い上がっている。しかもそのうちの一人がオーダーを取りに来るのであ
る。
客の反応に気をよくしたシードは「マイクとカミューも呼ぼう」と言っているし、よく事態が把握できていないギジムとロウ
エンは客の回転が悪いというより、どのグループも居座ったように動かないのを見て「入れ替え制にしようか」などと話し
合っている。コウユウはコウユウで「注文しないんなら帰ってくんな」と言いながら、注文だけして残した客は許さねぇと
息巻いていた。
みんなが熱に浮かされたように騒いでいる中、クラウスは一人取り残されたように重苦しい気持ちを抱えこんでいた。
「クラウス、このヒレ酒、どのテーブルだっけ」
「あそこ。柱の所の」
「あ、あそこか。サンキュー」
片手に料理、片手に酒の乗った盆を持って器用にテーブルの間を縫って歩いているのはシーナである。本当ならシー
ナがいてくれてとても心強いはずなのに、どんどん気分が沈んでいた。どうしてかは分かっている。シーナはシュウと一
緒に来たのだ。
シュウの姿を見たとき飛び上がりたいくらい嬉しかった。なのに、その後ろからひょっこりとシーナが顔を出して、自分
でも笑顔が強ばるのが分かった。シーナが今日会う約束をしていたのは女の子ではなくてシュウだったのだ。その事実
がショックだった。それなのにシーナの言葉が追い打ちをかけた。
「あれ、知らなかった?俺たち結構仲いいの。この間も深夜のドライブしちゃったんだ。ね、シュウさん」
シュウは少し困ったような顔をしてシーナを見ている。
いつも通りに微笑んで「そうなんだ」と言ったけれど、胸の中は嵐のように訳の解らない気持ちが渦巻いていた。
知らなかった?って知るわけがない。シーナとシュウがいつそんなに親しくなったのか、全然気付かなかった。誘拐事
件の時に気安そうに見えたのは、ずっと以前から親しかったからなのかもしれない。
ドライブはシュウの車でしたのかな。やっぱりシーナは助手席に座ったのだろうか。
そう思ったら胸の奥がチクチクと痛んだ。
『そんなの酷い。だってあそこは私の席なのに…』
それが自分勝手な思いこみだというのは分かっていた。それでも「裏切られた」という思いを拭い去ることはできなか
った。二人が親しいからと言ってシーナとシュウを詰るのはお門違いという物だ。だが理性ではそう思っていても、泣き
たいような気持ちはどうしようもなかった。
物凄く変だ。二人が一緒だったからって、どうしてこんな気持ちにならないといけないのだろう。
「クラウス、疲れたんじゃない?」
沈み込んでいるクラウスを気遣わしそうにマルロが見ていた。
「いつもならそろそろ手が空いてくるんだけど、今日は忙しいから。ごめんね」
「ううん、どっちかというと私たちの方がご迷惑をかけてるみたいなのに」
「迷惑なんてことないよ。店が繁盛してくれると凄く嬉しいんだ。姉さんには苦労させちゃってるし」
「苦労?」
「僕って金食い虫だから。学費がね、奨学金を貰ってもうちの大学って授業料高いでしょう」
「うん」
でも授業料のことなどクラウスは考えたこともなかった。
「国立にすればよかったんだけど、どうしてもテスラ先生のゼミに入りたくって」
「そうだったんだ」
今まで自分はとても狭い世界でしか生きていなかったんだ。唐突にそんな風に思った。
「元気ないね。裏に行って少し座ってていいですよ。もうそんなに注文も入らないと思うし」
「平気。これでもライブで結構体力ついたんだから」
二人でクスリと笑いあった。
「疲れてるっていうより、自分があまりにも物を知らないなって思って」
「そんなの、僕だって一緒ですよ」
不思議そうに見たクラウスにマルロは少し赤くなりながら話し始めた。
「今日は僕も色々発見が多かったです。僕、クラウスの伝記を書くなんていってて何も分かってなかったなって。クラウ
スの容姿端麗なところとか、家柄が良くて芸術的な才能にも恵まれていてっていう表面的なことばかりに目がいって、あ
んまりクラウスの内面のこととか考えたことがなかった。本当は僕達と全然変わらない普通の子なのにね」
「ホント?普通に見える?私は一人では何も出来なくてデュナンでもみんなの足を引っ張ってばかりで、全然ダメだって
思ってて」
「全然大丈夫です。そういう不安みたいなのって、きっと僕達みんなに当てはまることなんですよ。だから僕も今度はそ
ういうクラウスの一面をちゃんと捕らえて伝記に取り組んでみようと思うんです」
「伝記って…それ、本気なの」
「もちろんです」
「でも、私の事なんて何も書くことないのに。それならシーナの方がもっと凄い経験してるし」
「シーナ?」
「うん、だってシーナのお父さんってトラン共和国の大統領だよ」
「ええっ」
「3年前の革命の時、シーナも参加していたし」
「ほ、本当ですか」
「うん、ね、シーナ」
シーナが「なになに?」と寄ってきた。
「シーナも革命に参加したんだよね」
「ああ、あれね。大変だったんだよ。オヤジは夏休みだけ参加する革命の戦士なんているかって怒るし、おふくろは危
険だからと思って留学させてるのに何で戻ってくるんだって泣くし。大騒ぎになって困ったよ」
「す、凄いじゃないですか。レパント大統領は現代の英雄ですよ。シーナも革命に参加したなんて凄いなあ」
マルロの目は完全にハート形になっていた。
「ね、だから伝記だったらシーナの方が適任だと思うんだ」
「おい、クラウス。そんなこと言って俺に押しつけるのかよ」
「押しつけるなんて人聞き悪い。本当のことを言ってるだけなのに」
クラウスとシーナが言い争っているとマルロが目をキラキラさせて宣言した。
「是非二人の伝記を書かせてください。人気ミュージシャンと革命の戦士の友情。凄く良い物が書けそうな気がします
っ」
マジかよ、とシーナが情けなさそうな声を出した。
暖簾をしまった後、一通り片づけを終えてからもクラウス達は店に残っていた。
何だかんだと言いながらシーナはマルロの質問に答えて革命の話をしている。シュウとクルガンはワープの曲のこと
で話し込んでいるみたいだ。
クラウスはそっとお盆を持って席を外した。シードが「こっちの方が気楽だ」と言って一人で座敷に座り込んで飲んでい
たから下げる物があれば持ってこようと思ったのだ。シーナの会話に入るのも、シュウの会話に入るのも何となく面白く
なくて、かといってジッとしていると嫌なことばかり考えてしまうから少しでも動いていたかったのだ。
衝立で遮られている座敷をひょこっと覗き込んでクラウスはドキリとした。シードは何かぼうっと考え事をしているらし
い。その横顔がとても寂しそうに見えたのだ。
いつも陽気で元気いっぱい、覇気に満ちているシードのそんな様子を初めて見たから、とても声などかけられなかっ
た。どうしよう、と佇んでいるとシードがフッと笑ってこちらを振り向いた。
「なーにぼんやり突っ立ってンだよ」
そう言うシードはいつものシードだ。けれど、さっきの表情が気になるクラウスは「あの」と言ったきり話の接ぎ穂が見
つからない。こんな時に気の利いた言葉の一つも掛けられない自分が歯痒い。
「こっち来いよ」
言われるまま座敷に上がり込むと「飲むか」と猪口を渡された。
「でも」
「飲んだことくらいあるんだろ」
コックリと頷いた。父が家で飲む時少し付き合うことがある。父が「なかなか強いじゃないか」と言っていたから強い方
なのかもしれない。
「だよなあ。今時飲んだことないヤツなんていないよな」
そう言いながら酒を注ごうとするのでクラウスは慌てて猪口を遠ざけた。
「ダメ」
「あーあ、つまんねぇな。クラウスちゃんは良い子だからな」
その言葉に少し棘を感じて、自分もモヤモヤしていたクラウスはムキになって反論した。
「だって、それで問題になったらみんなに迷惑掛けちゃうんだから。クルガンだって大変になっちゃうし」
シードは少しドキッとした顔をした。
「そうだよな。お前、本当に良い子な」
今度のシードは少し落ち込んでいるみたいだ。一体どうしたんだろうとクラウスはシードの顔を覗き込んだ。
「クルガンがお前のこと可愛がるの当然だよな」
「シード?」
「クルガン、まだシュウと話してたか?」
「うん、ワープの新曲がどうとかって。用事があるんだったら呼んで来ましょうか」
「いい、いい。別に用事じゃないんだ」
そう言ってから自嘲気味に呟いた。
「自分で呼んどいて…するなんて、俺も小さい男だよなあ」
クラウスはまじまじとシードを見た。シードがそんなことをいうとは思わなかった。いつも自信満々のシードにもそんな
負の感情があるなんて思ってもいなかったのだ。
シードはグイッと酒をあおると、手酌でどんどん杯を重ねた。見る間に酒が減っていく。いくら強いといってもピッチが
早すぎるだろう。
「シード、そんなに飲んだらダメですってば。帰れなくなっちゃいますよ。またクルガンに怒られるから」
するとシードの手がフッと止まった。
「俺さ、クルガンがいるからデュナンに入ったんだ」
「シード、酔ってるでしょう。クルガンがデュナンをスカウトしたんでしょ。それくらい私だって知ってます。騙そうとしたって
ダメなんだから」
「バーカ。クルガンは元々デュナンのベーシストだったんだよ」
それは初耳だった。
「すげぇ格好良かったんだぜ。俺、クルガンの側いっつもウロウロしててさ。ホウアンがギターのオーディションさせてく
れるって言った時はホントに嬉しかったなあ。これで一緒にプレイできるんだって思ってたのに…」
でも現・デュナンの最古参はシュウの筈だ。
「シュウは?」
「俺よりちょっと前に入ったんだ。その頃、クルガンが家の事情だか何だかで外れていたから、その間の助っ人ってこと
だったんだけどな。でも結局そのまま戻ってこなかったから」
クラウスは少しドキッとしていた。シードはさっきもシュウを呼んだことを後悔しているようなことを言っていた。
「シード、シュウが嫌いなの?」
「ん?あ、そんな風に聞こえたらごめん。別にシュウが嫌いなんじゃないよ。ちょっと難しいヤツだけど、あいつのプレイ
も好きだし曲も好きだよ」
そう言ってから「はぁっ」と溜息をついた。
「お前にそんな心配させるようじゃしょうがねぇな。こういうところが小せぇんだよな、俺は」
やっぱりシードは酔っているに違いない。クルガンを呼んでこようかと迷っているうちに訳の解らないことを言いだし
た。
「お前たち見てるとやっぱり追いかけさせなきゃダメだと思うんだよ」
「は?」
「でも俺なんて追いかけてばっかだもん。最初っからずっとそうだしさ。負けって決まってるようなもんだよな」
「何が?」
「もう、クルガンなんてさ、俺のことなんかどうでも良いんだよ」
「そんなことないですよ」
よく分からないがシードは酔ってる上に少し落ち込んでいるらしい。だから元気づけようと勢い込んで否定した。
「クルガンはいっつも私たちのことを考えてくれてるじゃないですか。どうでも良いなんて思ってないですよ」
「そうだよな。私たちのことを考えてくれてるよな」
シードは更にどんよりとした雰囲気になっていた。
「カミューとマイクロトフが羨ましいよ。どうやったらあんな風に揺るぎない仲になれるのか、俺には想像もつかないや。
でも、俺がいけないんだろうな。独占したがるから」
本当に、カミューだったらこういう時なんて言って慰めるんだろう。そもそもクラウスはシードが何を言ってるかよく分か
ってないから、気を揉むばかりで口を挟むことも出来ない。
と、俯いていたシードが顔を上げた。
「一度聞いてみたかったんだけどさ。お前の目から見てデュナンの人間関係ってどう思う?」
「どうって…」
もしかしたらクラウスの知らないところで仲が悪いんだろうか、と心配になってきた。
「誰と誰ができて…じゃなくて仲良いか、とか分かる?」
取り合えず、仲が悪い話ではないんだとホッとした。
「えっと、みんな仲良いですよね」
「その中で、特に気付いたのある?」
「特に、ですか?」
クラウスは少し考えた。
「えっと…マイクとカミューは仲良いですよね。一緒に住んでるし」
「ええっ、そ、そうなのか?」
シードがガバッと顔を上げたのでクラウスは驚いた。
「同じマンションに住んでるって言ってましたよ」
「マンションだろ。ああびっくりした。それは知ってるよ。一応部屋は別だからな、あいつらも」
「そうなんですか。同じマンションなら一緒に暮らした方が経済的ですよねえ」
「…お前って、時に大胆だよね」
「?」
「まあ、いいや。後は?」
後と言っても残っているのはシードとシュウとクラウスである。何と答えたものか困ってしまった。するとシードは意味あ
りげに笑って聞いてきた。
「シュウは誰だと思う?」
「シーナ」
何故か自然と口から出て、その自分の言葉にクラウスはズーンと落ち込んだ。だが、シードは目を丸くして、それから
爆笑した。
「報われないなー、あいつも」
落ち込んでいるところにあんまり笑われたのでクラウスもムキになった。
「シードはクルガンと仲良しですよねっ」
「…そう?」
「そうですよ。今日だって一緒だったしっ」
「それは、俺が誘ったからだよ」
「でもシードの言うことならクルガン何でも聞くしっ」
「それは俺が我が儘言うから、しょうがなく…」
「いっつもシードを見てるしっ」
クラウスはプンプンして言ったのだが、シードは真顔で固まっていた。
「嘘言うなよ」
「嘘じゃないですっ。最初にデュナンのライブを見せてくれたときだってクルガン、ずっとシードのこと見てましたもん。だ
からクルガンはシードのことが大事なんだなって思って」
「すいません、今のところをもう一度」
「え、今のところ?…嘘言うなよ?」
「それは俺が言ったんだ」
「えっと、んーーー」
「だから、誰が誰を大事にしてるって?」
「…クルガンがシード」
「そうかあ」
シードはニカッと笑うとクラウスをギュッと抱きしめた。
「ほんとーに可愛いぞ、お前」
クラウスはギュウギュウと抱きしめられて苦しくてジタバタと藻掻いていた。
「よーし、お兄さんは気分がいい。今夜はお前の言うこと何でも聞いてやるぞ」
「いいですよ、そんなの。それよりちょっと、離してくれませんか」
だがシードは額と言わず頬と言わずキスの嵐をふらせている。ああもう、とクラウスは諦めてされるがままになってい
た。大体、酔っぱらいをまともに相手にしても無駄なのだ。ずっと父を見ていてそれだけはよく分かっているクラウスで
ある。
「何したい?寿司食いに連れてってやろうか」
「いいから離してください」
髪をグシャグシャと掻き回されていい迷惑である。
「よーし、じゃあ焼き肉にするか?」
その時ハッと閃いた。
「夜のおもちゃ、教えてください」
耳元で囁くとシードが唖然とした顔をした。
「まだそんなこと言ってるのか?」
「だって誰かに聞くのもなんだか」
「そりゃ、そうだな」
少し考えてからシードは意外なことを言った。
「シュウは教えてくれなかったのか?」
「シュウ?ううん、もうその話はするなって」
「ばっかだな、あいつ。つけこんじまえばいいのに」
「つけ込む?」
「ああ、気にするなって。じゃあ、お兄さんが教えてやろっか、手取り足取り」
「はいっ♪」
嬉しくて返事をするとシードは心底呆れたという顔をした。
「あのなあ、お前分かってんの?」
「だからっ、分からないから聞いてるんでしょっ」
「こら、そんな大きな声出すなって。ムードがなくなる」
「ムード?」
「そ、大体お前、天下のシード様とこんなくっついていて何ともないわけ?」
「何が?」
キョトンとしていると「ちょっと傷つくなあ」とシードが苦笑した。
「たとえばさ、キスしたいなーとか思わない」
「全然。大体さっき散々…」
「こーら、お兄さんを怒らすんじゃない。ホントにおもちゃにしちゃうぞ。後悔するなよ」
「え?」
グイッと体重を預けられてアッという間に畳に押し倒されてしまった。いつもと角度が違うせいかシードが違う人に見え
る。しかもその顔が徐々に近づいてきてクラウスは焦った。
「ちょ、ちょっとシード、酔ってるでしょ、シードッ、わーーーーっ」
「お前らさっきから何を騒いで…」
次の瞬間、すごい勢いでシードが引き剥がされた。
「「何をやってるんだっシードッ!」」
クルガンとシュウの怒号が響いた。
「ちぇっ、なんで二人とも俺のことばっかり」
「お前が原因作っているんだろうがッ」
クルガンが怒鳴りつけ、シュウが「何をされた?」とクラウスに問いただしてきた。
「何にもしてないって、まだ」
「まだって言うのは何なんだっ」
「煩いよ、クルガン」
「全く、少し目を離すと好き勝手なことばかりして」
「わーったって。それよりクラウス、続きはちゃんとシュウに教えてもらえよ」
シードにウインクされて戸惑いながら見上げると、緊張した面もちのシュウと目が合ってしまった。
「シュウ、クラウスに優し〜く教えてやれよ」
「いい加減に死ろっ、お前は」
とにかく先に失礼する、とクルガンはシードを引きずるようにして帰っていった。きっと物凄くクルガンに怒られるだろう
にシードはなんだか嬉しそうだった。
帰りはいつものようにシュウの車である。が、ここにシーナも座っていたのだと思うとなんだか気が晴れない。
『別に私が特別ということはないんだ』
それが寂しい。
クラウスの中では「夜のおもちゃ」については、もうどうでも良くなっていた。いくら鈍いクラウスでも、あそこまでシード
にされたらどうやらセックスと関係のあることらしいということは気がついた。だからみんな困ったり怒ったりしていたの
だろう。
だから、それはもういい。それよりシーナの事の方が大問題だと思っていた。
「シュウさんが可哀想じゃん」
あの騒ぎの後、いきなりシーナはそう言ったのだ。
「そりゃ、相手を振り回した方が勝ちって俺も言ったよ。けど、あれはやり過ぎだって。あんまり調子に乗ってると見放さ
れるぞ。大体、人の気持ちを踏みつけにするなんて、お前らしくないよ」
シーナはかなり怒っているみたいだった。
「調子に乗ってる訳じゃ」
「分かってる。お前は全然意識してないでやってるんだろ。でもそれってもっと罪が大きいっていうことは分かってた方が
いいと思うぞ」
何でシーナにこんなに怒られなければいけないんだろう。何で私はシュウの事が何も分からないのにシーナはなんで
も分かっているんだろう。
惨めな気持ちでいるクラウスに、シーナは更に意外なことを言った。
「シュウさん、今日全然お酒飲んでないだろ。きっとクラウスのこと送っていこうと思ってるんだよ。だから早く一緒に帰り
な」
「え?」
それからシーナは叱られてしょんぼりしているクラウスの代わりに「シュウさーん、クラウスのこと送ってやってよ」と声
を張り上げたのだった。
シーナが何を考えているのか、クラウスには全然分からない。
それに、本当はシーナに叱られたことよりも「見放されるぞ」という言葉が堪えていた。見放されるということは嫌われ
るということだろう。
シュウに嫌われる。それだけはイヤだ。断じてイヤだった。
「どうした?疲れたのか」
ずっと黙りこくっているクラウスにシュウが心配そうな声をかけた。
「シーナ、置いてきちゃったね」
「そんなことを気にしていたのか。あいつなら大丈夫だろう。あの近くに友達のマンションがあるらしい。居酒屋を手伝っ
ていたのも友達が帰ってくるまでの時間潰しみたいだし」
「そうなの?」
「電話の様子から察するにな」
そうか、今日一緒だったから知ってるんだ。
「シュウってシーナと仲良しだったんですね。知らなかった」
「仲良しって訳じゃない」
「でも、今日も一緒だったんでしょう」
「あ、あぁ、まあ…」
何故かシュウは言葉を濁して、それきり会話は続かない。気詰まりな沈黙のままマンションに着いてしまった。
「今日はありがとうございました」
そそくさと降りようとしたクラウスをシュウが慌てて引き留めた。
「その、ちょっと、これを持っていけ」
後部座席から何やら包みを取り出した。
「これ、何ですか?」
無造作にグイッと押しつけられた箱は綺麗にラッピングされている。
「気に入らなければ捨ててもいい」
怒ったような顔でシュウは言ったが、これはどう見たってプレゼントだろう。少なくとも、こんな大げさにリボンの付いて
いる物をプレゼント以外で貰ったことはない。
「え、でも、誕生日じゃないのに」
「だから、いらなければ捨てても」
「そんなっ、捨てたりなんてしませんっ。開けてみてもいいですか?」
「ああ」
ぶっきらぼうな中にどこか恥ずかしそうな響きの混ざった返事を聞いてクラウスはいそいそとリボンをといた。
「可愛いっ!」
箱から出てきたのは真っ白なテディベアだった。
「お前のは近所の子にあげたと言っていただろう。だから」
「それを覚えててくれたんですか」
「ああ、まあ。しかし、いろんな種類があるんで驚いた。ぬいぐるみのブランド物なんて聞いたことがなかったぞ、俺は。
それにしてもシーナはこの手のことには詳しいな。どこの店の何がどうだとか、俺にはさっぱりわからん」
何も聞いていないのに一人で喋り続けるシュウを余所にクラウスはテディベアを抱きしめていた。
「この子はシュウが選んでくれたんですか」
「そうだ」
「ありがとう、シュウ」
今までの不安も何もかもがいっぺんに吹き飛んで、クラウスの長い一日は最高の終わりを迎えたのだった。
そして…。
極上の笑顔と共に胸に飛び込んできたクラウスを抱き留めながら、どうして俺はここで理性が飛ばないのだろうとシュ
ウは己のクールな性格を少しばかり呪っていた。
が、まあいいだろう。少なくとも二人の間にあった距離が大分縮まっていることは確かなようだから。
fin.
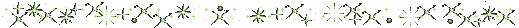
『愛と青春の日々』は一応これで完結です。
なのに最後に何ともお目汚しの物をお見せしてしまってすみません。
やっぱりおまけは付けない方が良かったかもと反省しています。
そもそも『愛と青春…』で最初に決まっていたのは
ラウドの話で始まりラウドの話で終わるということだけでした。
それに居酒屋のシーンを付けて
最大の目的はシュウがクラウスにテディベアをプレゼントするという
それだけの話だったのです。
ところが書いているうちに、メインの筈の居酒屋話がどこかへ飛んでしまい
テディベアのての字も出てこない誘拐話になってしまったのです。
正直書いている海棠が一番びっくりな展開でした。
なので、ついおまけに拘ってしまったのでした。むう…
いずれにせよここまでお付き合いくださってありがとうございました。
次週は外法帖発売記念(は?)デュナンの企画物が1本入る予定です。
お心の広ーい方がいらしたら、お待ちしておりますので是非…
それにしてもいつの間にやら仲良しトリオ。
トニーの立場は一体…(笑)
なのに最後に何ともお目汚しの物をお見せしてしまってすみません。
やっぱりおまけは付けない方が良かったかもと反省しています。
そもそも『愛と青春…』で最初に決まっていたのは
ラウドの話で始まりラウドの話で終わるということだけでした。
それに居酒屋のシーンを付けて
最大の目的はシュウがクラウスにテディベアをプレゼントするという
それだけの話だったのです。
ところが書いているうちに、メインの筈の居酒屋話がどこかへ飛んでしまい
テディベアのての字も出てこない誘拐話になってしまったのです。
正直書いている海棠が一番びっくりな展開でした。
なので、ついおまけに拘ってしまったのでした。むう…
いずれにせよここまでお付き合いくださってありがとうございました。
次週は外法帖発売記念(は?)デュナンの企画物が1本入る予定です。
お心の広ーい方がいらしたら、お待ちしておりますので是非…
それにしてもいつの間にやら仲良しトリオ。
トニーの立場は一体…(笑)

