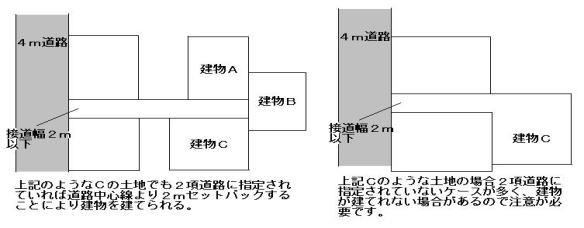| 市街化区域と市街化調整区域 |
1967年に新都市計画法の規制に際して、都市開発の無秩序な拡大を避けるために、市街化地域と市街化調整区域の区別がされました。市街化区域は市街地を積極的に整備する区域で、規制に則って各種の建物を建てることができるが、市街化調整区域は当面の市街化を規制するもので、原則的に建物を建てることはできません。ただ、最近の規制緩和、景気対策の必要性などから市街化調整区域にも住宅などを建設できるようにすべきだという考え方も強くなってきています。 |
| 国土利用計画法による監視区域制度 |
1974年に制定された国土利用計画表は、これまで自由に売買されていた土地取引に制限を加えたもので、規制区域を設定してその区域内の取引を規制し、一定規模以上の取引は許可制とする、遊休土地で活用されない土地の利用を促進し、受け入れられない場合には収容できる。ただし、これまでに規制区域は設定されたことがなく、バブル期に規制区域よりゆるやかな監視区域が実施された程度でそれも現在ではほとんど撤廃されています。 |
| 用途地域規制 |
都道府県知事や区市町村長が指定する都市計画区域内の線引きのことで、指定された地域ごとに、どのような建物が建てられるのか、どのような建物は建てられないのか、土地に対してどの程度の広さの建物がたてられるのかなどが決められています。また用途地域にによる建ぺい率・容積率は、豆知識の建ぺい率と容積率を参考にしてください |