和船の海運
徳川初期の海上交通
海上交通は陸上輸送と比べるとはるかに効率的なため古代から発達したが、西日本では瀬戸内海を中心に活発であった。戦国時代、大名は兵船や物資の輸送船をつねにある程度確保していなければならなかったが、常時保持するよりも緊急時に造船資材や船大工を調達・徴用できる体制を確立するほうが、はるかに効率的であった。このため、しばしば領国内での竹木伐採の禁止令が出された。また、戦時・平時にかかわらず民間から船舶を徴用することはしばしば行なわれ、しかも舟持には帆役などの課税もあった。船賃についても強い統制があり、業者が自由に運賃を決めることはできなかった。舟方に対しては、逃Sを防止するために船舶や家屋敷の売買を禁止して人員の確保に努めていた。
なお瀬戸内海では、中世以降、海賊による被害が続出したが、秀吉の天下統一以後は減少した。さらに1585年(天正13)には四国遠征が行なわれ、伊予、来島、阿波の海賊を従属させた。88年には海賊禁止令が出され、船頭や漁師から誓詞を取って海賊行為をやめさせた。海賊たちはその後、秀吉に従い、小田原遠征、文禄・慶長の役には大いに活躍した。
戦国時代の商船
都市が発展するにつれて生活物資の流通が増大すると、経済性の高い海運が大きな比重を占めていった。使用された船は帆走性、操櫓性、海底の深浅に応じた船底構造など、地域によってさまざまであった。瀬戸内方面では二形船、弁財船、押回し、九州ではアダテ、伊勢地方では伊勢船、北国地方では北国船、羽賀瀬(はがせ)、間瀬(まぜ)などの船があり、船型や構造はそれぞれ異なった。これに五大力(ごだいりき)、イサバ、猪牙(ちょき)といった小型船を加えるとその種類は相当な数にのぼった。
二形船は末期遣明船の形と構造を持つもので、軍用船の艤装を施せば安宅船(あたけぶね)に転用できた。「二形」とは、船首上部が箱形で、それにつづく下部が鋭角の水押(みよし)造であることからそう呼ばれた。中世末期から近世初期にかけて、大型回船の代表的存在として瀬戸内をはじめ、九州、伊勢、関東まで幅広く活躍した。
弁財船というのは「ベザイ」の当て字とされるが、本来の意味は不明である。二形船の発展した形であるが、船首以外、基本構造はほとんど変わらない。文禄・慶長の役のさいに毛利、島津、鍋島などの大名が準備した荷船の大半も、弁財船であったとみられる。また、江戸−大坂間の海運で活躍した菱垣(ひがき)回船や樽回船なども同様であった。
古くから海運・造船の中心地のひとつであった伊勢地方では、伊勢船と呼ばれる船が活躍した。これも二形船と同じく、艤装すれば安宅船となり、文禄・慶長の役には多数が建造されたが、堅牢性には定評があった。
近世前期、北陸・東北地方の商品は小浜・敦賀を経由し、琵琶湖の水運によって畿内に運ばれた。とくに桃山時代の築城をはじめとする建設ブームの時には、大量の木材が東北から運搬された関係から日本海ルートが発達し、北国船、羽賀瀬船が主力となって活躍した。冬期の日本海は波浪が高いため、鋭い波に船首を突っ込まない予備浮力を備えた幅の広い船首を持ち、多少岩礁に接触しても破損しない頑丈な船底を持っていた。
徳川初期の海上交通
戦国時代から桃山時代にかけては、東南アジアを中心に海外との航路も開けていたが、江戸幕府の鎖国政策の結果、海外進出は途絶えることとなった。その一方、石高制の成立、参勤交代制の強化といった中央集権的政策の実施に伴い、大坂・江戸への海上交通が盛んとなった。さらに各地の城下町・港町と江戸・京都・大坂の三都を結ぶ商品流通のネットワークが形成され、商品の海上輸送が頻繁となった。
1616年(元和2)には、江戸に出入りする回船を査察する機関として伊豆の下田に海関を設けて下田奉行が置かれた。こうして幕府は東海、関西および四国方面からの舟の出入りをチェックして海上交通を掌握したが、やがて東海地方、瀬戸内地方にも及んだ。瀬戸内では、かつて海外貿易の拠点であった堺が、1604年(慶長9)の大地震で壊滅的打撃を受けたこともあり、大坂が海運の中心となった。こうして大消費地江戸へは、天下の台所と言われた大坂が最大の供給基地となり、菱垣(ひがき)回船や樽回船が輸送を行なった。菱垣回船の起源は1619年(元和5)、堺の商人が紀州富田浦から250石積の回船を雇い、大坂で木綿、油、綿、酒などを積み入れて江戸まで海上輸送したことに始まる。以後、大坂―江戸間の大動脈として定期化された。
なお、日本海の北国海運は古くから発達して、近世初頭も畿内への中継基地である敦賀、小浜には船持豪商が輩出し、遠隔地間の商品輸送と販売をとうして海運を支配していた。
千石船
江戸時代に入ると、幕府によって国の文化と宗教を守るために鎖国令が出され、海外渡航が禁止されます。貨物船も海外まで渡航できないようにその大きさを制限されていました。外国へ行くことができなくなり、船も大きなものを造ってはいけないことになったことで、日本の航路はもっぱら沿岸航路の時代へと入っていきます。
出羽、北陸方面の御城米を下関回りで江戸へ運ぶ西廻り航路と、酒田以北の荷を三陸沖を通って江戸へ運ぶ東廻り航路などが名を残しています。この沿岸航路のために造られた船に通称「千石船」と呼ばれる船がありました。長さは23mと大きな船ではありませんでしたが、米を千石(約18万リットル)積めることからそう呼ばれたのです。構造は船底が平らで竜骨がなく、1本の帆柱に横帆が1枚というシンプルなものでした。しかし、帆の大きさ(反数)と櫓の数が多く、積載能力が大きかったため実際には1500石にも達するものが生まれたといいます。
弁才船
今日、千石船と俗称される弁才船は、中世末期から瀬戸内海を中心に発達した商船で、江戸時代前期以降、国内海運の主役として活躍しました。
弁才船は細かくて見てゆくとさまざまです。例えば大坂から江戸に日用雑貨を運んだ菱垣廻船(ひがきかいせん)は、胴(どう)の間(ま)に荷物を山積みするために舷側(げんそく)の垣立(かきたつ)が高く、菱垣廻船から分離独立、して酒荷を主に運ぶようになった樽廻船(たるかいせん)は重い酒樽を船倉に積むため船体が深くなっているといった具合です。また、地方的な特色ある弁才船も多く北前船(きたまえぶね)〔北前型弁才船〕はその代表例です。
明治時代になると、洋式帆船の影響を受けて折衷化(せっちゅうか)した弁才船が登場します。いわゆる合の子(あいのこ)船と呼ばれた船で、こうして弁才船はその後も活躍を続けました。

弁才船(薩摩形)(1987.7.24 船の科学館)

北前船(1987.7.24 船の科学館)
弁才船の帆装
弁才船は、船体ほぼ中央に大きな帆を上げていて、これを本帆(もとほ)といいます。船首には弥帆(やほ)と呼ばれる小さな帆もありますが、弁才船は1本帆柱の船と見るのが一般的です。弁才船の帆は中世以来の伝統的な形式を引き継いでいますが、下の帆桁(ほげた)を取り去り、帆の下を綱(つな)でとめて十分なふくらみがつくように改良されました。江戸時代の後期になると帆走性能を少しでも上げようと、船首や船尾に小さな帆と帆柱をさらに増設した船も現れます。弁才船の帆の取り扱いは、洋式船のように帆柱や帆桁に人が登る必要がなく、船上で操作できるのが特徴でした。重い帆桁の上下も、帆柱の先端の蝉(せみ)とよばれる滑車を通して船尾に縄を通じ、轆轤(ろくろ)と呼ばれる人力の巻き上げ機を使って船内から行いました。帆桁の方向は桁の両端につく手縄(てなわ)と呼ばれる縄を、帆のふくらみは帆の両脇につけた両方綱(りょうほうづな)と呼ばれる綱を操作して行いました。
弁才船の性能
弁才船は順風でしか走れないとよくいわれてきましたが、そんなことはありません。横風帆走を意味する「開(ひら)き走り」や逆風帆走を指す「間切(まぎ)り走り」といった語は、すでに17世紀初頭「日葡辞書」に収録されています。弁才船の逆風帆走性能は、ジャンク(中国船)やスクーナ―型などの縦帆船(じゅうはんせん)に比れば劣りますが、バーク型などの横帆船(おうはんせん)より優れていました。弁才船の耐航性と航海技術の向上した江戸時代中期ともなると、帆の扱いやすさとあいまって風が変わってもすぐに港で風待ちすることなく、可能な限り逆風帆走を行って切り抜けるのが常で、足掛け4日も間切り走りを続けた例もありました。
弁才船の建造
1.造船は、海岸または川岸の造船に適した傾斜地(けいしゃち)をつき固め、輪木(りんぎ)を埋め込んでその上で行います。輪木とは、腐食(ふしょく)しにくいクスやクリなどで作られた造船台のことです
2.航(かわら)(船底材)は胴航(どうがわら)と艫航(ともがわら)よりなり、胴航の先端に水押(みよし)(船首材)をつけ、艫航の後端には幅の広い戸立(とだて)(船尾板)を取り付けます。
3.航に根棚(ねだな)を取り付け、上縁に下船梁(したふなばり)を入れて固めます。根棚は航とともに堅固な船底部を構成する重要な材なので、棚板のうちで最も厚く、航の暑さの半分(50〜70%)あまりもあります。
4.根棚に中棚(なかだな)を取り付け、上縁に中船梁(なかふなばり)を入れて横張力をもたせます。中棚は水押との結合部で垂直になるので、ねじれが大きく、そのため三の間あたりから前を2〜3階造りにしています。これを四通り(よとおり)といいます。
5.中棚に上棚(うわだな)を垂直に近いくらいに立てて取り付けます。上棚は最も長い棚板なので、500石積以上の船では船首側と船尾側に分けて、船体中央の腰当(こしあて)部で重ね継ぐのが通例です。
6. 同程度の厚さの除棚(のけだな)(舷側板(げんそくばん))を外側に重ねて補強した上棚の上部に横張力用の上船梁を入れ、舷外に突き出た上船梁の端を台(だい)(太い角材)で連結して船体強度を高めます。船体中央部に垂直に立つのが帆柱を支える筒と筒挟み(つつばさみ)です。
7. 上棚の上縁にほぼ垂直にハギツケをはぎ合わせ、前部に合羽(かっぱ)(甲板)を張りつめます。18世紀中期に普及するハギツケと合羽(かっぱ)は、耐航性の向上と積載量の増大に大きな役割を果たしました。船首近くに垂直に立つのが、帆柱を倒したときの受けとなる舳車立(おもてしゃたつ)です。
8.台の上に垣立(かきたつ)を立てます。舳(おもて)垣立は艫(とも)垣立よりも低くし、胴の間の上部を取り外して、荷役を行うとともに、空船のときには伝馬船(てんまぶね)を搭載します。艫垣立の上に張る屋倉板(やぐらいた)は、操舵(そうだ)や操帆(そうはん)を行う作業甲板であると同時に乗組員の居住兼作業区画の屋根の役割を果たします。
9. 棚板の上に保護用の薄い包板(つつみいた)を張れば、船は完成します。船卸(ふなおろ)しのため船を手木(てぎ)で持ち上げ、下輪上面の上輪を取り外し、水際まで敷き並べた修羅板(しゅらいた)(堅木の板)の上にカシのコロを多数おいて船をのせます。
10. 船から沖の碇(いかり)にしかけた滑車(かっしゃ)に綱をとって轆轤(ろくろ)でまきながら徐々に船を動かし、船卸しの当日、船上から撒銭(まきぜに)・撒餅(まきもち)をふるまい、船を水に卸して船主と船頭以下の乗務員が乗って乗初めを行います。
弁才船の用語
航(かわら):敷(しき)ともいい、船首から船尾まで通す平らな船底材
水押(みよし):船首に付く材戸立(とだて):船体後面を構成する幅広い板
根棚(ねだな):かじきともいい、航の両側につける最下部の棚板
中棚(なかだな):根棚の上に大きく開いて取り付ける幅広い船底材
上棚(うわだな):中棚の両側に垂直に近く立てて取り付ける舷側板
ハギツケ:上棚の上べりにほぼ垂直にさらにはぎつける舷側板
下船梁(したふなばり):左右の根棚の開きを保ち、かつ横張力をもたせる梁
中船梁(なかふなばり):中棚の上部に入れる横張力用の梁
上船梁(うわふなばり):上棚の間に入れる横張力用の梁、上棚の外側に突き出している
台(だい):上棚から外に張り出した梁を連結して上に置いた長い角材
垣立(かきたつ):船体の舷側の台の上につく格子組みの欄干状のもの、装飾的要素が強い外艫(そとども):戸立より後の部分、船体後の流れを整え抵抗減少と舵の効きを良くした
屋倉(やぐら):腰当船梁から床船梁までの後部甲板上を占める船室
帆柱(ほばしら):取り外しができるのが特徴で、後に細い柱を何本も束ねて鉄のタガをはめた松明(たいまつ)柱が主用された
帆桁(ほげた):帆の上部に付ける円柱の材、両端に向かって細くなっている
舵(かじ):船の方向を定める板、和船は取り外し式になっていて引き上げることができる
菱垣新綿番船
新綿番船とは、大坂周辺で秋にとれた新しい木綿を積み込んだ菱垣廻船によるスピード・レースのことで、江戸十組問屋成立の元禄7年(1694)から明治時代初期まで行われました。
大坂を出帆し、ゴールの浦賀への到着の順番を競ったことから当時は番船を「ばんぶね」と呼んでいました。新締番船はその順位が賭(か)けの対象となるほど人気を集めた華々しい年中行事でしたが、単なる競走にとどまらず、その年の新しい木綿の値段を決めるという重要な役割もあわせ持っていました。
船頭達は少しでも早くゴールしようと航海や帆装に工夫をこらしたので、幕末の安政6年(1859)には1着の番船の所要時間が50時間(平均速力7ノット/時速13キロメートル)との大記録も達成されました。
含粋亭芳豊(がんすいてよしとよ)作の「菱垣新綿番船川口出帆之図」と題された三枚続きの錦絵には、切手を安治川岸に臨時に設けた切手場に受取りに来た船頭の乗る上荷船(うわにぶね)と、それを見物する多数の屋形船や川岸の群衆のお祭り騒ぎを中央に、右上方に安治川口の天保山(目印山)沖に碇泊する7隻の番船を描いたもので、当時のにぎわいが伝わってくるような、臨場感のある錦絵です。

檜垣廻船(1987.7.24 船の科学館)
河川交通
近世になって、河川交通は著しい発達をとげて物資輸送の大動脈となった。量的には海上輸送のほうが大きいとはいえ、港湾にいたるまでは河川の利用が多く、海上輸送の活況が河川交通のさらなる発達をうながした。信長、秀吉による天下統一により、政治経済圏が拡張されるとこの傾向はますます進んだ。
平安時代より交通路として発達していた淀川沿岸の船着き場はひじょうに繁栄したが、なかでも淀は諸国より到来した商品の陸揚場として、交通・商業の中心地となった。また当時活躍した、大山崎の油商人たちも舟運を利用し、いわゆる過書船(かしょぶね)として淀川を上下した。
このほか、流入する河川では木津川、宇治川、保津川、高瀬川などが舟運で賑わった。保津川(大堰川)は、1606年(慶長11)に角倉了以(すみのくらりょうい)によって開削されたもので、丹波方面からの物資輸送に大きな役割を果たした。また了以が作った高瀬川は、京都市内から伏見にいたる運河であるが、もっとも利用度の高い河川のひとつとなった。

高瀬船(1987.7.24 船の科学館)

舟帯船(1987.7.24 船の科学館)

五大力船(1987.7.24 船の科学館)
⇒ 船鑑
徳川初期の河川交通
河川を利用して人や物資を運送する方法は、原始・古代にまでさかのぼることができるが、もっとも盛んになったのは近世で、徳川家康の天下統一後である。江戸・大坂の二大都市を中心に、全国的な経済流通の発展に伴って幕府、諸藩の年貢米や各種物資をきわめて安く、しかも大量に運送できることから全国的に発達したものである。
主要河川に就航していた川船は船底の平たい高瀬船と、それによく似た_舟(ひらたぶね)で、両船ともかなり大量の荷物を積んで帆走することができた。高瀬舟の最大級のものは船長約26メートル強で、積載量は米1200俵という記録もある。_舟の場合は、船長約24.4メートル、積載量は米500俵ほどであった。
1590年(天正18)、江戸へ入城した徳川家康は、関東郡代に命じて関東の河川整備に着手したが、とくに大規模であったのは利根川と荒川の改修工事であった。これにより江戸と関東・東北・上信越方面の農村とを結びつける河川交通網が形成され、水運発展の契機となった。
また、畿内では淀川の水運の重要性に着目し、1603年(慶長8)には運上金の上納や運賃などに関する七カ条を定めた。1625年(寛永2)に230艘であった淀二十石船は、数年後には500艘にも達し、当時の盛況振りがうかがわれる。また、古くから大坂市内には縦横に水路が走っていたが、文禄年間(1592年〜96年)には上荷船・茶船が頻繁に活動していた。1673年(延宝元)には新規に出願する者がいて、前者が300艘、後者が200艘追加公認されたほどであった。
淀川の舟運
京都と大坂、さらに瀬戸内海を結ぶ淀川には、中世以来、山崎胡麻船、石清水(いわしみず)八幡船、淀船、伏見船などが就航していた。なかでも石清水八幡に属した淀船は、淀川だけでなく木津川、宇治川の独占権を握っていたが、信長入京後はそれまでの二十石船のほかに、大型の三十石船も許可された。秀吉の朝鮮出兵のさいには徴用されたが、そのころには100艘ほどが運行していたらしい。
その後、宇治川の水流変更によって伏見港が建設されて舟運は一段とよくなり、1598年(慶長3)には朱印状が与えられた。なお、このとき「過書船(かしょせん)」という名称が与えられ、旧来の淀船もこのなかに組み入れられた。ちなみに過書とは、中世において河関通行税免除の特権を意味する。過書船には積荷の種類や運行区間によって、人乗せ三十石船、天道船(てんとせん)、青物船など数種類あった。人乗せ三十石船というのは、28人乗りで船頭4人というのが規則で、ふつう一日二回、大坂−伏見間を往復した。これらの旅客を目当てに、枚方(ひらかた)では「くらわんか船」と呼ばれる家康公認の船が、餅や寿司などの食物を売ったことは有名である。
なお、関ヶ原の戦では東軍に味方し、淀・伏見の情報を家康に伝えた功績により、1603年(慶長8)再度、朱印状が交付された。さらに、大坂冬の陣では淀の二十石船が前面的に協力し、生命の危険をかえりみずに戦場近くまで運行したが、動員された船は延べ3560余艘、船頭7220余人を数えたという。
木曽川の舟運
木曽川の幹流がほぼ現在の形に固定されたのは、1586年(天正14)の大洪水以後のことである。それ以前の本流は、犬山の対岸・鵜沼から西流して長良川に合流し、墨俣(すのまた)・桑名を経て伊勢湾に流れ込んでいた。従って、それ以前は境川と呼ばれ、木曽川と称したのは天正以後のことである。木材資源の流通路として開けたのは古く、13世紀にはすでに記録に現れている。
近世初期は城と城下町の建築ラッシュで、岐阜城をはじめ江戸・名古屋城などの建設に用いる大量の木材が必要となった。豊臣・徳川両家は全国の土地を把握するとともに、有力な山林を直轄支配したが、とりわけ木曽は重要な位置を占めていた。豊富な木材を江戸や畿内に運搬するのに、木曽川を使用すると容易であったからだ。
豊臣秀吉の時代、木曽の木材は美濃の墨俣などから陸揚げされ、琵琶湖畔の朝妻まで陸送、そこからは船積みにして京都まで運搬された。もともと木曽川は軍事上の目的から、兵器類と負傷兵の通行、夜間の通船、徒行渡り(かちわたり)などは許可されていなかったが、徳川家が実権を掌握した元和以後、さらに厳しく取り締まった。このような情勢によって木曽川の舟運は発達しなかったため、岐阜・加納・笠松および飛騨方面とを上下する荷は、飛騨街道を利用した。また、名古屋と東濃・木曽との間の荷物は、小牧街道から中山道を利用するほかなく、これにより陸上輸送と継荷問屋の発達がうながされた。
長良川の舟運
下流の墨俣で木曽川に合流していた長良川の上流(郡上川)には、美濃紙の産地とその集荷市場である上有知(こうずち)・大矢田を控えていた。美濃紙は上有知湊で船に積まれ、墨俣・近江を経由して畿内に出荷された。紙のほかには茶、あずき、柿、たばこ、干し大根、木綿、荏胡麻(えごま)などが、岐阜やさらにその下流地域へ船で運ばれた。また、檜、けやき、杉、松、栗などの丸太や角材、板などが船や筏で川下げされた。
現在の美濃市港町にある上有知湊は、郡上八幡と桑名(三重県)と結ぶ重要な通り筋であったが、特に岐阜との間の便が盛んであった。また、近世になっても伊勢参りの旅人が利用した。この川湊は金森長近の時代に開け、番船40艘を造らせて地方物資の輸送と集散に当たらせた。
長良川の舟運を管理する役所が、いつ頃から設けられていたのかたしかなことは不明であるが、1592年(天正20)岐阜城主織田信秀が、中流にある鏡島湊が遡上荷船の最終湊であることを保証する文書があるので、のちの「長良川役所」に相当するものがすでに存在したことは間違いない。桑名・揖斐川を経由して加納城下、岐阜方面へ登る荷物は、すべて鏡島湊で荷揚げして陸送されていたのである。なお、関ヶ原戦後は徳川家康の支配下となり、元和以後は尾張藩の支配下に入った。
揖斐川(いびがわ)の舟運
揖斐川(久瀬川)は、木曽三川のなかで西に位置し、他の二川と同様に交通・運輸に大きな役割を果たした。往来の拠点となったのが、北方(きたがた)や房嶋(ぼうじま)などの現在の揖斐川町である。輸送物資のなかでもっとも多いのは「つだ」と呼ばれる燃料用の薪材で、上流の徳山や坂内(さかうち)方面から伐りだされたが、徳川政権以後も大垣藩の重要な財源であった。
1580年(天正8)織田信忠は掟書を下し、揖斐川の渡船場である呂久(ろく)の諸役を免除しているが、この文面からすでに桑名との舟運が開けていたことがうかがわれる。1594年(文禄3)、秀吉の代官・古田織部は、荷船と材木・薪炭に「久瀬川六分一役」という税を課しているが、この頃すでに相当数の荷物が往来していたようだ。なお、揖斐川の湊では五十石から百石級の大型船が就航していたことが注目される。しかし関ヶ原戦後、中山道の一大拠点であった大垣に水運が開け、70軒の船町を形成するにいたって、それまで揖斐川の三湊を経由していた船荷までが大垣に集中するようになり、徐々に衰退へと向かっていった。
琵琶湖
近江は畿内と関東や東北、また裏日本や表日本を結ぶ要衝にあり、全国の主要交通路が集中的に集まっていたが、その中心にある琵琶湖はとくに重要であった。京都にのぼり天下統一を号令しようとする戦国武将にとって、近江を掌握することは避けることのできない関門であり、琵琶湖の交通を手中に収めることは必須の条件であったからだ。
当時、日本海側の敦賀に陸揚げされた北陸・東北の物資、また東海方面から中山道を経由して運ばれた物資は、すべて琵琶湖畔に運ばれて湖上を通り、いったん陸揚げされて京都・山科を経由して淀川を下った。琵琶湖は裏日本、表日本の物資を京都・大坂へ運ぶために欠かせない、まさに「天下の回廊」であったのだ。
湖上の水運を支配していたのは中世以来、湖西の堅田衆で、時に海賊まがいのことも行なっていたが、1569年(永禄12)信長が支配下に収めると、回船業の継続を保証した。そのため、71年(元亀2)の朝倉討伐戦には信長に協力した。天正年間、秀吉が京都の玄関口に当たる大津に「大津百艘船」を組織してからは、事実上、秀吉が湖上権を掌握した。
琵琶湖の丸子船
上代以来、日本海沿岸と畿内の物流の中継航路として繁栄した琵琶湖の水運では、丸子船と呼ばれる独特の船が発達した。これは中世の刳船(くりぶね)から発展した構造船で、日本海の北国船に類似したものであった。琵琶湖水運が日本海に直結していた関係から、造船技術の面で影響があったものと考えられる。
大きさは100石積以上の大丸子と、それ以下の小丸子があったが、船形は細長く、舷側(船の横)に「おも木」と呼ばれる半丸太を使用するのが特徴である。その他、専門的な細部の説明は省略するが、当時の典型的な和船構造とはまったく異なる造りであったことだけはたしかである。
しかし、丸子船がいつ頃から存在したのか、史料がまったくといってないため明らかにすることができない。もっとも、海運の本場で造船技術の先進地区であった瀬戸内でも、刳船技術をベースにした準構造船から本格的な構造船へ移行するのが中世後期であるから、琵琶湖においても中世以前ということはないであろう。
屋形船
屋形船の歴史は以外に古く、現存する日本最古の歌集「万葉集」で歌われるほどで、その原形は平安時代に出来上がったと伝えられます。
「屋形」とは、元来「苫(とま)」が発達したもので、日光や雨風をしのぐためのものでした。両者は柱のないものを「苫(とま)」、あるものを「屋形」と区別出来ます。
平安時代以降は貴族の遊船、年貢輸送船、官船、商船、と様々な船に屋形を取り付けるようになりました。当然のことながら、貴族用の豪華な屋形と、庶民的な商船用の屋形とでは、用途が違いますから、構造・装飾などの点で大きな違いがあったようです。また、当時すでに唐風のものも存在し、「唐屋形船」として遊覧に使われていました。
江戸時代には、大名、武家の持ち船として発展したものが多く、それらは「御座船」「楼船」とよばれたのです。更に江戸中期には、大名や裕福な町人達が豪華を競って、金・銀・漆・絵画とあらゆる手段で屋形を飾り付けたり、長さ十一間(約20m)・幅三間(約5.5m)にも及ぶ巨大な船を建造するなど、その繁栄ぶりは素晴らしく、江戸の隅田川を始め、京都の桂川・鴨川、大阪の淀川、岐阜の長良川と各地で活躍した屋形船ですが、幕府が装飾や大きさに制限を加えるようになり、明治の頃には数も減り、小船に簡単な屋形を付けた小規模なものとなっていったのです。
昭和初期には、長さ四間半〜五間(約8m〜9m)の船に、四方に提灯を下げた屋形を取り付けたものが主流で、お客様は半玉さんや芸者衆と一緒に遊ぶ、というのが当時の風景でしたが、そんな風情も戦争とともに吹き飛んでしまいました。しかしながら、戦後の復興期、屋形船も再び甦り、春はお花見船が、夏は涼み船が隅田川を上り・下りで行き通い、それはそれは栄えたものです。
現在に至り、隅田川は昔の姿を取り戻しつつあります。隅田川で生まれ、ともに生きて来た屋形船 濱田屋は、江戸文化の担い手の一人となり、歴史ある文化遺産を気軽に遊びながら、味わっていただける時代となっています。

屋形船(1987.7.24 船の科学館)
江戸 御米蔵
江戸 御米蔵 (現 蔵前1-2丁目)
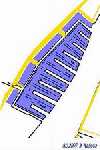 .
.
江戸 御米蔵 (現 両国)
 .
.
⇒ 船の歴史
⇒ 日本の船/和船
⇒ 海の歴史
⇒ 遣明船 勘合貿易
⇒ 大航海時代
⇒ 水軍
⇒ 朱印船 南蛮貿易
⇒ 平戸・長崎 阿蘭陀貿易
⇒ 船鑑
⇒ 船番所
⇒ 御座船
⇒ 下田奉行所
⇒ 浦賀奉行所


新規作成日:2002年2月5日/最終更新日:2002年2月13日







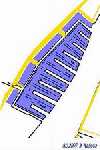 .
.
 .
.

