幕末の海軍
我が国には、古くから「水軍」があり、江戸時代には、幕府や各藩に、お船手、大坂船奉行、船番 などの役職が置かれている。
しかし、これらには、
⇒ 日本の船/和船
⇒ 水軍
⇒ 野島流船軍備之図 解析
⇒ 伊能忠敬測量船団
などに見られるように、関船、小早などと言う沿岸用の和船集団であり、弓矢槍刀で合戦する時代の産物でしかなく、あまっさえ当時は戦闘用と言うよりも、大名行列の海路を受け持つ「御座船」の色彩が強かった。
これに対して、
⇒ 幕末の黒船
に影響を受けた、幕府諸藩は、近代様式軍艦の整備に乗り出した。
そして幕末維新の動乱を経て、近代日本海軍のいしづえとなって行く。
嘉永六年(1853年)、アメリカ東インド艦隊司令長官ペリーは、サスケハナ(2500トン・パーク型蒸気機帆軍艦)を旗艦とする4隻の艦隊で浦賀に来航し、日本は長い鎖国を解かれ、幕府は寛永以来の大船建造の禁も解き、幕府・諸藩ともに洋式船の建造と購入を始める。
幕府(徳川家)の軍艦・船舶
幕府・諸藩は開国直後から洋船の建造に力を注いでゆく。しかし開国直後の日本ではまだ大型船・蒸気機関を作るのは難しく、幕府は軍艦・船舶を外国に買い求める事に主眼を置いて行く。こうして人材を育成し技術を吸収し、幕府海軍は創設される。
新造艦で最新装備を誇る開陽丸、アメリカ使節団の護衛として太平洋横断をした咸臨丸などが有名。
創世期の幕府海軍は雑多な編成だったが、それでも国内で最大の戦力を備えたのは幕府海軍であった。
諸藩・新政府・その他の軍艦・船舶
幕府が洋式船の建造と同時に外国船の購入にも力を注いだのにくらべ諸藩、特に薩摩・佐賀・長州・水戸などは洋式船自力建造に力をいれる。しかし洋式帆船は建造できても建造設備・修理と船体維持の体制・船体強度などは不充分。倒幕維新の世情急な中で、外国からの洋式船購入に頼らざるを得なかった。しかし倒幕諸藩は維新まで幕府海軍ををしのぐ事は出来ず、そのまま新政府へ移管することになった。
徳川幕府は恭順、一部の軍艦引き渡しなどで海軍力は増強、さらに甲鉄(東)の就役と、開陽丸の沈没で函館の旧幕臣軍に有利に立つことになる。
造船所
幕府 浦賀 鳳凰丸
水戸藩 石川島 旭日丸
伊豆君沢郡戸田村 安政2年ディアナ号代船「ヘダ」、安政2年10月と翌年10月、君沢形合計6隻
薩摩藩 昌平丸、鳳瑞丸
佐賀藩
 .
.
 .
.
 .
.
横浜製鉄所
慶応元年(1865)2月に横浜本村に着工。ヴェルニーらの指導により9月には完成し、艦船の修理が可能となった。
明治維新で新政府に引き継がれ、大蔵省、工部省所管を経て、やがて廃止された。
長崎製鉄所
安政2年(1855)長崎海軍伝習所総取締役永井玄蕃守尚志は、第一次海軍伝習教育班を率いる オランダ海軍中佐グ・ファビウスに製鉄所の建設を依頼した。
これを受けて第二次海軍伝習教育班指揮官カッテンディーケ等と共に長崎の製鉄所建設の任務を 帯びた機関将校H・ハルデス率いる配下が、安政4年8月5日に長崎に上陸した。
3年5か月をかけて長崎製鉄所一期工事の竣工を済ませ、文久元年(1861)3月29日に帰国した。
長崎製鉄所はわが国最初の近代的洋式工場であり、日本の産業近代化の原点であった。
また、H・ハルデスは明治以降の最初のお雇い外国人でもあり、日本の産業の近代化に計り知れない 足跡を残した。
日本が開港する安政5年の前年、安政4年10月10日、のちに外国人居留地が建設される大浦の対岸 飽の浦に長崎製鉄所の建設が始まった。
艦船を補修するための本格的な洋式工場建設のための一期工事が文久元年3月25日に落成した。
長崎製鉄所は鍛冶場、鋳物場、ろくろ盤細工所、舎密所、蒸気釜仕立所、蘭人宿舎、仮細工所、 諸職人小屋などで構成されていた。
鍛冶場はわが国最初の煉瓦造建築で、中にはボイラーがあり、2本の煙突がある建物である。
ろくろ盤細工所は工作場とも称し、当時先端の工作機械が設置されていた。この中にあった 堅削盤が残されており、わが国最古の工作機械として国指定の重要文化財になっている。
幕府直営の長崎製鉄所は、明治維新で官営長崎製鉄所となり、明治4年(1871)に工部省所管の長崎造船局と名称を改称した。
後に払い下げられ、三菱長崎造船所として発展して行く。
横須賀製鉄所
フランス公使ロッシュの肝いりにより、技師ヴェルニーらによって建てられたもので、着工の約定書が取り交わされたのは一八六五年二月二四日(慶応元年)のことである。見積もり総額は二四〇万ドルで裏づけは日仏合弁商社設立によるフランスへの生糸の専売権であったが、このフランスの抜けがけに諸外国から非難続出で、結局商社設立は流れている。
フランスから技術導入することを決めた幕府により、一八六五年(慶応元)9月に横須賀製鉄所の名で起工された。所長に就任したのがF・L・ヴェルニー(一八三七―一九〇八)。彼の登場により、一寒村に過ぎなかった横須賀が、近代技術の一大集積地に一変するに至る。
ヴェルニーはパリのエコール・ポリテクニック(理工科大学)を卒業した造船技師だが、経歴以上に有能だった。観音埼灯台を建設したL・フロラン、富岡製糸場を設計したE・バスチャンらを配下に抱え、造船だけでなく、工場・倉庫の建設、灯台設置、レンガ製造、水道工事など、驚くほど幅の広い仕事を推し進めた。全長百二十二・五メートルの第1号ドックは、起工から四年で完成にこぎ着けている。
だがそれ以上に教育を重視し、日本人への技術移転に心血を注いだ功績が計り知れない。所内に黌舎(こうしゃ)と呼ばれる学校を建て、フランス語、数学、物理学などを若者たちにたたき込んだ。その成果は「この造船所ほど伝習がうまくいったケースはないのではないか」と西堀昭・横浜国大教授(日仏交渉史)が語るほどだ。
事実、黌舎からは、軍艦建造に貢献した辰巳一ら、造船技術者だけではなく、近代日本を背負う人材が沸き立つように育っている。
その後、明治政府の手により明治4年(1871)に製鉄所として完成し、後に、横須賀海軍工廠として発展して行く。
遣米使節団
安政7年(1860)1月13日、咸臨丸は品川沖を抜錨、横浜に寄港し16日出帆、19日浦賀を経て太平洋を渡り、2月26日サンフランシスコ港外に到着した。
遣米使節を乗せたアメリカ軍艦「ポーハタン」は、1月22日に横浜を出航している。
 .
.
幕府・諸藩の連合艦隊
文久3年(1863)12月、将軍家茂上洛に際し、幕府・諸藩の連合艦隊が編成された。
12月27日、芝御浜御殿より端舟にて品川沖の翔鶴丸に乗船。翌28日出航、伊豆沖で時化に会い、陸路案も出されたが、翌元治元年1月8日、大阪天保湾に投錨した。
幕府 翔鶴丸(御座船)、朝陽丸、千秋丸、第一長崎丸(長崎丸一番?)、播龍丸
越前藩 黒龍丸
薩摩藩 安行丸
佐賀藩 観光丸(幕府船を借りて、乗組員を佐賀藩より乗船)
加賀藩 発起丸
南部藩 廣運丸
筑前藩 大鵬丸
雲州藩 八雲丸
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
観光丸 (復元船)
幕末の役職
海軍総裁 1862(文久 2.12.)阿波徳島藩主蜂須賀斉裕(ハチスカ・ナリヒロ)が臨時に陸軍総裁兼任で就任。のち老中が海軍を管轄。徳川慶喜の軍制改革により復活し、1866(慶応 2)正規の役職として老中格の稲葉正巳が就任して常置となる
海軍奉行 1865年新設。下野国黒羽藩主大関増裕が初代奉行に就任。のち若年寄の兼任
海軍奉行並
軍艦奉行 1859(安政 6)設置
軍艦奉行並
軍艦奉行頭
軍艦操練所頭取
軍艦頭取
軍艦役頭取
長崎海軍伝習所総責任者
築地海軍操練所監督
幕府海軍の階級
海軍総裁 / Admiral of the Fleet / Admiraal
海軍副総裁 / Admiral / Luitenant Admiraal
海軍奉行 / Vice Admiral / Vice Admiraal
御軍艦奉行 / Rear Admiral / Schout bij nacht
御軍艦頭 / Captain / Kapitein ter Zee
御軍艦頭並 / Commander / Kapitein Luitenant ter Zee
御軍艦役 / Lieutenant Commander / Luitenant ter Zee der 1e Klasse
御軍艦役並 / Sub Lieutenant / Luitenant ter Zee der 2e Klasse
御軍艦役並見習 / Midshipman / Adelborst
曹長 / Fleet Chief Petty Officer
権曹長 / Chief Petty Officer
軍曹 / Petty Officer
伍長 / Corporal
兵 / Seaman
咸臨丸
幕府が最初にオランダに発注した木造コルベット2隻の第1艦が“咸臨丸”(原名ヤパン)です。
“咸臨丸”は、スクリュープロペラ推進の蒸気エンジンを装備するとともに、バーク型の帆装も備えており、汽走と帆走を併用できるようになっていました。
オランダで完成した“咸臨丸”は安政4年(1857)にロッテルダムを出港、艦長のファン・カッテンディーケ海軍大尉以下の教師団によって長崎に回航され、海軍伝習所の練習艦となりました。
万延元年(1860)には、日米通商条約批准(ひじゅん)のための外交使節の随行艦として、軍艦奉行(ぶぎょう)木村摂津守(せっつのかみ)、艦長勝海舟(かつかいしゅう)の他、長埼海軍伝習所でトレーニングを積んだ多くの士官や水夫を乗せてアメリカへと向かいました。
この航海では、往航で冬季の北太平洋を走ったため、難しい操船をよぎなくされましたが、同乗していたアメリカの測量船“フェニモアクーパー”船長ジョン・ブルックとその乗組員の協力も得て、無事大平洋横断に成功し、サンフランシスコに到着しました。
“咸臨丸”は、その後輸送船として使われましたが、明治4年(1871)北海道沖で座礁沈没し、14年の短い生涯を閉じました。
主要要目 排水トン数 625トン、全長 49.7メートル、幅 8.5メートル、船質 木造、主機 蒸気往復動機関(100馬力)、帆装 3本マスト・バーク型、砲 各舷 6門、造船所 スミット造船所(オランダ)
幕末の軍艦
- 艦名 原名 船形 砲 トン数
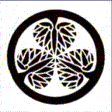 幕府軍艦
幕府軍艦
- 観光丸 スームビンク 蒸気外車 6門
 .
.
 .
.
- 咸臨丸 ヤッパン/日本 蒸気内車 12門
 .
.
- 蟠龍 エンピロル 蒸気内車 4門
- 朝陽丸 エド/江戸 蒸気内車 12門
 .
.
- 富士山 フジヤマ 蒸気内車 12門 1000
- 回天 イーグル 蒸気外車 11門 710
- 開陽丸 蒸気内車 26門
 .
.
- カガノカミ 蒸気内車 6門 530
- 甲鉄 ストーンウォール 蒸気内車/装鉄 4門 700
- 千代田形
 .
.
- 鳳凰丸
 .
.
- 君沢形
 .
.
- 豊島形
- 大元
- 先登 蒸気内車
- 正光 蒸気内車
- 二番回天 蒸気内車
幕府購入船舶
- 鵬翔丸 カタリナテレシヤ バルク 340
- 千秋丸 デニールエブストル バルク 263
- 健須丸 アルテヤ バルク 378
- 千歳丸 アルミステス バルク 256
- 順動丸 ジンキー/仁記 蒸気外車 405
- 昌光丸 ナンキン/南京 蒸気内車 81
- 長崎丸一番 ヴィクトリヤ(Victoria) 蒸気外車 94
- 協隣丸 サントン/山東 蒸気外車 361
- 長崎丸 シアルツアルリス・フヲルブ(Sir Charles Forbes) 蒸気外車 138
- 太平丸 ライモン/鯉魚門 蒸気外車 370
- 長崎丸二番 ジョンリー 蒸気内車 341
- エリシールラス 蒸気内車 85
- 翔鶴丸 ヤンチー(Yangtse)/楊子 蒸気外車 350
- 神速丸 メテヨ 蒸気内車 250
- 黒龍丸 コムシング/金星 蒸気内車
- 太江丸 ターキヤン/太江 蒸気内車
- 美加保丸 ブランデンボーグ バルク 800
- 鶴港丸 マツテツリュス バルク 305.8
- 龍翔丸 マルクリー 蒸気内車 66
- 長鯨丸 ドムバルトン 蒸気外車 996
- 奇捷丸 タバンニヨー 蒸気内車 517
- ケストル 蒸気内車 161
- 行速丸 フイセン 蒸気外車
- 千歳丸 ラウアリ バルク 323
- 飛龍丸 プローミス 蒸気内車
 薩摩藩購入船舶
薩摩藩購入船舶
- 船名 原名 船形 トン数
- 天祐丸 イングランド 蒸気内車 746
- 永平丸 フイリーコロス 蒸気内車 447
- 白鳳丸 コンテスト(Contest) 蒸気内車 532
- 安行丸 サーラ(Sarah) 蒸気内車 160
- 平運丸 スコットランド 蒸気内車 750
- 胡蝶丸 ホーキン/福建 蒸気外車 146
- 翔鳳丸 ロチユス(Lotus) 蒸気内車 461
- シアルジョルジゲレー(Sir George Grey) 蒸気内車 492
- 乾行丸 ストルク(Stork) 蒸気内車 6門 164
- 豊瑞丸 ノムプルウアン 蒸気内車
- 龍田丸 ハントルス(Huntress) バルク 383
- 開聞丸 フィオラ(Viola) 蒸気内車 684
- 萬年丸 キンリン(Kinlin) 蒸気内車 270
- 三國丸 ゼラール(Gerarad) 蒸気内車 410
- 櫻島丸 ユニヲン(Union) 蒸気内車 205
- 大極丸 ウイルウエイフ(Wild Wave) スクネル
- 春日丸 キヤンスー 蒸気外車 1015
 長州藩
長州藩
- 庚申丸 蒸気内車
- 千戌丸 ランスヒールト 蒸気内車 448
- 癸亥丸 ランリツク ブリキ 283
- 丙寅丸 テントウ 蒸気内車 94
- 丁卯丸 ヒング 蒸気内車
- 乙丑丸 ユニオン(Union) 蒸気内車 300
- 昇平丸
 .
.
 土佐藩
土佐藩
- 南海丸 サンハイ/上海 蒸気内車 .
 .
.
- 胡蝶丸 ヒョウゴ(兵庫)/当初フーキーン 蒸気外車 146
- 夕顔 スーイリン(Shunleen)/朱林 蒸気内車 659
- 横笛 セイボルン スクネル 265
- 羽衣 カツヒルチーマ スクネル 186
- 南海船 ナンカイ 蒸気内車 4門 140
- 乙女 ヲーサカ/大阪 バルク 386
- 蜻蛉 スパンキー 蒸気内車
 肥前藩
肥前藩
- 電流丸 ナカサキ 蒸気内車
 .
.
- 甲子丸 カテージ(Carthage) 蒸気内車 8門 500
 .
.
- 皐月丸 エド 蒸気内車 370
 .
.
- 孟春丸 イウゼニー 蒸気内車 4門 299
羽後/秋田藩
- 福海丸
 .
.
伊予松山藩
- 弘済丸
 .
.
伊予/宇和島藩
- 開産丸
 .
.
大野藩
- 大野丸
 .
.
 加賀藩
加賀藩
- 駿明丸
 .
.
- 啓明丸
 .
.
 肥後/熊本藩
肥後/熊本藩
- 万里丸
 .
.
- 凌雲丸
 .
.
- 奮迅丸
 .
.
久留米藩
- 遼鶴丸
 .
.
小城藩
- 大木丸
 .
.
筑後/佐賀藩
- 凌風丸
 .
.
- 晨風丸
 .
.
 庄内藩
庄内藩
- 龍神丸
 .
.
 陸前/仙台藩
陸前/仙台藩
- 開成丸
 .
.
津藩
- 神風丸
 .
.
 阿波/徳島藩
阿波/徳島藩
- 乾元丸
 .
.
- 通済丸
 .
.
 南部藩
南部藩
- 廣運丸
 .
.
備中松山藩
- 快風丸
 .
.
 安芸/広島藩
安芸/広島藩
- 震天丸
 .
.
- 達観丸
 .
.
 筑前/福岡藩
筑前/福岡藩
- 大鵬丸
 .
.
 福山藩
福山藩
- 順風丸
 .
.
松江藩
- 八雲丸一番
 .
.
- 八雲丸ニ番
 .
.
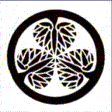 水戸藩
水戸藩
- 旭日丸 三檣シップ
越前藩
- 大野丸 スクーナー
箱館奉行所
- 箱館丸 トップスル・スクーナー
- 亀田丸 トップスル・スクーナー
⇒ 船の歴史
⇒ 日本の船/和船
⇒ 海の歴史
⇒ 大航海時代
⇒ 水軍
⇒ 野島流船軍備之図 解析
⇒ 平戸・長崎 阿蘭陀貿易
⇒ 和船の海運
⇒ 御座船
⇒ 幕末の黒船
⇒ 幕末の海軍伝習・操練所
⇒ 幕末の海戦
⇒ 亀山社中と海援隊
⇒ 幕末明治 江戸 龍馬の足跡
⇒ 東京湾の城塞
⇒ 帆船時代の艦載兵器


新規作成日:2002年2月1日/最終更新日:2002年11月30日
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.
 .
.

