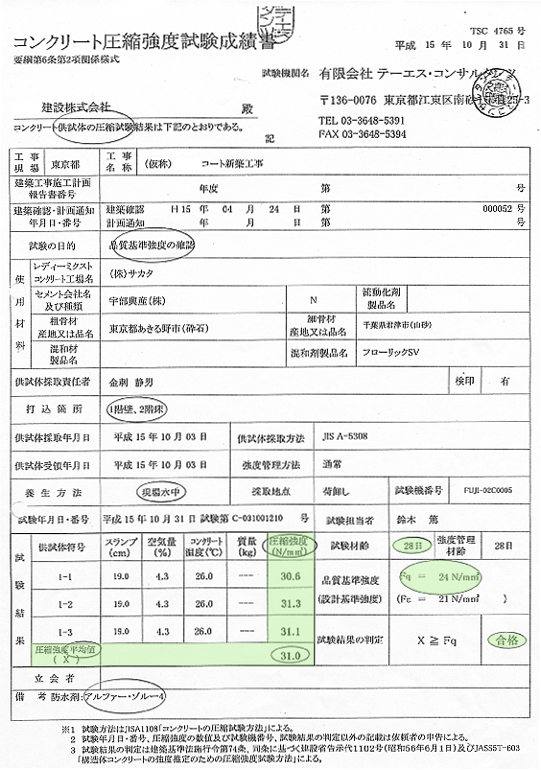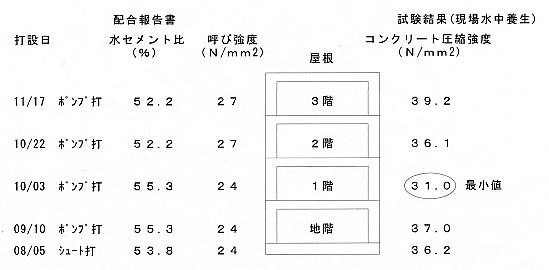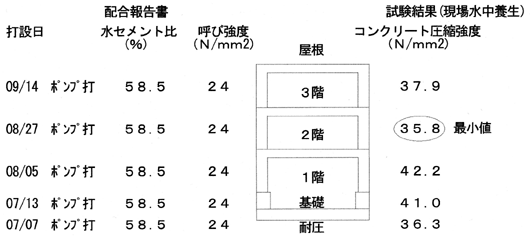|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| コンクリートの圧縮強度とは |
|
| N/mm2は、コンクリート強度を表す単位です |
|
|
ニュートン・パー平方ミリメートルと読みます |
|
| 1N/mm2とは1m2当りでは約100t の圧力まで耐えられることを示します |
|
| コンクリート圧縮強度とは、コンクリート打ちから4週間後の材令28日の圧縮強度 |
|
| で、これが基準です。 普通、コンクリート強度と言ったら、すべてこの材齢28日の |
|
| 圧縮強度(4週強度)のことを指しています。材齢28日の強度は、そのコンクリートが |
|
| 本来持っている強度の約80%です。100%強度が出るピークは諸説あるようですが、 |
|
| 3年〜30年位 と、いろいろです。 |
|
|
|
生コンの呼び強度は、通常18�・21�・24・27・30・33・36・40N/mm2とありますが、 |
|
| ごく一般的に使われているコンクリートは、設計基準強度は21N/mm2で、 |
|
| 品質基準強度は24N/mm2です。 |
|
|
|
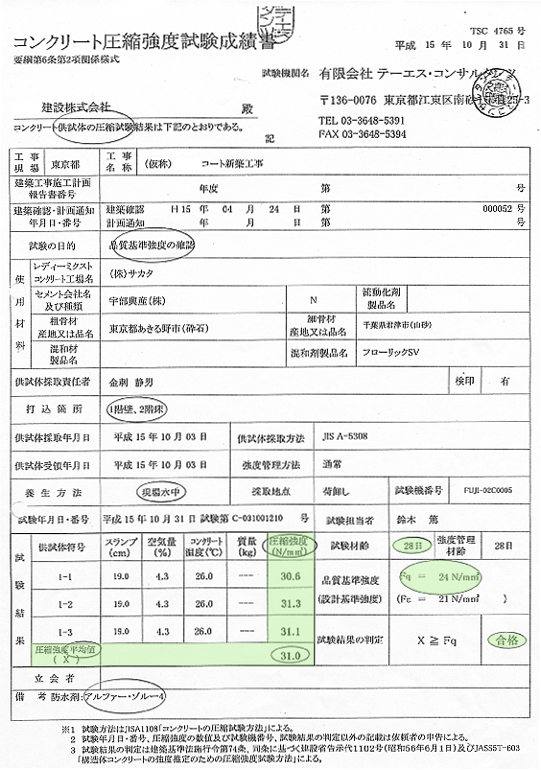 |
|
| 上記の表は実際のコンクリート圧縮強度試験成績書の例です。この表の下部に |
|
|
|
|
| 試験結果の欄があり、圧縮強度平均値として、31N/mm2になっていて、 |
|
|
|
| 材齢28日品質基準強度24N/mm2以上なので、判定は合格です。 |
|
 |
|
|
| コンクリート打ちの現場で採取されたテストピース(供試体)とスランプ試験です。 |
|
| 9本のテストピースの内、3本が7日目に、3本が21日目に、3本が28日目につぶし試験をします。 |
|
| 7日目と21日目のつぶしは、施工上必要と思われる時に強度を確認するためのものです。 |
|
| 下記の図表は当設計の実例1で5回分の水セメント比とコンクリート圧縮強度試験(材齢28日)の結果です。 |
|
|
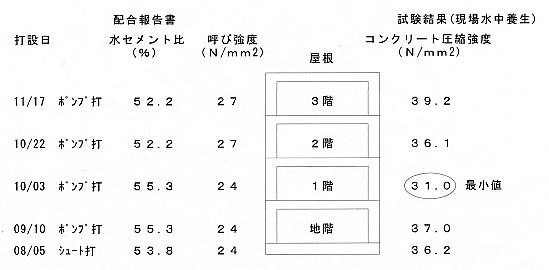 |
|
|
| この建物は設計基準強度21N/mm2 品質基準強度24N/mm2 で設計し、躯体防水剤アルファゾル4を、 |
|
| 現場添加したコンクリートです。試験結果の値が高いのは、生コンの温度補正や防水剤添加が原因と思われます。 |
|
| この建物の圧縮強度は最小値の31.0N/mm2で、結果として計画供用期間はおよそ100年です。それ以上の |
|
| 構造体コンクリートの信憑性は現場にて、コアを抜き取り、中性化の深度の測定やつぶし調査等をして判定します。 |
|
|
|
注:生コンの温度補正とは コンクリート打ちから28日間の平均気温に対応して、生コンの 呼び強度 を上げて、 |
|
|
強度補正とするものです。 |
|
|
|
|
| 下記の図表は当設計の実例2で5回分の水セメント比とコンクリート圧縮強度試験(材齢28日)の結果です。 |
|
|
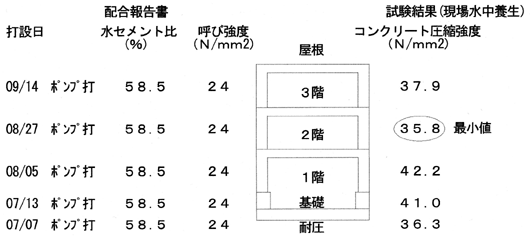 |
|
|
| この建物は設計基準強度21N/mm2 品質基準強度24N/mm2 で設計したコンクリートです。 |
|
| この建物の圧縮強度は最小値の35.8N/mm2で、結果として計画供用期間はおよそ200年弱です。それ以上の |
|
| 構造体コンクリートの信憑性は現場にて、コアを抜き取り、中性化の深度の測定やつぶし調査等をして判定します。 |
|
|
住宅性能表示のコンクリートの劣化対策等級は下記のようになっています。 |
|
|
|
等級3 建築基準法のかぶり厚さの場合は水セメント比45%以下 |
|
|
|
| 建築基準法のかぶり厚さ +10mmの場合は水セメント比50%以下 |
|
| 等級2 建築基準法のかぶり厚さの場合は水セメント比50%以下 |
|
|
| 建築基準法のかぶり厚さ +10mmの場合は水セメント比55%以下 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|