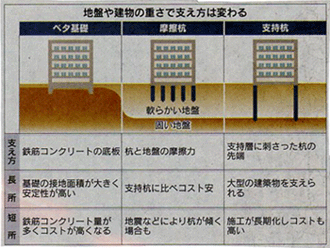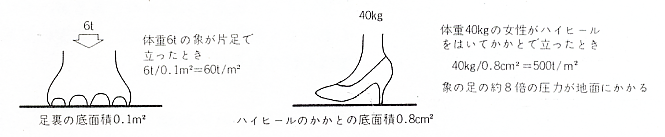|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基礎の設計 |
|
| くい基礎 べた基礎 布基礎 どの基礎にしますか |
|
|
それにより基礎工事費が大きく違います |
|
|
| 杭基礎はどうしても、べた基礎又は布基礎 + 杭になり、杭工事費分が増額に |
|
| 現在建物を建てる場合、木造・鉄骨造・ブロック造・RC造等 |
|
|
| 考えられますが、その基礎はすべて鉄筋コンクリートで造られ |
|
| ます。このRC基礎をどの深さの地盤に安定的に載せるかが |
|
| 不同沈下・家が傾いたりしないための重要なポイントになります。 |
|
|
地盤の長期地耐力と選択できる基礎の方式 |
|
|
| 長期地耐力 KN/m2 |
くい基礎 |
べた基礎 |
布基礎 |
| 30以上 (3t/m2以上) |
○ |
○ |
○ |
| 20以上30未満(2t以上3t/m2未満) |
○ |
○ |
× |
| 20未満 (2t未満/m2) |
○ |
× |
× |
|
|
|
|
|
|
10kN/m2とは → 1トン/m2 のことです |
|
|
| 長期地耐力は現場の地質調査の結果によります。 |
|
|
| 山の手の地盤の状況は、GLから約1m前後が腐植土や盛土になっていて、 |
|
| その下に関東ローム層があり、このローム層に基礎の底盤を直接のせれば |
|
| 万全です。また、地盤改良には表層改良や、ラップルコンクリートや、 |
|
| ソイルセメント 等があります。しかし、ベタ基礎をローム層にのせる方法が |
|
| 多少基礎の深さが深くなりますが、一番経済的です。 そうすると、常水面 |
|
| より上で、1階床下に物入れ 等もつくれます。 |
|
| 杭工事としては、既成コンクリート杭・鋼管杭・現場打コンクリート杭(BH)等 |
|
| があります。 |
|
|
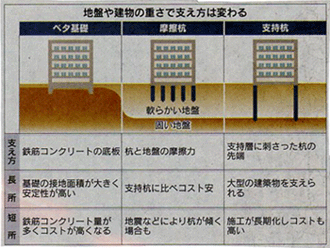 |
|
|
|
|
|
|
| RC基礎の下面には、その基礎の重さから始まって、使われて |
|
| いる全ての建材の重さ(固定荷重)と、その建物の中にいる人 |
|
| や家具等の重さ(積載荷重)と、屋根に積もる雪の重さ(積雪 |
|
| 荷重)の合計の重さがかかります。基礎の下の地盤はこの重さ |
|
| にびくともしない事が求められます。 |
|
| 基礎とは、建物の全荷重を安全に地盤に伝達し、かつ |
|
|
|
|
|
| 水平構面を固めるためのものです。 |
|
| 全荷重を安全に地盤に伝えるには、力を分散して地盤に伝えることです。 |
|
|
水平構面を固めるとは、建物が重力や台風や地震の力で、 |
|
|
| ばらけないようにすることです。 |
|
| ぞうの足とハイヒールどちらの接地圧が大きいのだろうか |
|
|
| 下図の例にみるように、接地部分の底面積を広げたほうが、 |
|
| はるかに有利なことがわかります。 |
|
|
ぞうの足とハイヒール |
|
|
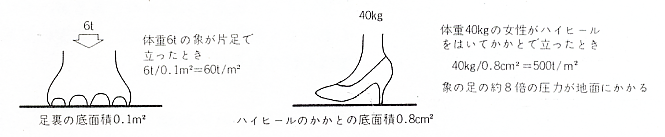 |
|
|
建物の基礎も、ぞうの足と同じで、底面積を広げた方が荷重が分散され、より安定します。 |
|
| また、基礎と道路や隣地の境界線との間に余裕があれば、フーチンを広げることも可能で、 |
|
| より、基礎の底面積を大きくできますので、安定した建物になります。 |
|
|
建物の全荷重と、基礎の底面積と、地盤の長期地耐力のバランスを計っていきます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|